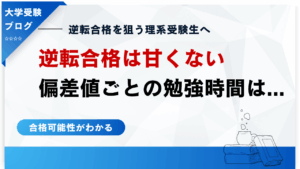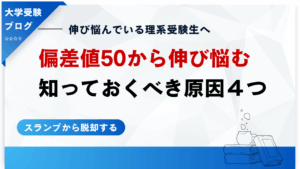夏休みに勉強しなかった受験生|今から追いつくたった2つの方法
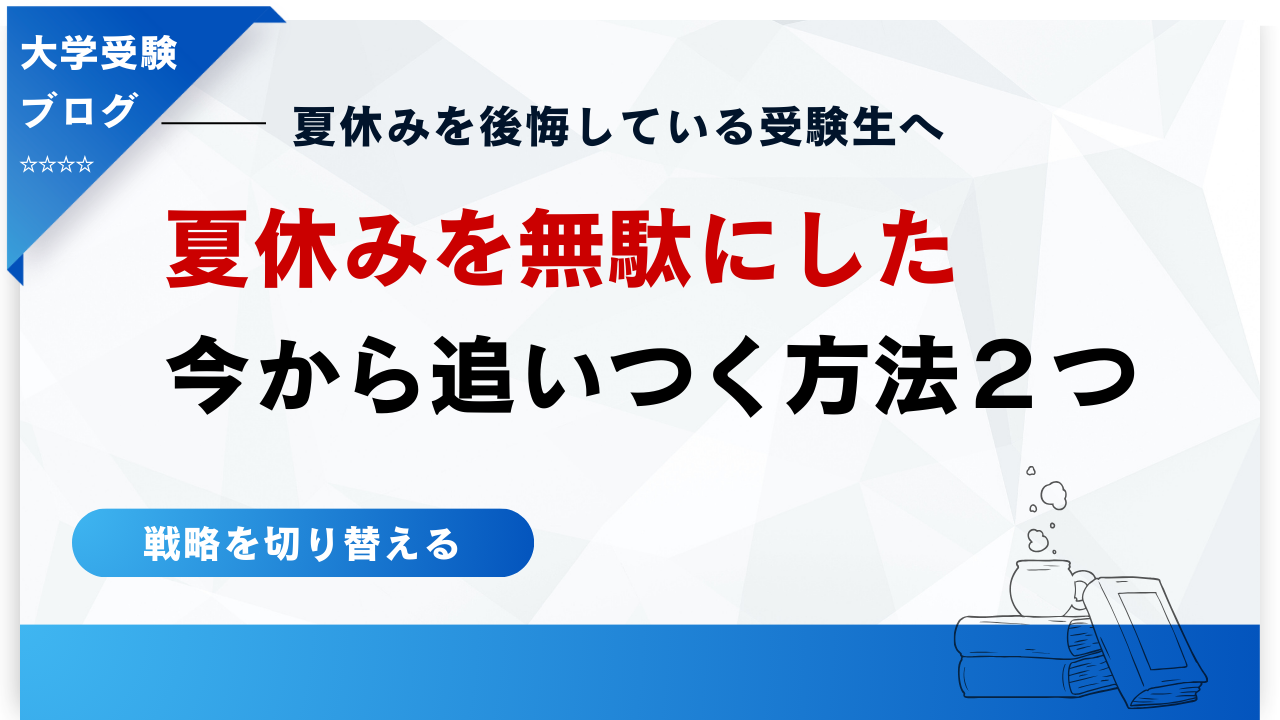
夏休みなのに思うように勉強できなかった、今から周りに追いつけるかな…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

今年の夏休みこそは頑張るつもりだったのに、結局いつもと変わらなかった…

周りのライバルは成績が伸びているのに、夏休みにあまり勉強できなかった…
正直に言えば、夏休みに思うように勉強できなかったことは、受験生にとって致命的です。
なんで妥協してしまったんだろう、夏休みの初日に戻らないかな
過ぎたことを嘆いても仕方ありません。失った過去を悔やむのではなく、その時間を今からの挽回にどう使うかを考えましょう。
✔︎ 夏休みに勉強できなかった末路
✔︎ 夏休みの遅れを取り戻す方法
✔︎ サボりを再発させない行動方法
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
夏休みに勉強しなかった損失
これから挽回をするには、まずどれほどの損失を埋めなければならないのか、そのハードルを正しく認識する必要があります。
❶ 物理的には追いつける損失の場合
❷ 物理的に追いつけない損失の場合
❶ 物理的には追いつける損失の場合
代表的なケース
目標が妥当
夏休みは休日が多いため、普段の休日と同程度の勉強量を毎日の計画に組み込んだ
実際の成果
少し気が緩んで計画した分量には届かなかったが、少なくとも7割は達成できた
代表的なケース
目標が高い
基礎が固まっているので、過去問対策や二次試験に向けた応用対策の計画を立てた
実際の成果
日頃の学習を優先したため、過去問や二次レベルの応用問題には取り組めなかった
これらのケースは、勉強習慣や学習量をこなす力は備わっており、夏休みの計画を達成できなかっただけです。そのため、その損失を本番までに埋められれば問題はありません。
例えば、夏休みに「毎日10時間勉強する」と目標を立てたものの、実際には1日7時間しかできなかった場合、夏休み30日で合計90時間の損失になります。
本番直前期である12月まで残り90日あるとすると、1日1時間増やせば埋め合わせ可能です。これは日常生活の工夫で十分に捻出できる範囲です。
さらに、参考書演習などで基礎が固まっていれば、基礎が不十分な場合に比べて挽回しやすくなります。
❷ 物理的に追いつけない損失の場合
代表的なケース
目標が高い
夏休みは自学の時間を確保できるため、日頃の勉強よりも大幅に高い目標を設定した
実際の成果
1日あたりの目標量を高く設定していたが、実際にはその大部分を達成できなかった
代表的なケース
目標が高い
これまでは忙しさを理由に勉強しなかったが、夏休みに向けて理想的な計画を立てた
実際の成果
毎日の勉強量を設定したものの、実際には習慣が身につかず、数日でやめてしまった
これらのケースは、現在の勉強習慣や学習の許容量を大きく超えた目標を掲げてしまい、理想通りに実行できなかった例です。
例えば、夏休みに「毎日8時間勉強する」と目標を立てたものの、実際には2日に1回3時間しかできなかった場合、夏休み30日で合計195時間の損失になります。
本番直前期である12月まで残り90日あるとすると、1日2時間ほど増やさなければなりません。しかし、それ以上に問題なのは、時間そのものではなく、その膨大な勉強量を毎日継続できる習慣がまだ身についていない点です。
この場合、仮に物理的な時間が残されていても、習慣化に至るまでに日数が刻々と失われていくため、追いつく難度は日に日に高まっていきます。
夏休みの遅れを取り戻す方法
先ほどは夏休みに遅れをとった場合の損失について述べましたが、ここからはその損失をどのように挽回するか、ケースごとに方法を紹介します。
❶ 物理的には追いつける損失の場合
夏休みの損失を大まかに把握し、残りの日数で1日あたりどれくらい挽回する必要があるかを具体的に見積もる
具体的に見積もった1日あたりの追加量をこなすために、1日のルーティンをどのように調整するかを決める
挽回する量を見積もる手順
❶ 目標量を振り返る
目標が勉強時間
目標がページ数
目標が参考書数
まずは、夏休みに終える予定だった具体的な目標量を振り返りましょう。
立てていた目標が「1日あたりの勉強時間」であれば夏休み全体の合計勉強時間を、ページ数であれば合計ページ数を、参考書数であれば合計冊数を把握します。
❷ 達成量を振り返る
実際の勉強時間
実際のページ数
実際の参考書数
次に、夏休みに実際に終えられた具体的な量を振り返りましょう。
勉強時間であれば、日々のおおまかな勉強時間から合計を算出し、ページ数や参考書数であれば、どこから始めてどこまで進んだかを確認します。
❸ 目標との差を知る
目標量と達成量の差を知る
目標量と達成量を把握できれば、これから挽回すべき量が明確になります。
ページ数であれば、これまでの1時間あたりの進捗ペースから必要なおおよその勉強時間を見積もり、参考書数であれば、1冊を終えるのに必要なおおよその勉強時間を想定します。
そのうえで、残りの日数で1日の勉強量をどれだけ増やす必要があるかを把握しましょう。
1日のルーティンを調整する方法
基本となる考え方
優先度の低い生活時間を順に削り、勉強時間へと充てる
1日の生活の中にまだ余白がある場合は、その時間を勉強に充てればよい。
しかし、すでに余白を使い切っている場合は、今の生活から優先度の低いものを順に削り、勉強時間を捻出する必要があります。
Point1 準備時間
Point2 食事時間
Point3 入浴時間
Point4 移動時間
Point5 休憩時間
Point6 雑談時間
起床直後の準備時間や勉強を始めるまでの時間は、無駄が生じやすく削減しやすい例です。特に、目覚ましが鳴った後にスマホを見て目を覚ます時間や、ゆったりと準備している時間は、場合によっては30分以上削れることも少なくありません。
自力での制御が難しい場合は、保護者の協力を得てでも、起床後や準備に制限時間を設けて行動するとよいでしょう。
1日に食事は3回ありますが、1回の食事時間は平均すると30程度のようです。スマホやテレビを見ながらだと時間がかかりますが、食事に集中すれば1食あたり10〜20分で終えられます。
もし「ながら食事」で時間をかけすぎているのであれば、極端に早口にならない範囲で、時間短縮を意識するとよいでしょう。
お風呂時間は2つの使い方があります。1つは、髪や体を洗って流す一連の手順を手早く済ませ、お風呂時間を10分程度に収める方法。もう1つは、お風呂時間をゆったり使い、入浴中に暗記科目などの勉強を行なう方法です。
おすすめは、普段はできるだけ入浴時間を短縮し、疲れているときや湯船に浸かりたいときは、暗記科目の勉強を風呂場に持ち込んでゆっくり入浴する、といった使い分けです。
移動時間は多くの場合、避けられないものです。電車やバスなどの交通機関を利用する場合は、移動中に英単語やリスニング対策、暗記科目を勉強しましょう。
一方、自転車や徒歩のときは、前日に勉強した内容を思い出したり、理解したことを自分に説明するように脳内で復習するのがおすすめです。
大前提として、休憩時間は少なくとも1時間に5〜10分、または2時間に10〜20分を目安にとりましょう。ただし、休憩が長すぎたり頻度が多すぎたりする場合は、必要な範囲に収めるようにしてください。
また、家庭でのトイレ休憩など短い時間でも、暗記教材を置いたり壁に暗記内容を貼ったりすることで、目にする回数を増やし記憶の補強につなげられます。ただし、同じものを貼りっぱなしにすると慣れて視界から消えてしまうため、1〜2週間ごとに内容を入れ替えると効果的です。
友だちと同じ空間で勉強している場合や、学校・塾の自習室を利用している場合には、雑談が生じることもあるでしょう。会話はストレス発散や情報収集の面で有益なので、大いに楽しんで構いません。
ただし、必要以上に時間を費やすのは本末転倒です。あらかじめ定めた休憩時間の範囲内にとどめ、休憩が終わったら切り替えて勉強に戻るようにしましょう。
Step1 集中できた環境を振り返る
Step2 集中に差があった要素を列挙
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
❷ 物理的に追いつけない損失の場合
基本となる考え方
夏休みに失った勉強量は潔く諦め、志望大学の出題傾向から逆算して勉強範囲を絞る
物理的に追いつけない場合は、無理に挽回を試みるよりも、残りの時間で最大限できることに振り切った方が賢明です。
できることとできないことを取捨選択し、限られた時間で最大の成果を狙う、弱者が強者に勝つ可能性を残すための戦略的転換です。
その際に必要となるのは、単なる博打に終わらせないために、出題傾向や配点の重みに基づいて優先度を逆算するという、徹底したリサーチです。
リサーチするべき項目
❶ 共テと二次試験の配点割合
❷ 共テと二次の教科別配点割合
❸ 共通テストの出題単元と配点
❹ 二次試験の頻出単元と配点
❺ 二次試験の大問別の難易度
まずは共通テストと二次試験の配点割合を確認しましょう。どちらかに大きく偏っていて、現実的にその対策に集中すれば合格ボーダーを狙えそうな場合は、いずれかに注力するのが有効です。
たとえボーダーに届かなくても、軸足をどちらかに置ければ時間短縮につながるので、必ず確認しておきましょう。
次に、共通テストと二次試験を合わせた教科別の配点割合を確認しましょう。こちらも❶で述べた通り、特定の教科に大きく偏っている場合は、その教科に軸足を置くことで時間短縮につながります。
次は、共通テストの頻出単元と配点を調べましょう。教科によっては出題単元が固定されているものもあるため、毎年変動する可能性のある単元だけを確認し、どの単元が頻出なのか、また各単元の配点がどうなっているのかを把握してください。
最悪の場合、対策が間に合わなければ、配点の低い単元を割り切って捨てるという選択肢もあります。
次は、二次試験の頻出単元と、大問ごとの配点を確認しておきましょう。過去5年から10年の出題単元を見ておくと、目処がつきやすいです。
❶ 過去問を直近10年分確認する
❷ 10年中7年以上出ている単元は必須
❸ 10年中3年以下の単元は捨ててよい
10年間のうち4年以上7年未満出題されている単元は、過去2〜3年出題されていなければ警戒しておきましょう。また、直近で2年以上連続して出題されている単元についても警戒が必要です。
最後に、二次試験の大問ごとの配点とその難易度を、問題と解答解説に目を通して確認しておきましょう。
大問によっては難易度や配点に大きな差があるため、現実的に考えて残りの期間でどの大問なら得点を狙えるのか、どの大問は得点が難しいのかを判断しておくことが重要です。
力を入れるべき優先順位をおおまかにでも把握できれば、あとはそこに力を集中させる勇気を持って行動するだけです。
サボりを再発させない行動方法
これからの行動を変えるためには、夏休みの勉強でなぜ失敗したのか、その根本原因を把握しておく必要があります。原因を特定しないまま変えようとしても、高い確率で同じ過ちを繰り返してしまうからです。
失敗の原因を具体的に特定する
Step1 集中できた環境を振り返る
Step2 集中に差があった要素を列挙
集中できた環境を振り返る
具体的にやること
これまでの人生を振り返り、比較的集中できた勉強場所と、集中ができなかった勉強場所を思い出す
まずは、中学受験や高校受験、定期テスト直前など、これまでを振り返り、比較的集中して勉強できた場所とできなかった場所を挙げましょう。
✔︎ 塾の自習室
✔︎ 学校の自習室
✔︎ 図書館
✔︎ 公民館
✔︎ カフェ・ファミレス
✔︎ 自宅
これらのうち、集中できた勉強場所が自宅以外で、集中できなかった場所が自宅だった場合、そもそも「家では集中できない」タイプです。そのため、外の勉強環境に主軸を置き、家での勉強時間を減らすことを考える必要があります。
集中に差があった要素を列挙
具体的にやること
同じ場所で勉強した際に、集中できたときと集中できなかったときとで、どのような差があったのかを考える
過去の勉強場所を一つ思い出したとき、程度の差はあっても、集中できたときとできなかったときがあるはずです。その際、どのような違いがあったのかを、思いつく限り挙げてみましょう。
✔︎ スマホの有無
✔︎ 周囲の騒がしさ
✔︎ 周囲の人数の多さ
✔︎ 眠気の有無
✔︎ 空腹の有無
✔︎ 勉強内容の不明の有無
これらのうち、周囲の騒がしさや人数の多さを除けば、自分の行動次第で調整できます。
たとえば、スマホの場合は通学定期をカード型にしてスマホを家に置いて外出する、眠気や空腹がある場合はその場で仮眠を取ったり休憩中に間食を挟む、勉強内容がわからない場合は一旦飛ばし、帰宅後にスマホで調べるなど、自分なりのルールを設ければ解決できます。
一方で、周囲の騒がしさや人数の多さは自分では制御できないため、勉強場所そのものを変える必要があります。比較的集中しやすい環境を、自宅や学校から1時間圏内で探してみましょう。
原因を再発させないよう工夫する
自分に合った勉強場所へ欠かさず通うための、一連のルーティンと自分ルールを決める
集中に差があった要素(タップで移動可)を克服できても、勉強場所に通う習慣がなければ、日々の勉強量に大きなブレが生じ、夏休みの二の舞になりかねません。
たとえば、平日は学校から直接勉強場所へ向かう、休日は親に起こしてもらい身支度をしたらすぐに勉強場所へ行く、などのように、勉強場所に向かうまでの流れを統一しておくことが大切です。
ルーティンと自分ルールの例
平日はスマホを家に置いて登校し、授業が終わり次第そのまま図書館へ向かって20:30まで勉強する。帰宅後は22:30~23:30の間を「追加の勉強やわからなかった問題の調べ物をしてよい時間」とし、それ以外のおうち時間は潔く息抜きに回し、図書館でできるだけ勉強をすることでメリハリをつける。
休日は朝起きられないと1日を無駄にしてしまうため、8:00に親に起こしてもらい、朝食と身支度を済ませたらスマホを持たずにすぐに図書館へ向かい、9:30から勉強を開始できるようにする。終了時間は早めでも構わないので、毎日の勉強習慣に慣れるまでは「行く」こと自体を目標に掲げる。
揺るぎない習慣をつくるポイントは、無理な目標や強いモチベーションがなければ一歩を踏み出せないような目標を掲げないことです。無理なくこなせる目標を立て、日々の成功体験を積み重ねていくことが大切です。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。