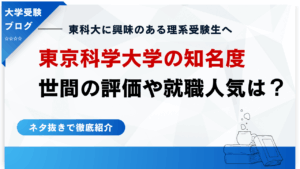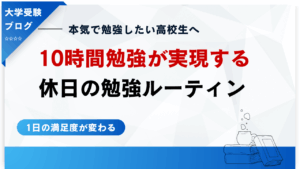【理系決定版】高1〜高3がやるべき9月の勉強法とおすすめ参考書を学年別に紹介
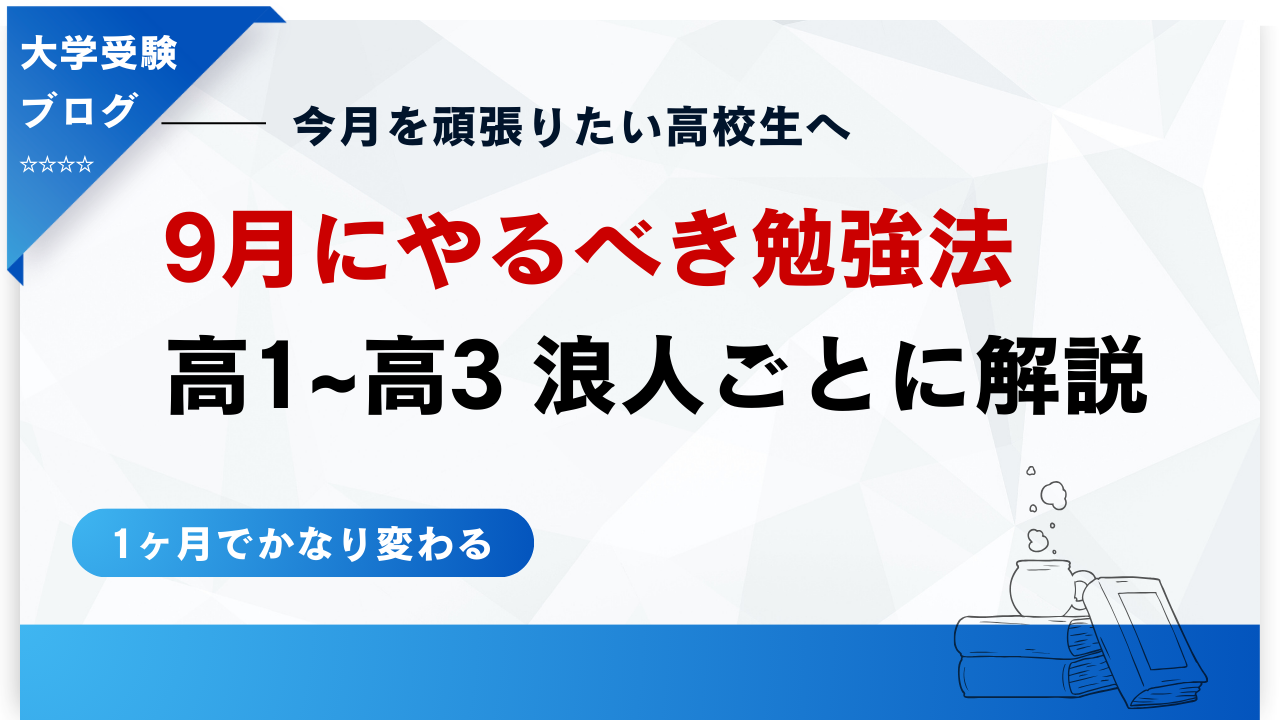
夏休みは思うように勉強が進まなかったけど、9月から切り替えて巻き返したい…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

気づけば夏休みも終わってしまって、もう新年まで3ヶ月ちょっとしかない…

年末までに必要な勉強をやり切って、夏までの遅れを少しでも取り戻したい…
9月は、夏休みで崩れてしまった習慣や予定していた勉強を見直しながら、年末までにこなすべき学習量を進めていく大切な時期です。
夏休みにできなかった分は、1日の勉強量を増やして9月で一気に巻き返す!
こう意気込む人も少なくないと思いますが、実はこの考え方は非常に危険で、かえって勉強全体の量を減らしてしまう可能性すらあります。
そこで本記事では、9月の勉強のあるべき姿を正しく認識し、そのうえで取り組むべき勉強法とおすすめ参考書を、高1〜高3・浪人生に分けて具体的に解説していきます。
✔︎ 9月に集中して勉強するコツ
✔︎ 各学年における9月の勉強法
✔︎ 9月にやるおすすめの参考書
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
夏休みの失敗原因を振り返る
夏休みに予定していた理想のプラン通りに勉強できた人は、読み飛ばしてかまいません。しかし、予定していた分量を終えられなかったり、思ったより集中できなかったりした場合は要注意です。
目標が達成できなかった原因
❶ 目標プラスアルファを望んだから
❷ 理想的すぎる目標を立てたから
❸ パフォーマンスが低下したから
目標を達成できなかったと感じるときは、上記の3つのいずれかに当てはまります。どれに該当するかによって、根本的な原因も対策も異なります。
❶ 目標プラスアルファを望んだから
原因
本来やるべき分量は終えて目標自体は達成できているものの、プラスアルファで取り組みたかった分量が終わっていないために、達成感を得られていない
このケースに当てはまる場合、夏休みの勉強に対する不安は気にしなくても大丈夫です。予定はどうしても高めに立てがちであり、やるべき目標を達成できているだけでも十分です。
自信を持って、9月にやる勉強法に移り、目の前のやるべきことに集中していきましょう。
❷ 理想的すぎる目標を立てたから
原因
現在の能力を大きく超える目標を立ててしまった結果、現実のパフォーマンスと理想の勉強量との間に大きな乖離が生じてしまった
このケースに当てはまる場合は、かなり危険な状態です。これまでの長期休みでも同じように、休み前に理想的な目標を立てたものの、まったく予定通りに進まなかった経験がある人は特に注意が必要です。
その場合は、まず今の自分でも確実にこなせる量から目標を設定し、リハビリのつもりで取り組むことが大切です。それを毎日継続できるようになってから、少しずつ量を増やしていきましょう。
❸ パフォーマンスが低下したから
原因
勉強の習慣自体は身についていて、夏休み中も毎日勉強はしていたものの、1日あたりの勉強量がいつもより少なくなってしまった。
このケースでは、普段の勉強量からどれだけパフォーマンスが落ちているかによって、再発の危険度が変わります。次の例のうち、どちらに当てはまるか確認してみましょう。
失敗例 ①
目標が妥当
夏休みは休日が多いため、普段の休日と同程度の勉強量を毎日の計画に組み込んだ
実際の成果
すこし気が緩んで計画した分量には届かなかったが、少なくとも7割は達成できた
失敗例 ②
目標が妥当
夏休みは休日が多いため、普段の休日と同程度の勉強量を毎日の計画に組み込んだ
実際の成果
夏休みで時間があった分、息抜きや仮眠が増えてしまい、半分も達成できなかった
失敗例①の場合は、多少失速して目標を達成できなかったかもしれませんが、夏休みから通常の日常生活へと環境が戻ることで、自然と元に戻ります。
一方、失敗例②の場合は、夏休み前までは新学年の緊張感によって頑張れていたものの、夏休みを機にその緊張が解けてしまい、習慣ごと失速してしまったケースです。
9月の目標は、夏休み前よりも分量を減らし、確実に達成できるところから徐々に増やしていく。もともとできていたこともあり、比較的早く元の状態に戻せる。
9月の勉強量を成功させるコツ
ポイント
目標は3段階にレベル分けする
必ず自分に合う環境で勉強する
目標は3段階にレベル分けする
勉強が継続できなくなる原因は、目標達成の失敗が続いてしまうことと、巻き返そうとする際のハードルの高さにあります。
Lv1. 最低限の目標
定義
やむをえない事情がない限り、今の自分の力でも必ず達成できる最低限の目標のこと
Lv2. 標準の目標
定義
今の自分の能力から現実的に考えて、少し努力すれば達成できる標準的な目標のこと
Lv3. 理想の目標
定義
今の自分の能力から考えて、相当な努力をしなければ達成できない理想的な目標のこと
Lv.3は調子がかなり良いときに達成できるレベル、Lv.2は達成できればその日の満足度が高まるレベルの目標となります。
Lv.1の達成を目標に進めていけば、自然とLv.2の達成にも近づいていきます。もし「勉強が継続できない」「集中力が続かない」などの悩みを抱えている場合は、Lv.1を毎日の目標として掲げましょう。
上記のケースに当てはまる場合のLv.1の目標は、自分に合った勉強環境に身を置いて勉強すること
必ず自分に合う環境で勉強する
では、自分に合う環境とは何か。それは、モチベーションの高低にかかわらず、そこに身を置けば自然と勉強できる環境のことです。以下の手順に沿って調べましょう。
① 集中できた環境を振り返る
具体的にやること
これまでの人生を振り返り、比較的集中できた勉強場所と、集中ができなかった勉強場所を思い出す
まずは、中学受験や高校受験、定期テスト直前など、これまでを振り返り、比較的集中して勉強できた場所とできなかった場所を挙げましょう。
✔︎ 塾の自習室
✔︎ 学校の自習室
✔︎ 図書館
✔︎ 公民館
✔︎ カフェ・ファミレス
✔︎ 自宅
これらのうち、集中できた勉強場所が自宅以外で、集中できなかった場所が自宅だった場合、そもそも「家では集中できない」タイプです。そのため、外の勉強環境に主軸を置き、家での勉強時間を減らすことを考える必要があります。
② 集中に差があった要素を列挙
具体的にやること
同じ場所で勉強した際に、集中できたときと集中できなかったときとで、どのような差があったのかを考える
過去の勉強場所を一つ思い出したとき、程度の差はあっても、集中できたときとできなかったときがあるはずです。その際、どのような違いがあったのかを、思いつく限り挙げてみましょう。
✔︎ スマホの有無
✔︎ 周囲の騒がしさ
✔︎ 周囲の人数の多さ
✔︎ 眠気の有無
✔︎ 空腹の有無
✔︎ 勉強内容の不明の有無
「周囲の騒がしさ」や「周囲の人数の多さ」以外の項目は、自分の行動次第で調整できます。
一方で、これらは自分では制御できないため、勉強場所そのものを変える必要があります。比較的集中しやすい環境を、自宅や学校から1時間圏内で探してみましょう。
自分に合った勉強場所へ欠かさず通うための、一連のルーティンと自分ルールを決める
ルーティンと自分ルールの例
平日はスマホを家に置いて登校し、授業が終わり次第そのまま図書館へ向かって20:30まで勉強する。帰宅後は22:30~23:30の間を「追加の勉強やわからなかった問題の調べ物をしてよい時間」とし、それ以外のおうち時間は潔く息抜きに回し、図書館でできるだけ勉強をすることでメリハリをつける。
休日は朝起きられないと1日を無駄にしてしまうため、8:00に親に起こしてもらい、朝食と身支度を済ませたらスマホを持たずにすぐに図書館へ向かい、9:30から勉強を開始できるようにする。終了時間は早めでも構わないので、毎日の勉強習慣に慣れるまでは「行く」こと自体を目標に掲げる。
高1が9月にやる勉強法と参考書
高校1年生の9月は、まず学校や部活、習い事や課題などに追われる平日の生活リズムを取り戻すことが先決です。まずは1日のルーティンを整えましょう。
平日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 宿題時間 | 0.5〜1時間 |
| 自学勉強 | 0.5〜1時間 |
| 自由勉強 | 1〜2時間 |
休日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 宿題時間 | 0.5〜1時間 |
| 自学勉強 | 1〜3時間 |
| 自由勉強 | 5〜7時間 |
・学校の宿題
・英語
・数学
まずは優先度の高い学校の宿題から取りかかり、溜め込まずに毎日解消していきましょう。できれば1日あたり1時間以内に終わらせるのが理想です。宿題が終われば、いよいよ自学の時間です。
高1が9月にやる英語の勉強法
9月にやること
・中学〜高校基礎の英単語
・中学〜高1基礎の英文法
英語に関しては、高1の9月は「英単語」と「英文法」を中心に学習しましょう。
特に、本来は夏休みまでに固めておきたかった「中学〜高1基礎」の範囲が、まだ十分に定着していない人も多いと思います。これらをある程度固めることを目標にしましょう。
❶ 授業ノートをまとめている場合
❷ 授業ノートをまとめてない場合
❶ 授業ノートをまとめている場合
勉強ステップ
1. 教科書の目次で苦手箇所を把握
2. 該当単元を教科書とノートで復習
中学時代から高校1学期までの授業ノートをきれいにまとめてストックしている場合は、学校で配布された教材とあわせて活用することで復習ができます。
ただし、すべてを一度にやろうとするとやる気をなくすため、まずは教科書の目次を確認し、自信を失った文法の単元がどこからかを把握してください。
そのうえで、教科書の該当単元と授業ノートを併用しながら地道に復習を進めることで、効果的に見直しができます。
❷ 授業ノートをまとめてない場合
授業ノートをきちんと取っていなかったり、内容が整理されておらず復習に使えない場合は、参考書を活用して復習を進めましょう。
英単語熟語帳
英単語熟語帳であるターゲット1200は、中学レベルから受験基礎レベル(偏差値50~55程度)までの英単語と熟語が載っています。基本的な単語熟語から順に載っているので、前から順に覚えていくのがよいです。
ただし、熟語が覚えづらいということであれば、まずは英単語を中心に覚え、英単語が覚えられたら熟語を中心に覚えるというやり方をとってもよいでしょう。
もしも、heやdoなどの超基本的な単語の意味がわからない場合は、ターゲット1200ではなく1800を選んだ方がよいかもしれません。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
英文法参考書
大岩の英文法は、中学から共通テストレベルまでの英文法を、英語の初学者でもわかりやすいように解説している、良質な参考書です。
一般的な教科書や参考書では、ページ内の隅に小さく載っているような補足事項は必要ない場合もあったりしますが、この参考書に載っている知識は、隅から隅まですべて受験で頻出の内容となっています。
これまで英語をサボってしまって、どこからやり直せばいいのだろうと迷っている人は、この1冊を極めることで英語を読むために必要な基礎英文法が身につきますので、丁寧に進めていきましょう。
文法の勉強方法
まずは単元の説明ページを読み進める際に、1ページごとに理解した内容を自分の言葉で要約して雑紙などに簡単にまとめる。説明途中に例文が載っている場合は、理解した後に自力で例文を英作文してみること。
単元終わりに載っているチェック問題は、最終的には自力ですべて解けるようにしてほしいが、超重要な問題しか掲載されていないので、チェック問題だけ反復して覚えても、英文法の基礎は固まらないことに注意しておく。
あくまでも、参考書全体の内容を理解して頭に入れるように、何度も反復して定着させること。
高1が9月にやる数学の勉強法
9月にやること
・数学IAの復習
・数学IAの予習
数学については、高1の9月は「数学I・Aの復習」と「数学I・Aの予習」を中心に取り組みましょう。
夏休み明けの段階ですでに遅れをとっている場合や、夏以降の授業についていけなくなるケースは、毎年少なくありません。ここで不安を解消しておくことが大切です。
❶ 授業ノートをまとめている場合
❷ 授業ノートをまとめてない場合
❶ 授業ノートをまとめている場合
勉強ステップ
1. 教科書の目次で苦手箇所を把握
2. 該当単元を教科書とノートで復習
高校1学期の授業ノートをきれいにまとめてストックしている場合は、学校で配布された教材とあわせて活用することで復習ができます。
教科書の目次を確認し、自信を失った単元がどこからかを把握してください。教科書の該当単元と授業ノートを併用しながら復習を進めることで、効果的に見直しができます。
予習は復習が十分に終わってからでかまいません。予習をする際は、まず教科書の説明を読んで大まかに理解し、例題を解いて定義や公式をぼんやりとでも頭に入れてから授業に臨みましょう。
❷ 授業ノートをまとめてない場合
授業ノートをきちんと取っていなかったり、内容が整理されておらず復習に使えない場合は、参考書を活用して復習・予習を進めましょう。
復習用①:白チャート
高校1年生の場合は、まだ受験まで時間があるため、基礎固めにしっかりと時間をかけられます。そのため、チャート式などの網羅系参考書を使って復習を進めるのがおすすめです。
特に、数学は苦手だけれど、網羅系参考書で幅広く基礎を学びたいという人には、チャート式の中でも初学者向けに構成された「白チャート」がおすすめです。
注意点としては、例題の分量が多いため、まずは例題★1〜★3を身につけ、その後で★4〜★5に取り組む、といったように段階を分けて学習すると効果的です。
復習に必要な手順
優先:例題コンパス1〜3を反復
後で:例題コンパス4〜5を反復
チャート式の単元冒頭には詳しい説明が書かれています。まずはそれを読み、単元全体を大まかに理解しましょう。理解できたら、理解した内容を不要な紙などに自分の言葉でまとめると、知識が整理されて定着が早まります。
❶のステップで説明パートを終えたら、次はいよいよ例題に移ります。例題の問題文を読み、自力で解いてみましょう。その際、20秒以内に解法の方針が立たない場合は、すぐに解答を確認してください。
公式や定義がわからない場合は、単元冒頭の説明を読み直します。解き方がわからない場合は、解説を読んで理解したら、理解した内容を含めて、その問題の解き方を誰かに教えるように、先生になりきって声に出して説明してみましょう。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元冒頭の説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元冒頭の説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元冒頭の説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元冒頭の説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
自分が習得したい問題すべてに◯が3つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。ここまでの流れが完了すれば、次の参考書へと移りましょう。
復習用②:入門問題精講
数学は苦手、白チャートのような網羅系参考書では分量が多すぎて復習する気になれないという人には、初学者向けレベルの中でも頻出度の高い問題を集めた「入門問題精講」がおすすめです。
この参考書は例題だけでなく講義形式の解説も掲載されているため、授業のように学びながら復習を進めたい人に向いています。
ただし注意点として、解説がやや紛らわしい箇所もあるため、数学が大の苦手という人は質問ができる環境で取り組むと安心です。
復習に必要な手順
優先:講義内容と練習問題を定着
後で:応用問題を中心に進める
入門問題精講は授業形式で単元の解説が丁寧に掲載されています。公式の導出や定義の意味まで詳しいので、まずは講義部分を読みましょう。理解できたら、理解した内容を不要な紙などに自分の言葉でまとめると、整理されて定着が早くなります。
入門問題精講では、読み進めていくと途中で練習問題が出てきます。練習問題に出会ったら、まずは問題文を読んで自力で解いてみましょう。その際、20秒以内に解法の方針が立たない場合は、すぐに解答を確認してください。
公式や定義がわからない場合は、単元の講義を読み直します。解き方がわからない場合は、解説を読んで理解したら、理解した内容を含めて、その問題の解き方を誰かに教えるように、先生になりきって声に出して説明してみましょう。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
講義部分は飛ばしてもよいので、練習問題を中心に解き進めます。どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元の講義を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元の講義を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
2周目と同様に、講義部分は飛ばしてもよいので、練習問題を中心に解き進めます。どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元の講義を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元の講義を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
自分が習得したい問題すべてに◯が3つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。ここまでの流れが完了すれば、次は応用問題を中心に解き進めてみましょう。
旧帝大志望の高1はこちら ▼
旧帝大や医学部レベルを志望する高校1年生は、高2の9月に取り組むべき勉強法(タップで移動可)を、高1の9月時点での目標に設定してみましょう。
さらに余裕を持って受験勉強を先に進めたい場合は、以下の記事で受験本番までに必要な参考書と勉強法をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
高2が9月にやる勉強法と参考書
高校2年生の9月は、まず学校や部活、習い事や課題などに追われる平日の生活リズムを取り戻すことが先決です。まずは1日のルーティンを整えましょう。
平日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 宿題時間 | 0.5〜1時間 |
| 自学勉強 | 1〜2時間 |
| 自由勉強 | 1〜1.5時間 |
休日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 宿題時間 | 0.5〜1時間 |
| 自学勉強 | 2〜5時間 |
| 自由勉強 | 4〜6時間 |
・学校の宿題
・英語
・数学
・理科
まずは優先度の高い学校の宿題から取りかかり、溜め込まずに毎日解消していきましょう。できれば1日あたり1時間以内に終わらせるのが理想です。宿題が終われば、いよいよ自学の時間です。
高2が9月にやる英語の勉強法
9月にやること
・高校〜受験基礎の英単語
・高校〜受験基礎の英文法
・高校〜受験基礎の英文解釈
・高校〜受験基礎の長文読解
英語に関しては、高2の9月は「英単語」「英文法」「英文解釈」「長文読解」を中心に学習しましょう。
特に、本来は夏休みまでに固めておきたかった「高校〜受験基礎」の範囲が、まだ十分に定着していない人も多いと思います。これらをある程度固めることを目標にしましょう。
❶ 授業ノートをまとめている場合
❷ 授業ノートをまとめてない場合
❶ 授業ノートをまとめている場合
勉強ステップ
1. 教科書の目次で苦手箇所を把握
2. 該当単元を教科書とノートで復習
高校1年〜高校2年1学期までの授業ノートをきれいにまとめてストックしている場合は、学校で配布された教材とあわせて活用することで復習ができます。
ただし、すべてを一度にやろうとするとやる気をなくすため、まずは教科書の目次を確認し、自信を失った文法の単元がどこからかを把握してください。
そのうえで、教科書の該当単元と授業ノートを併用しながら地道に復習を進めることで、効果的に見直しができます。
❷ 授業ノートをまとめてない場合
授業ノートをきちんと取っていなかったり、内容が整理されておらず復習に使えない場合は、参考書を活用して復習を進めましょう。
英単語帳
ターゲット1900は、受験基礎から早慶・旧帝大レベルまでの英単語を掲載している英単語帳です。ターゲット1200を使用していた人は、1400を挟まずにそのまま1900へとつなぐことができます。
また、時間があれば1〜1900まで覚えた方がよいですが、中堅以下の大学を志望する場合は、1500までをしっかり定着させるのでも十分でしょう。
ターゲット1900の進め方ですが、①まずは見出し単語をひと通り覚える ②覚えられたら次に派生語も覚える ③全体的に覚えたら右ページの例文を用いて定着させる、というように段階を踏んで学習すると挫折しづらいです。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
英文法参考書
高校2年の9月になると、英文法の基礎はある程度身についているはずです。その定着度を確認するために、文法の実践問題に取り組んでみましょう。
おすすめは英文法ポラリスシリーズです。問題数がそれほど多くないため、時間が限られていても知識の確認がしやすく、効率的に演習できます。特にポラリス1は読解に必要な内容が中心なので、ぜひ取り組んでみてください。
ただし、難関私大を志望する場合は文法問題の出題が多いため、Vintageのような網羅系参考書を使って対策しておくと安心です。
文法の勉強方法
まずは自力で問題を解き進め、根拠も含めて正解できた問題と、間違えたあるいは根拠が曖昧だった問題を振り分けること。2周目以降は、1周目に根拠を含めて正解できた問題以外を集中的に反復していく。
ただ丸暗記をしても、文章の中で使えない知識となってしまうので、正解の根拠を説明できるようにすることが大切。
英語苦手向けの英文解釈
英語が苦手な人向けに、難しい英単語は使わないように構成された、英文解釈の参考書です。英単語と英文法の基本が身についた段階で取り組むと、詰まることなく学習を進めることができます。
ただし、苦手というよりも、まだ英語の学習をほとんどしていない段階であれば、まずは高校1年生の9月の勉強法(タップで移動可能)で紹介した英語の内容からやり直すことをおすすめします。
英語一般向けの英文解釈
入門と書かれていますが、英単語や英文法の基礎、英文解釈の基本ができていないと厳しい、一般的なレベルの高2向け英文解釈参考書です。
後半になるにつれて難易度が上がり、説明や表現もやや堅めではありますが、英文解釈の基礎を固めるには非常に適した王道の参考書です。
英文解釈の勉強方法
まずは自力でSVを振りながら英文の構造を把握し、日本語訳を紙に書きましょう。このときに、変な日本語になってもよいので、英文法のルールに従って正しく正確に直訳するようにしてください。
直訳ができたらそこで初めて、直訳の日本語をもとに、意味が変わってしまわないように自然な日本語に書き換えましょう。ここまでができたら、解答解説の確認をします。
最後は、例文をシャドーイングしながら(付属の音声を使う)、返り読みをせずに前から順に(左から右に)訳します。これを数回ほど繰り返して前から順に意味をとれだしたら、次の例文へと移ります。
英語苦手向けの長文読解
英語が苦手な場合は、まず長文レベル別問題集の3から長文読解の練習を始めましょう。中学レベルの英単語と英文法の基礎が身についていれば進められます。
ただし、苦手というよりも、まだ英語の学習をほとんどしていない段階であれば、まずは高校1年生の9月の勉強法(タップで移動可能)で紹介した英語の内容からやり直すことをおすすめします。
英語一般向けの長文読解
この参考書は、長文問題の読み進め方を丁寧に解説した、英文解釈と長文読解を兼ね備えた一冊です。長文読解を通して、英文を読む練習を積み重ねましょう。
解くだけでなく、全文訳とシャドーイングも欠かさず行なう(タップで確認)ようにすると、非常に効果的です。ただし、英文の分量が意外と多いため、音読が体力的にきつい場合は、パラグラフごとに区切ってシャドーイングしても構いません。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
高2が9月にやる数学の勉強法
9月にやること
・数学IAの復習
・数学IIBの復習
・数学IIBの予習
数学については、高2の9月は「数学I・Aの復習」「数学II・Bの復習」「数学II・Bの予習」を中心に取り組みましょう。
夏休み明けの段階ですでに遅れをとっている場合や、夏以降の授業についていけなくなるケースは、毎年少なくありません。ここで不安を解消しておくことが大切です。
❶ 授業ノートをまとめている場合
❷ 授業ノートをまとめてない場合
❶ 授業ノートをまとめている場合
勉強ステップ
1. 教科書の目次で苦手箇所を把握
2. 該当単元を教科書とノートで復習
高校1年〜高校2年1学期までの授業ノートをきれいにまとめてストックしている場合は、学校で配布された教材とあわせて活用することで復習ができます。
教科書の目次を確認し、自信を失った単元がどこからかを把握してください。教科書の該当単元と授業ノートを併用しながら復習を進めることで、効果的に見直しができます。
予習は復習が十分に終わってからでかまいません。予習をする際は、まず教科書の説明を読んで大まかに理解し、例題を解いて定義や公式をぼんやりとでも頭に入れてから授業に臨みましょう。
❷ 授業ノートをまとめてない場合
授業ノートをきちんと取っていなかったり、内容が整理されておらず復習に使えない場合は、参考書を活用して復習・予習を進めましょう。
復習用①:青チャート
青チャート(黄色チャート・Focus Gold・LEGENDでも可)は、章末問題や★4〜★5を除けば難易度はそれほど高くなく、解説も丁寧に書かれている網羅系参考書です。そのため、時間を集中して一気に復習するにはおすすめの一冊です。
ただし、例題の分量が多いため、まずは基礎〜標準レベルである例題★1〜★3を身につけ、その後で応用レベルの例題★4〜★5に取り組む、といったように段階を分けて学習すると効果的です。
復習に必要な手順
優先:例題コンパス1〜3を反復
後で:例題コンパス4〜5を反復
チャート式の単元冒頭には詳しい説明が書かれています。まずはそれを読み、単元全体を大まかに理解しましょう。理解できたら、理解した内容を不要な紙などに自分の言葉でまとめると、知識が整理されて定着が早まります。
❶のステップで説明パートを終えたら、次はいよいよ例題に移ります。例題の問題文を読み、自力で解いてみましょう。その際、20秒以内に解法の方針が立たない場合は、すぐに解答を確認してください。
公式や定義がわからない場合は、単元冒頭の説明を読み直します。解き方がわからない場合は、解説を読んで理解したら、理解した内容を含めて、その問題の解き方を誰かに教えるように、先生になりきって声に出して説明してみましょう。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元冒頭の説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元冒頭の説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元冒頭の説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元冒頭の説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
自分が習得したい問題すべてに◯が3つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。ここまでの流れが完了すれば、次の参考書へと移りましょう。
復習用②:基礎問題精講
網羅系参考書では分量が多すぎて復習する気になれないという人には、頻出度の高い問題を集めた「基礎問題精講」がおすすめです。
解説は入門問題精講ほど丁寧ではありませんが、共通テストや中堅大学レベルまでを効率よく狙うには適した一冊です。
ただし、この参考書はどちらかといえば時間がない人向けの教材なので、十分に時間がある場合はチャート式などの網羅系参考書に取り組むほうがよいでしょう。
復習に必要な手順
優先:講義内容と基礎問を定着
後で:演習問題を中心に固める
まずは基礎問の問題文を読んで自力で解いてみましょう。その際、20秒以内に解法の方針が立たない場合は、精講に目を通して、再度考えてみます。それでもわからない場合は、すぐに解答を確認してください。
公式や定義がわからない場合は、学校の教科書などでそれらを確認し直します。解き方がわからない場合は、解説を読んで理解したら、理解した内容を含めて、その問題の解き方を誰かに教えるように、先生になりきって声に出して説明してみましょう。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
基礎問を中心に自力で解き進めます。どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、精講を読んで再度考え、それでもわからない場合はすぐに解答を見ましょう。
精講のヒントなしに自力で解法を思い出し、過程を含めて最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、教科書でそれらを確認し直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
❸の過程が完了したら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し解いてください。その問題を最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
2周目と同様に、基礎問を中心に解き進めます。どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、精講を読んで再度考え、それでもわからない場合はすぐに解答を見ましょう。
精講のヒントなしに自力で解法を思い出し、過程を含めて最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、教科書でそれらを確認し直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
❸の過程が完了したら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し解いてください。その問題を最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
自分が習得したい問題すべてに◯が3つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。ここまでの流れが完了すれば、次は演習問題を中心に解き進めてみましょう。
高2が9月にやる理科の勉強法
9月にやること
・基本事項の理解と全体像の把握
高校2年生の9月は、英語と数学が最優先であることに変わりはありませんが、理科の苦手も克服する必要があります。
苦手意識がある場合は、まず必要科目の全体像と基本的な公式・定義を頭に入れ、ざっくりと構造を掴んでおきましょう。
いきなり問題演習から入ると挫折しやすいため、講義系の初学者向けでわかりやすい参考書からコツコツと進めていきましょう。
上記で紹介した参考書のシリーズは、そのとっかかりとしておすすめの講義系参考書になります。
旧帝大志望の高2はこちら ▼
旧帝大や医学部レベルを志望する高校2年生は、高3の9月に取り組むべき勉強法(タップで移動可)を、高2の9月時点での目標に設定してみましょう。
さらに余裕を持って受験勉強を先に進めたい場合は、以下の記事で受験本番までに必要な参考書と勉強法をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
高3・浪人の9月の勉強法と参考書
高校3年生と浪人生の9月は、本番まで残りおよそ4か月しかないため、後悔のないよう、これまで以上に勉強に力を注がなければなりません。
平日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 自学勉強 | 3〜5時間 |
| 自由勉強 | 0〜1時間 |
休日のルーティン
| 睡眠時間 | 6〜7時間 |
| 自学勉強 | 5〜10時間 |
| 自由勉強 | 0〜1時間 |
・英語
・数学
・理科
・古文
この時期は、成績優秀な人を除き、学校の宿題よりも志望大学合格のための自学に優先的に時間を割く必要があります。
高3・浪人が9月にやる英語の勉強法
9月にやること
・受験レベルの英単語
・必要な英文解釈の完全定着
・志望大学レベルの長文読解
・二次で必要な場合は英作文
・志望大学の英語過去問1年
英語に関しては、高3・浪人の9月は「英単語」「長文読解」「英文解釈」「英作文(必要な場合のみ)」「志望大学の過去問」を中心に学習しましょう。
英単語帳
高3・浪人の場合は、この時期には主要な英単語帳(ターゲット1900やシス単など)を少なくとも8割以上は完成させておきたい
受験基礎から早慶・旧帝大レベルまでの英単語を掲載している英単語帳です。1〜1900まで覚えた方がよいですが、中堅以下の大学を志望する場合は、1500まででも十分でしょう。
進め方ですが、①まずは見出し単語を1秒以内に答えられるよう完璧にする ②派生語も覚える ③右ページの例文を定着させる、というように段階を踏んで優先的に固めましょう。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
英文解釈の参考書
高3・浪人の場合は、どれだけ遅くとも9月が終わるまでには英文解釈の参考書を完成させておくこと
基礎英文解釈の技術100は、入門英文解釈の次に取り組む標準レベルの参考書です。志望大学の目安としては、千葉大学や筑波大学などの準難関大学までを想定しています。
本来であれば英文解釈は8月までに仕上げておくべきですが、学習が遅れている受験生も少なくありません。遅れている場合でも、9月までには必ず英文解釈を完成させておきましょう。
英文解釈の勉強方法
まずは自力でSVを振りながら英文の構造を把握し、日本語訳を紙に書きましょう。このときに、変な日本語になってもよいので、英文法のルールに従って正しく正確に直訳するようにしてください。
直訳ができたらそこで初めて、直訳の日本語をもとに、意味が変わってしまわないように自然な日本語に書き換えましょう。ここまでができたら、解答解説の確認をします。
最後は、例文をシャドーイングしながら(付属の音声を使う)、返り読みをせずに前から順に(左から右に)訳します。これを数回ほど繰り返して前から順に意味をとれだしたら、次の例文へと移ります。
長文読解の参考書
この参考書は、標準的な英語レベルの国公立(準難関大含む)やMARCHレベルを目指す受験生に対応した長文読解用の参考書です。
解答や構文解説が丁寧で、シャドーイング用音声も用意されているため、しっかりと活用すれば、旧帝大や難関私立を目指す場合を除いて十分対応できるでしょう。
重要なのは、ただ解くだけでなく、全文訳とシャドーイングも欠かさず行ない(タップで確認)、この参考書を使いこなすことです。
英作文の参考書
二次試験で英作文が必要となる場合は、9月中に一般的な英文の型をある程度定着させ、標準的な英作文であれば書けるようにしておくこと
ハイパートレーニングシリーズは、解説が丁寧でわかりやすいのが特徴です。分量的にも取り組みやすく、インプット用の例文も掲載されているので、残された期間で英作文の土台を叩き上げるのにもってこいです。
和文英訳編はしっかりと身につけられたら、ほとんどの大学で通用します。反復を重ね、9月のうちに英文の型がある程度身についている状態にしておきましょう。
自由英作文は、最初は書かなければならない英文の量に圧倒するかもしれません。ですので、書き上げるまでに必要な要素を分けて、段階的に書き上げていきましょう。
手順としては、まず日本語で回答をつくり、その日本語を自分が英語を書きやすいように言い換え、それから英訳するというようにステップを踏むと、取り組みやすくなります。
英作文の勉強方法
まずは自力で英作文をして紙に自分の回答を書き、終えたらペンの色を変えて、単語熟語帳や辞書などを用いて、書けなかった箇所を書き足していく。ここまでが終わったら、模範解答と解説を確認し、書き方を理解して学んだら、再び自力で解答を再現してみる。
これをできるまで繰り返し、再現ができるようになったら、次の例文に移る。英作文は理解で終わるだけでなく、使えるようにならないと意味がないため、移動時間などの暇な時間で例文集を反復するとベスト。
自由英作文の勉強方法
いきなり英文を書き始めずに、まずは日本語で「主張 → 理由 → 具体例 → 結論」の論理構成で自分の回答を作ってみる。その日本語をもとに、自分が英語を書きやすいように、日本語を言い換えてみる。
言い換えが完了したら、ここでようやく英語へと書き換えて、自由英作文を完成させる。英文が完成したら、模範解答と解説を確認し、自分の論理主張と何が違うか、どのような英語表現の使われ方がしているかを丁寧に分析する。
最後に再び、自力で英作文を行ない、次の問題へと移る。この流れにある程度慣れてきたら、日本語で回答を作る過程をなくしていき、いきなり英文で書けるように練習していくとよい。
志望大学の過去問
二次試験本番レベルと現時点の英語力との間で、どこに乖離が生じているのかを特定し、残りの期間で集中的に対策できるようにすること
できれば9月のうちに、志望大学の英語の過去問を1年分解いてみましょう。
現段階でどの程度得点できるのかを確認し、足りない力が単語熟語の知識なのか、英文解釈力なのか、あるいは速読力なのかを特定できるようにするとよいです。
高3・浪人が9月にやる数学の勉強法
9月にやること
・数学IAIIBIIICの総仕上げ
・数学IAIIBIIICの応用演習
・志望大学の数学過去問1年
数学については、高3・浪人の9月は「数学I・A・II・B・III・Cの総仕上げ・応用演習」を中心に取り組みましょう。
総仕上げ用の参考書
9月は数学IAIIBIIICの基礎〜標準レベルを仕上げて定着させ、その後は過去問演習に進む
中堅国公立・私立志望なら、青チャート(黄色チャート・Focus Gold・LEGENDでも可)などの網羅系参考書で、例題★1〜★3を完璧に、★4は7割定着を目標に9月で仕上げましょう。
練習問題もできれば解いておきたいですが、これまでに学校の傍用問題集をしっかりこなしていれば省略してもかまいません。
基礎問題精講を使っている場合は、問題数がやや少ないため、学校の傍用問題集の応用問題以外を確実に解けるように演習しておいた方が無難です。
総仕上げの勉強法
これまでの演習で解けなかった問題や理解が曖昧な問題には、マークを付けているはずなので、9月はそれらを中心に解き直しましょう。5分考えても解法の方針が立たない場合は、新たに目立つ付箋を貼ってから解答を確認してください。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
9月のうちに定着しなかった問題には、目立つ付箋が貼られたまま残ることになります。そうした問題は、今後も定期的に振り返るようにするとよいでしょう。
応用演習用の参考書
9月は数学IAIIBIIICの基礎〜標準レベルを仕上げて定着させ、その後は応用問題の演習と過去問演習を並行して進める
筑波大や横国など準難関大志望の場合は、チャートなどの網羅系参考書に加えて、1対1対応、あるいは理系数学入試の核心(標準)のような応用演習用の参考書にも取り組んでおくと安心です。
1対1対応は冊数と問題総量が多いので、時間がない場合は入試の核心がおすすめです。
応用演習の勉強法
応用演習では、これまでの“解法インプット型”の勉強法とは少し異なり、1問あたりの思考時間を多めに確保します。解くべき問題で解法がすぐに思い浮かばなくても、さまざまな切り口から自分なりに方針を立ててください。
ほんの少しでも方針が見えたら、実際に手を動かして解き進めます。途中でその方針が誤りだと分かったら、別の方針に切り替えて再挑戦し、“お手上げ”になるまで粘りましょう。
どうしても解けない場合は、解答を確認して理解したうえで、解説を隠しながら自力で解けるまで何度も解き直します。問題の最初から最後まで自力で通せたら、そこで初めて次の問題へ進むようにしましょう。
志望大学の過去問
二次試験本番レベルと現時点の数学力との間で、どこに乖離が生じているのかを特定し、残りの期間で集中的に対策できるようにすること
できれば9月のうちに、志望大学の数学の過去問を1年分解いてみましょう。
現段階でどの程度得点できるのかを確認し、足りない力が解法の知識なのか、発想力なのか、あるいは計算力なのかを特定できるようにするとよいです。
高3・浪人が9月にやる理科の勉強法
9月にやること
・網羅系の基礎を総仕上げ
・網羅系の応用を反復演習
・志望大学の理科過去問1年
理科については、高3・浪人の9月は「基礎の総仕上げ・応用演習」を中心に取り組みましょう。
総仕上げ用の参考書
9月は理科の基礎レベルを仕上げて定着させ、その後は過去問演習に進む
基礎レベルを確実に定着させる最終仕上げとして、「基礎問題精講」や「セミナー・リードα・センサー」シリーズの応用を除く基礎問題に取り組みます。
とくにセミナーやリードα、センサーは学校の傍用問題集として使われることが多いため、基礎問題精講レベルの参考書+いずれか1つの計2冊をやっておくと安心です。
総仕上げの勉強法
これまでの演習で解けなかった問題や理解が曖昧な問題には、マークを付けているはずなので、9月はそれらを中心に解き直しましょう。5分考えても解法の方針が立たない場合は、新たに目立つ付箋を貼ってから解答を確認してください。
その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
9月のうちに定着しなかった問題には、目立つ付箋が貼られたまま残ることになります。そうした問題は、今後も定期的に振り返るようにするとよいでしょう。
応用演習用の参考書
9月は理科の基礎レベルを仕上げて定着させ、その後は応用問題の演習と過去問演習を並行して進める
筑波大や横国など準難関大志望の場合は、基礎問題精講などの基礎参考書に加えて、重要問題集など応用まで扱う参考書で演習を進めましょう。
準難関大学を志望する場合は、A問題のすべてと、B問題の必・準のうち8割以上を解ける状態にしておくようにしましょう。
志望大学の過去問
二次試験本番レベルと現時点の実力との間で、どこに乖離が生じているのかを特定し、残りの期間で集中的に対策できるようにすること
できれば9月のうちに、志望大学の理科の過去問を1年分解いてみましょう。
現段階でどの程度得点できるのかを確認し、足りない力が解法の知識なのか、発想力なのか、あるいは問題文の理解力なのかを特定できるようにするとよいです。
高3・浪人が9月にやる古文の勉強法
9月にやること
・文法(特に助動詞・敬語)を学ぶ
・単語帳の単語を大まかに覚える
古文単語の勉強法
古文単語315は、古文単語とその意味を載せているだけでなく、イメージしやすい絵と、その言葉になった語源も一緒に載せてくれています。
絵を見ながらイメージをわかせつつ、なぜその古文単語ができあがったかの理由と背景を読んで理解すれば、知識が長期的に定着しやすくなるので、非常におすすめの単語帳です。
ただし、すべてを学習すると分量が非常に多いので、まずは赤字の見出しのみ覚えるようにしましょう。9月はそれほど時間をかける必要はないので、隙間時間などを利用して覚えていくとよいです。
単語の覚え方
まずは古文単語とその意味(赤字)を声に出して反復しながら覚える。このやり方で見開き1ページ分を覚えたら、次のページへ移動して同様の作業を行なう。
その日の分量が終わったら、最後にその日覚えた古文単語を覚えているか通しで復習する。覚えていない単語があった場合は、その日の分量の最初からやり直して、通しでクリアするまで繰り返す。
その日の分量をクリアできたら、寝る前、あるいは次の日の朝に復習をする。
全体的にある程度覚えられたら、次は単語単体ではなく例文を使って覚えているか確認をするとベスト。
古典文法の勉強法
富井の古典文法は、これまで学校の古典の授業をまともに受けていなかった人でも取り組めるような、話し言葉で書かれた非常にわかりやすい文法参考書です。古典文法の全体像を把握でき、共通テストで必要とされる文法は網羅されています。
ただし、問題演習が少ないため、知識のインプットとしては申し分ありませんが、これとは別にアウトプット用の参考書もしておくとベストです。
古典文法に関しても、英語と数学と理科が優先なので、1日のうち残った時間で少しずつ進めていきましょう。
文法の学習手順
まず1周目は章の中に含まれている講を読み進めていき、書かれている内容を理解する。内容が理解できたら、参考書にそのまま書き込んでよいので、理解したことを自分の言葉でメモする。
1つの講が終わったら練習問題を解き、正答率が悪い場合は(目安は50%以下)、再びその講の説明を読み返して、理解し直してからもう一度解き直すこと。
2周目以降は、別冊を使って反復し、わからないところだけ本冊の内容を確認するとベスト。
旧帝大志望の高3・浪人はこちら ▼
旧帝大や医学部レベルを志望する高校3年生・浪人生は、以下の記事で受験本番までに必要な参考書と勉強法をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。