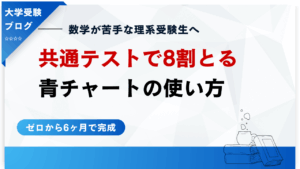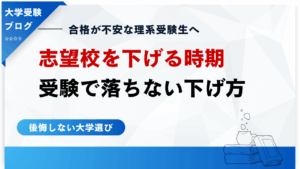【こんな受験生は危険】落ちないための滑り止め大学の選び方4選
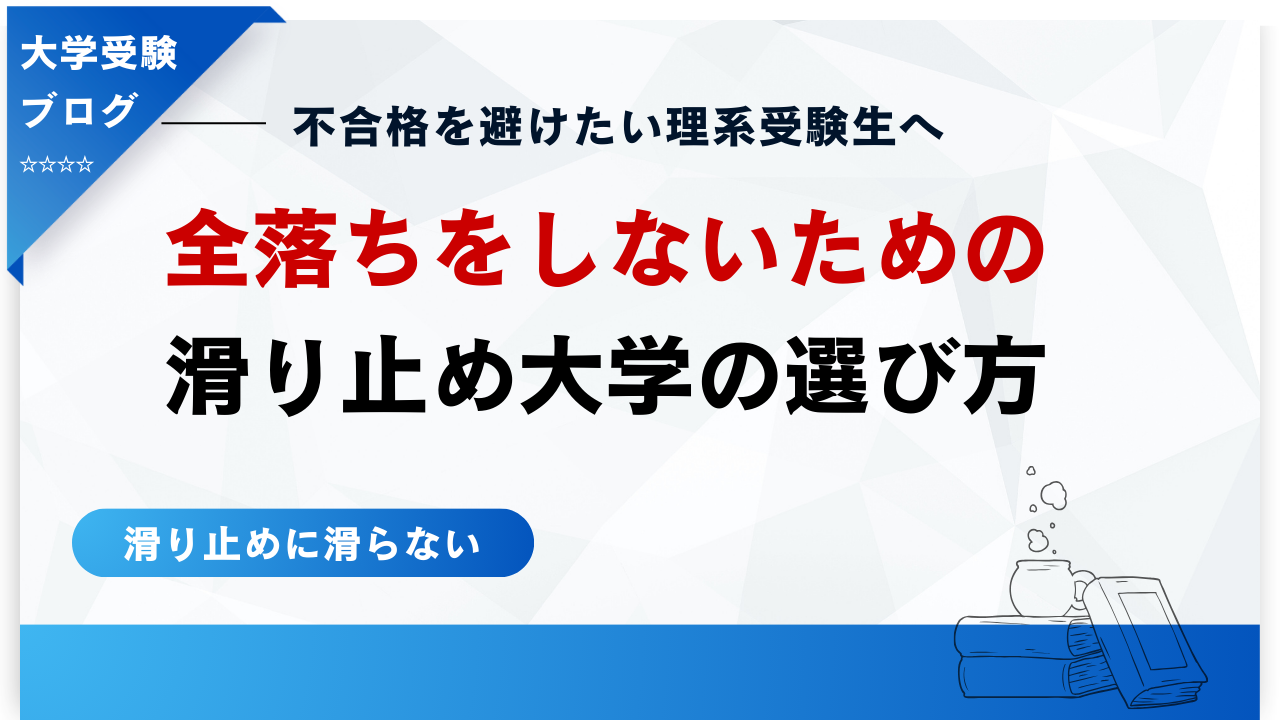
全落ちだけは避けたいけれど、滑り止めが低すぎるのも嫌だ…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

滑り止めの大学って、どのレベルまで下げないといけないのかな…

滑り止めの大学にも滑ったってよく聞くから、自分もなりそうで怖い…
実際に、筆者の運営するYouTubeには毎年のように「滑り止めの大学にすら落ちてしまった」という受験生からの後悔の声が届きます。
かくいう筆者自身も、現役時代に大学全落ちを経験しました。
よりによって、自分が全落ちするなんてありえないだろう
その「まさか」があっけなく自分の身に降りかかるのが大学受験です。そしてこれは、毎年のように繰り返される悲劇でもあります。
✔︎ 滑り止め大学に落ちる受験生の特徴
✔︎ 滑り止めに落ちた実体験と反省点
✔︎ 後悔しない滑り止め大学の選び方
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
滑り止め大学にも落ちる受験生
ここでは、実際に滑り止めの大学にも落ちてしまった受験生の声をいくつか紹介します。
全落ちを経験した受験生の声
Aさんの場合
12校目の不合格が決まりました。模試の偏差値は60ちょっとで、受けた大学はすべてA判定でした。それなのに、偏差値45の大学にも落ちました。 大学がこんなに難しいなんて知りませんでした。
Bさんの場合
大学に全落ちしました。まさか自分がこんなことになるなんて思ってもみませんでした。滑り止めにさえも滑り止まらず、そもそも滑り止めにする大学を失敗しました。模試でずっとA判定だったからって滑り止めにするべきじゃなかったです。
Cさんの場合
大学受験に全落ちしました。早慶志望でMARCH1つしか受けてないのですが、そのMARCHすら落ちて受験終わってからベッドから起き上がれません。
大学受験では、その「まさか」が自分の身に起こり得ます。しかし、それは実際に経験してみないとなかなか実感できないものです。
全落ちしてしまえば、もはや浪人するか受験を諦めるかしか選択肢はありません。もし心に油断があるなら、このことを少しでも胸に留めておいてください。
滑り止めに落ちる受験生の特徴
滑り止めの大学にまで落ちてしまう受験生には、氏名の書き忘れといった不運な致命的ミスを除けば、一定の共通した特徴があります。
✔︎ 滑り止め大学を過小評価している
✔︎ 滑り止め大学のレベルが高すぎる
✔︎ 自分が落ちるわけないと思っている
滑り止め大学を過小評価している
危険なケース
甘く見て過去問を確認しないまま本番を迎えて、出題のクセや形式への不慣れで想定以上に失点してしまうケース
滑り止めの大学に対して、実力が大きく上回っているならまだしも、多少上回っている程度で「対策なしでも受かるだろう」と思い込み、過去問を確認せずに本番を迎えるのは危険です。
たとえば、英語なら和訳問題や英作文の有無、数学なら証明問題の出題頻度など、出題形式によって求められる力は大きく変わります。時間配分を誤り、解き切れずに失点してしまうこともあります。
偏差値帯が少し下がった大学でも、出題のクセが強かったり合格最低点が意外と高いケースは少なくありません。基礎を正確に固め、簡単にでもよいので過去問で傾向を確認しておきましょう。
滑り止め大学のレベルが高すぎる
該当するケース
選んだ滑り止めの大学が、自分の実力と同等、あるいはそれ以上のレベルであったため、失敗リスクが高まるケース
これは、油断や手抜きをしているわけではなく、そもそも選んだ滑り止めの大学が自分の実力に対して同等、あるいはそれ以上のレベルだったというケースです。
たとえば、第一志望がMARCHレベルの受験生が「滑り止め」として同じMARCHや日東駒専の上位学部を出願する場合がこれに当たります。
結果的に、滑り止めどころか、現在の実力からすれば第一志望と同じく挑戦校になってしまっているのです。
自分が落ちるわけないと思っている
該当するケース
自分の実力が上だと過信し、ケアレスミスや基礎問題の取りこぼしで失点が重なり、合格ボーダーに届かないケース
この大学はレベルが低いから大丈夫だろうと軽視し、学力が十分に固まっていないのに、自分は実力が上だと勘違いしてしまうケースです。
滑り止めは偏差値的に高くない大学かもしれませんが、実際には緊張や形式の違いで得点が伸びにくいのが現実です。
基礎が固まりきっていないのに「自分はできる」と思い込むと、本番でケアレスミスや基礎問題での取りこぼしが重なり、合格最低点に届かず不合格になることもあります。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
滑り止めの大学に落ちた実体験
冒頭でお伝えしたとおり、筆者は現役時にすべての大学に不合格となりました。ここでは、そのときの状況をお話しします。
| 入試 | 大学名 |
|---|---|
| 前期試験 | 東京科学大学 |
| 後期試験 | 東京農工大学 |
| 滑り止め | 東京理科大学 |
正直なところ、現役時の筆者は大学受験を甘く見ていました。
東京科学大学を受ける人にとって理科大は滑り止めだし、自分も受かるだろう
そう過信していたのです。ところが、実際に受験してみると現実は想像以上に厳しく、試験内容は想像の何倍も難しくてまったく歯が立ちませんでした。
東京科学大学の入試対策をしているのだから、理科大なら楽勝だろう
このように高をくくっていたのですが、結局ほとんど解けず、不合格という結果になりました。さらに、最後の砦だった後期試験の農工大にも落ち、全落ちが確定します。
頭では過信がダメなことだと理解していたつもりでも、無意識のうちに他の大学を見下していたのです。
おそらく、先ほど紹介したA〜Cさんも「まさか自分が滑り止めに落ちるなんて」と思っていたことでしょう。
しかし、その“まさか”が起こるのが大学受験であり、自分の実力不足を突きつけられるのも大学受験です。
ぜひ筆者の失敗を反面教師にして、全落ちという結果を避けられるようにしましょう。
滑り止め大学の選び方3選
滑り止め大学は、その名のとおり「落ちるのを防ぐ最後の砦」です。挑戦しながらも必ず合格を確保できるように設定する必要があります。
共通テスト利用の大学がある場合
ポイント
共通テスト利用で確実に合格できる大学を、滑り止め大学として1校選ぶ
共通テスト利用は大学ごとに必要科目が異なるため、自分の得意科目だけを組み合わせて出願できる場合もあります。
そのため、共通テスト利用が使える場合は、比較的強気に大学レベルを上げやすいのが特徴です。
また、自己採点のミスがなければ合格可能性をある程度見通せるため、共通テスト利用で押さえられる大学があると安心感が大きくなります。
ただし、ミスなどの不安がある場合は、実際に受験しに行く大学を1校追加で確保しておくとよいでしょう。
共通テスト利用の大学がない場合
共通テスト利用を使わない場合、その大学の記述入試を受ける必要があります。
共通テスト利用での合格に比べ、記述試験での合格は難易度が高くなることが多いため、慎重に選ぶことが重要です。
以下の表では、第一志望大学の模試判定結果を参考にした、滑り止め大学選びの目安を示しています。
| A判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス4~5の私立大学を選ぶ |
| B判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス5~7の私立大学を選ぶ |
| C判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス7~10の私立大学を選ぶ |
| D判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス10~12の私立大学を選ぶ |
| E判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス12~15の私立大学を選ぶ |
あくまで目安ですので、最終的には自分の受けたい気持ちや、直近の過去問演習での得点を基準に判断してください。
できるだけギリギリまでレベルを上げたい気持ちは分かりますが、滑り止めは「確実に合格すること」が最優先です。謙虚な姿勢で選ぶようにしましょう。
後期を滑り止め大学にする場合①
ここでは、共通テストの配分が低い大学を滑り止めとして設定する場合について、第一志望大学の模試判定結果を参考に目安を紹介します。
| A判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス5~7の国公立大学を選ぶ |
| B判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス7~9の国公立大学を選ぶ |
| C判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス9~10の国公立大学を選ぶ |
| D判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス10~11の国公立大学を選ぶ |
| E判定 | 第一志望大学の偏差値マイナス11~14の国公立大学を選ぶ |
後期試験で国公立大学を滑り止めとして選ぶ場合は、前期落ちの優秀な受験生が上から流れ込んでくるため、少し低めに設定しておくと無難です。
後期を滑り止め大学にする場合②
ここでは、共通テストの配分が高い大学を滑り止めとして設定する場合について、目安を紹介します。
ポイント
共通テスト得点がA判定の大学を滑り止め大学として選ぶこと
共通テストの配分が高い場合は、周いにも優秀な受験生が集まるため、共通テストでの失点を二次試験で逆転するのは難しくなります。
その結果、共通テスト得点がB寄りのA判定であっても不合格になることがあります。
そのため、後期の国公立大学を滑り止めとして設定する場合は、共通テストでA判定をとれていなければ安心できないと考えておきましょう。
滑り止め大学を受ける注意点
滑り止めや併願校を複数受験する予定の受験生も少なくないでしょう。ただし、受ける数を誤るとかえって自分の首を絞める危険性があるため、以下の点に注意してください。
✔︎ 会場に受けに行く滑り止めは2~3校
✔︎ 県外で受験する大学は数を絞る
直接受験しなければならない滑り止めや併願校が多いと、想像以上に勉強時間が奪われます。
特に、県外への移動が必要な場合や試験時間が長い大学では、各大学の対策時間が減るだけでなく、本命である第一志望大学の対策にも悪影響を及ぼします。
会場受験が必要な場合は、受験校の数を絞っておくのがおすすめです。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。