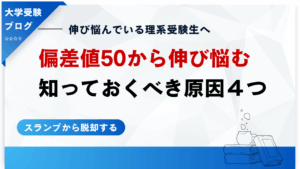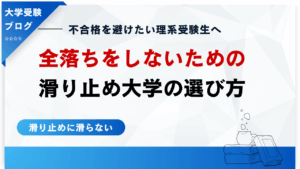【ゼロから6ヶ月】青チャートだけで共通テスト8割をとる使い方【理系】
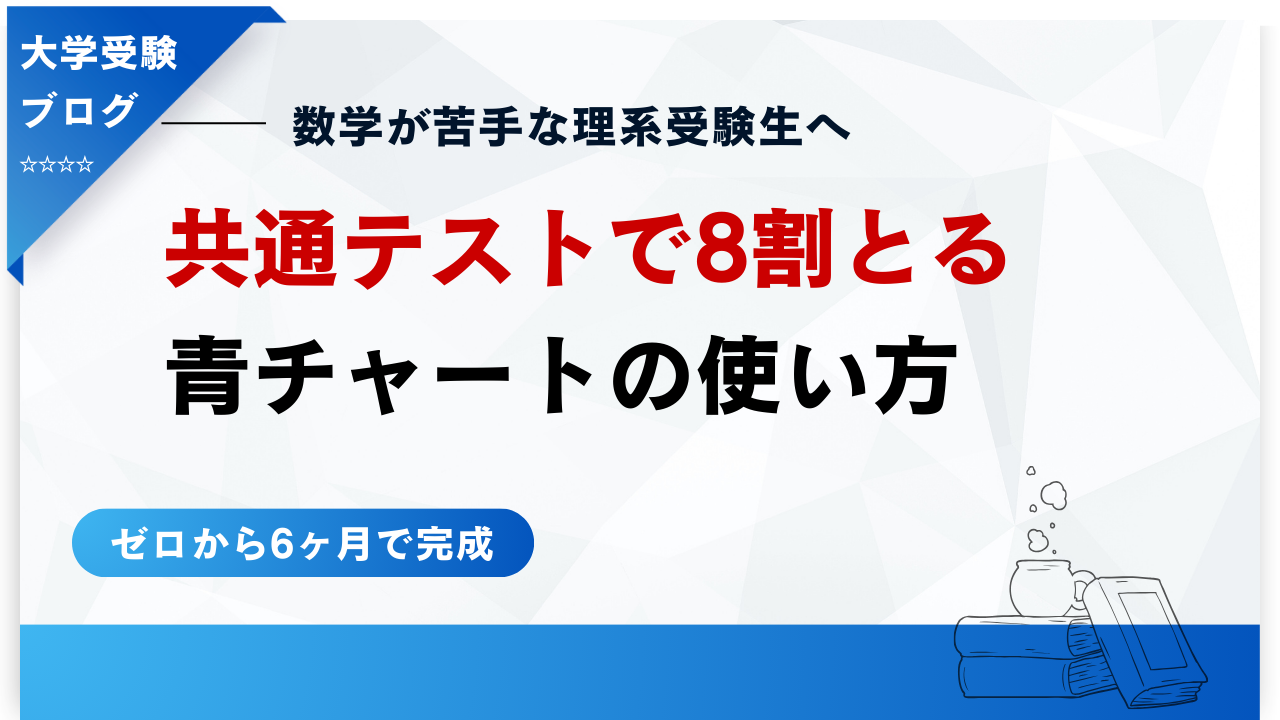
これから数学の勉強を始めて、共通テストまでに間に合うかな…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

数学の対策が遅くなってしまったけど、今からでも8割狙いたい…

数学はあまり得意じゃないけど、共通テスト数学で8割とらないと…
共通テスト数学で得点しなければならないのに、このままでは達成できそうにないと感じている人も少なくないのではないでしょうか。
学校や自学でも広く使われる「青チャート」は、内容がボリューム豊富なため、使い方を誤ると膨大な時間を費やしてしまいます。
青チャートをどのように使えば、効率よく数学力を身につけられるだろうか
今回は、数学の学習に「青チャート」を使っている理系に向けて、ゼロから共通テスト数学で8割を目指すための勉強法を紹介します。
✔︎ 青チャートの学習にかかる時間
✔︎ 青チャートの具体的な勉強法
✔︎ 共通テスト数学8割を狙う計画
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
青チャートの学習にかかる時間

共通テスト数学で8割を目指すために、青チャートで取り組みべき学習範囲とかかる学習時間の目安を確認していきましょう。
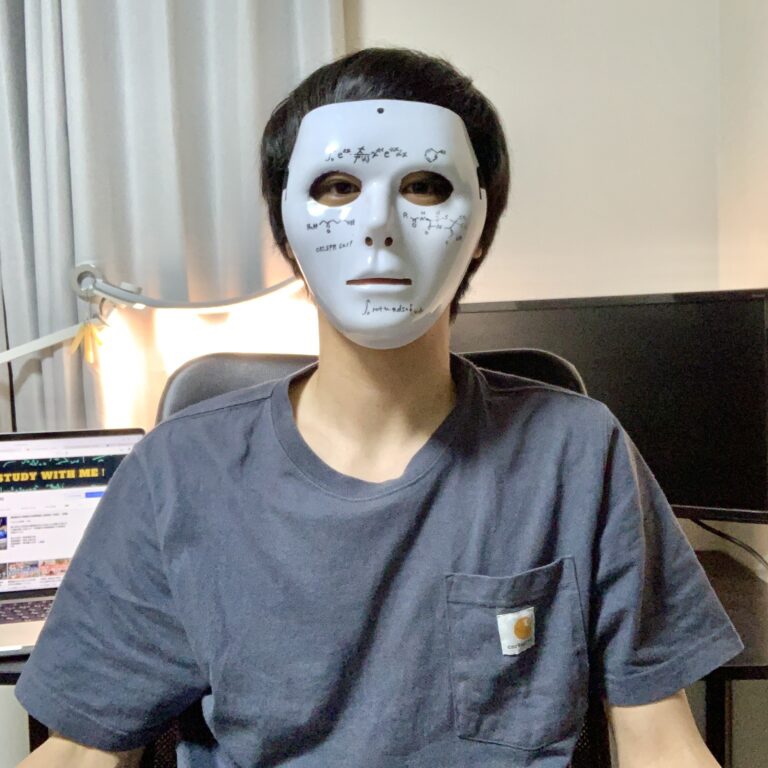
分量が非常に多いので目的を持って活用しましょう!
青チャートIAの1周に必要な時間
| コンパス | 例題数 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 40問 |
| ★★☆☆☆ | 139問 |
| ★★★☆☆ | 131問 |
| ★★★★☆ | 36問 |
| ★★★★★ | 4問 |
| 共テ必須単元 | 数学と人間の活動 | |
|---|---|---|
| ★1 | 5問 | 4問 |
| ★2 | 50問 | 16問 |
| ★3 | 46問 | 17問 |
| ★4 | 6問 | 10問 |
| ★5 | 2問 | 0問 |
✔︎ 基本例題のコンパス1〜4
✔︎ 重要例題のコンパス3〜4
※ 数学と人間の活動は学習対象外
学習進度
例題の1周目は、全体を平均して1時間に4問のペースで進める
共通テスト数学IAでは「数学と人間の活動」は出題されないため、共通テストでのみ数学を利用する場合や、志望大学の二次試験でこの単元が範囲外の場合は、学習を省いても構いません。
以上を踏まえると、青チャートIAを1周するのに必要な勉強時間の目安は、コンパス1〜3で約70時間、コンパス1〜4で約80時間となります。
青チャートIIBの1周に必要な時間
| コンパス | 例題数 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 32問 |
| ★★☆☆☆ | 148問 |
| ★★★☆☆ | 118問 |
| ★★★★☆ | 51問 |
| ★★★★★ | 7問 |
| 数列 | 統計的な推測 | |
|---|---|---|
| ★1 | 5問 | 7問 |
| ★2 | 19問 | 17問 |
| ★3 | 22問 | 7問 |
| ★4 | 13問 | 2問 |
| ★5 | 2問 | 0問 |
✔︎ 基本例題のコンパス1〜4
✔︎ 重要例題のコンパス3〜4
※ 統計的な推測は飛ばす人が多い
学習進度
例題の1周目は、全体を平均して1時間に4問のペースで進める
共通テスト数学IIBCでは、「数列・統計的な推測・ベクトル・複素数平面と平面上の曲線(※平面上の曲線=式と曲線)」の中から3題を選択します。
二次試験で数Bの範囲に「統計的な推測」が含まれていない場合、この単元を学習対象外とすることが多いですが、志望大学によっては出題範囲に含まれることもあるため、必ず大学の出題単元を確認しておきましょう。
仮に「統計的な推測」を除いた場合、青チャートIIBを1周するのに必要な勉強時間の目安は、コンパス1〜3で約70時間、コンパス1〜4で約80時間となります。
青チャートIIICの1周に必要な時間
| コンパス | 例題数 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 34問 (Cは24問) |
| ★★☆☆☆ | 142問 (Cは57問) |
| ★★★☆☆ | 142問 (Cは66問) |
| ★★★★☆ | 71問 (Cは31問) |
| ★★★★★ | 4問 (Cは1問) |
| ベクトル | 複素数平面 | 平面上の曲線 | |
|---|---|---|---|
| ★1 | 11問 | 7問 | 6問 |
| ★2 | 34問 | 8問 | 15問 |
| ★3 | 35問 | 17問 | 14問 |
| ★4 | 9問 | 13問 | 9問 |
| ★5 | 0問 | 1問 | 0問 |
✔︎ 基本例題のコンパス1〜4
✔︎ 重要例題のコンパス3〜4
※ 数学が共テだけならば数Cのみ
学習進度
例題の1周目は、全体を平均して1時間に4問のペースで進める
二次試験で数学IIICまで課される場合、数学Cは全単元から出題されることが多いです。さらに、共通テストで特定の単元が難化する可能性も考慮すると、理系は数学Cを全単元学習しておくことをおすすめします。
以上を踏まえると、青チャートIIICを1周するのに必要な勉強時間の目安は、コンパス1〜3で約80時間、コンパス1〜4で約100時間となります。
共通テストのみで数学を利用する場合は、数学Cの範囲だけを学習すればよいため、その場合の目安はコンパス1〜3で約40時間、コンパス1〜4で約50時間です。
青チャートが定着するまでの時間
危機感を持つべし
本番まで半年を切っている場合、1日過ぎるごとに完成が遠のいてしまう
先ほど青チャート1周にかかる時間の目安を紹介しましたが、もちろん1周だけでは十分に定着しないため、必要に応じて反復することが大切です。
1周目は時間がかかりますが、2周目は1周目の60〜70%の時間、3周目は40〜50%の時間で進められるようになり、定着が進むにつれて学習にかかる時間は短縮されていきます。
❶ 青チャート例題 1周目:210 h
❷ 青チャート例題 2周目:120 h
❸ 青チャート例題 3周目:90 h
❹ 青チャート例題の周回:30 h
❺ 青チャート各練習問題:50 h
※各練習問題の演習対象は★3〜★4
❻ 共テ実践と青チャ復習:50 h
完成までにかかる目安:550時間
たとえば、1日の数学の勉強時間を1時間とした場合、共テ数学レベルを完成させるまでに2年弱かかります。つまり、2年生の前半からコツコツ積み上げていなければ間に合わない計算です。
6ヶ月で仕上げるとなると、1日に約3時間は数学に取り組む必要があります。数学以外の成績が比較的安定していれば、これは実現可能な範囲でしょう。
一方で、数学以外の科目もまだ基礎が固まっていない場合には、全体の勉強量を底上げしなければ間に合わなくなるため、1日でも早く始めることが重要です。
青チャート完成までの反復方法
問題分量の多い青チャートを効果的に進めるためには、反復方法の工夫が重要です。
手順1 青チャート基礎~標準編
青チャートでは、基本例題のコンパス①〜③が数学の基礎、重要例題のコンパス③が標準にあたります。まずはIA・IIB・C(※二次試験でIIIまで必要な場合はIIIも含む)の基本例題コンパス①〜③を徹底的に定着させ、基礎を固めましょう。
そのうえで、同じくIA・IIB・C(※必要に応じてIIIも含む)の重要例題コンパス③に取り組み、標準レベルを仕上げていきます。
| 定着順 | 学習対象 |
|---|---|
| IA(基礎) | 基本例題 コンパス①〜③ |
| IIBC(基礎) | 基本例題 コンパス①〜③ |
| III(基礎) | 基本例題 コンパス①〜③ |
| IA(標準) | 重要例題 コンパス③ |
| IIBC(標準) | 重要例題 コンパス③ |
| III(標準) | 重要例題 コンパス③ |
基礎から標準レベルを固めるための全体的な勉強の流れは、以下のとおりです。
コンパス①〜③の基本例題を解き進め、解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上にOKマークを書き足しましょう。

コンパス①〜③の基本例題のうち、OKマークがついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。

2周目と同様に、コンパス①〜③の基本例題のうち、OKマークがついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。

コンパス①〜③の基本例題のうち、OKマークまたは◯マークが2つついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。
コンパス①〜③の基本例題すべてにOKマーク、または◯マークが2つついたら基礎は完成です。
青チャートIAで4周目以降まで終えたら、次は青チャートIIBに移り、同じ手順を進めます。IIBも同様に仕上げたら、最後に青チャートIIICに取り組み、IA・IIB・IIICすべてで基礎を完成させましょう。
コンパス③の重要例題だけを、青チャートIA・IIB・C・IIIすべてで並行して毎日解き進め、解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上にOKマークを書き足しましょう。
コンパス③の重要例題のうち、OKマークがついていないものだけを周回し、解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。
コンパス③の重要例題すべてにOKマーク、または◯マークが2つついたら基礎から標準まで完成です。
到達レベル
共通テスト数学で70%〜75%の得点率(偏差値55〜60程度)になる
ここまでをしっかり定着させるだけでも、数学の基礎力は十分に身につきます。次の段階では、本格的に共通テスト数学で8割を目指すための応用力を養っていきましょう。
手順2 青チャート応用編
青チャートの基本例題および重要例題のコンパス④は、数学における応用レベルにあたります。
これまでの工程で基礎から標準レベルまでは十分に身についているはずですので、ここからは応用を定着させていきましょう。
| 定着順 | 学習対象 |
|---|---|
| IA(応用) | 基本・重要例題 コンパス④ |
| IIBC(応用) | 基本・重要例題 コンパス④ |
| III(応用) | 基本・重要例題 コンパス④ |
基礎から標準レベルを固めるための全体的な勉強の流れは、以下のとおりです。
コンパス④の基本例題+重要例題を解き進め、解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上にOKマークを書き足しましょう。
コンパス④を進める際は、IA・IIB・IIICに分けずに、毎日並行して3冊を解き進めるようにしてください。

コンパス④の基本・重要例題のうち、OKマークがついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。

2周目と同様に、コンパス④の基本・重要例題のうち、OKマークがついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。

コンパス④の基本・重要例題のうち、OKマークまたは◯マークが2つついていないものだけを解き進めましょう。解答を見ずに自力で解けた問題には、例題の上に◯マークを1つ書き足してください。
コンパス④の基本例題すべてにOKマーク、または◯マークが2つついたら一旦演習は終了です。
到達レベル
共通テスト数学で75%〜80%の得点率(偏差値60〜65程度)になる
ここまで定着させれば、共通テスト数学で8割を狙える力が身についてきます。とはいえ、まだ十分に安定して得点できる段階には達していません。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
手順3 青チャート実践復習編
ここまで定着できれば、共通テスト数学の対策としての参考書演習は十分です。以降は、共通テスト形式の実践演習に取り組んでいきましょう。
❶ 共通テストの過去問を自力で解く
❷ 解き直しと苦手分析を丁寧に行う
❸ 苦手または理解が浅い単元の復習
❹ 復習した単元の理解度チェック
❺ 以降は❶〜❹を本番まで繰り返し
❶❷ 共通テスト実践と解き直し
まずは、上記手順の❶〜❷に従い、共通テストの過去問(各予備校の模擬問題集でも構いません)を制限時間内に自力で解き、解き直しと苦手分析を丁寧に行いましょう。
解き直しと苦手分析のやり方がわからない場合は、以下の記事で具体的に解説しています。
❸❹ 苦手の復習と理解チェック
❶ 苦手が判明した単元の定義を確認
❷ 単元の例題コンパス★3を解き直し
❸ 単元の例題下にある練習問題を解く
共通テスト実践で判明した苦手な単元(失点率の高い単元)は、青チャートを使って復習します。
まずは該当単元の冒頭にある説明ページを読み、定義や公式の導出過程などを確認しましょう。

次に、該当単元のコンパス③の例題を自力で解けるかどうか解き直してみましょう。
解けなかった場合は、解説を読んで理解したうえで再度解き直し、最後に練習問題を解いて理解度を確認してください。

苦手や理解不足を克服できるまで繰り返せば、共通テスト数学で安定して8割以上を狙えるようになります。
到達レベル
共通テスト数学で80%以上の得点率(偏差値65以上)を安定して狙える
青チャートの具体的な勉強法
ここまでは、青チャートを使ってどのようにステップアップをしていくか、その全体的な流れを紹介してきました。
ここからは、実際に青チャートを読み進めたり例題を解いたりする際に、どのような点に注意して学習すべきか、具体的な勉強法を解説します。
| 学習手順 | 学習対象 |
|---|---|
| ❶ | 単元はじめの説明を読む |
| ❷ | ヒントなしで例題を解く |
| ❸ | 指針を見て例題を解く |
| ❹ | 解説を読んで理解する |
| ❺ | 解けるまで解き直しする |
| ❻ | 理解した内容をメモする |
手順1 単元はじめの説明を読む

❶ 説明を読んでざっくり理解する
❷ わからない場合は数回読み直す
❸ 理解できなければネットで調べる
❹ それでもわからなければ例題に進む
新しい単元に入ったら、まず冒頭の説明ページに目を通し、おおまかに理解しておきましょう。
もし読んでも理解できない場合は、数回読み返したり、ネットで調べたりしてみてください。それでも理解が難しいときは、ひとまず例題に進んで構いません。
手順2 ヒントなしで例題を解く

✔︎ 問題文を読んでヒントなしで解く
✔︎ 必ず途中過程や図を書いて解く
✔︎ 20秒考えてわからなければ手順3へ
まずは問題文を読み、ヒントなしで解いてみましょう。その際は、ノートやコピー用紙に途中過程や図を丁寧に書いてください。
目で確認するだけのやり方は、基礎が十分に入っている場合にのみ有効です。基礎〜標準レベルがまだ定着していない人は、必ず途中式やつなぎの日本語までしっかり書いて解きましょう。
また、解くときの注意点として、20秒考えても進展がない場合は、手順3へ進むようにしてください。
手順3 指針を見て例題を解く

✔︎ 指針を読んでから解いてみる
✔︎ 必ず途中過程や図を書いて解く
✔︎ 1分考えてわからなければ手順4へ
手順2で自力で解けなかった場合は、例題の下に載っている指針を読み、解けるかどうか再度挑戦してみましょう。
指針を読み終えてから1分考えても解答が思いつかない場合は、長時間悩まずに手順4へ進むようにしてください。
手順4 解説を読んで理解する

✔︎ 途中過程の式が合っているか確認
✔︎ 解説を読んで理解できたら次の例題へ
✔︎ 途中過程が間違っていたら手順5へ
解けた場合は、自分の解答の途中過程が正しいかどうか、解説を読んで確認しましょう。途中過程に誤りがあった場合は完答とは言えないため、解説を読んで理解したうえで手順5に進みます。
答えも途中過程も正しかった場合は、そのまま次の例題に進みましょう。
✔︎ 解説を読んで理解できたら手順5へ
✔︎ 解説が理解できなければ5分考える
✔︎ 5分考えても理解できなければ保留
解けなかった場合は、まず解説を読んで理解するようにしましょう。問題なく理解できた場合でも、それで終わりにせず手順5へ進んでください。
もし解説を読んでも理解できなかった場合は、5分だけじっくりと考えてみましょう。それでも理解できなければ、その時点では知識が不足している可能性が高いため、一旦保留にして構いません。
保留とは
身近に質問できる人がいる場合はすぐに質問し、いない場合はその例題を一旦飛ばし、1週間後に改めて振り返ってみること
手順5 解けるまで解き直しする
手順4で解説を読んで理解したら、もう一度その例題を解き直しましょう。このときに大切なのは、途中過程の記述も含めて、自力で完答できるまで繰り返すことです。
| ❶ | 解説を思い出しながら解き直す |
| ❷ | 途中で詰まったら解説を読み直す |
| ❸ | 解説を思い出しながら解き直す |
| ❹ | 完答できるまで❶〜❸を繰り返す |
数学の得点は、理解しただけでは伸びません。解法を理解し、それを自力で使いこなせるようになって初めて、得点につながります。
その場で解き直し、自力で完答できるまで「解説の確認 → 最初から解き直し」を繰り返しましょう。
理解しただけで「できる気」になり、次々と参考書を進めた結果、模試や本番で完答できない受験生は毎年多く見られます。以下の特徴に気をつけてください。
① 解説を見れば問題なく理解できる
② なぜ解けなかったのかと後悔する
手順6 理解した内容をメモする
おすすめの方法
自分が理解しやすい言葉で要点をメモし、あわせて図やイラストなど脳内イメージを追記しておくと、理解がより一層深まる
青チャートの解説は、きれいに整理されているというメリットがある一方で、数学が得意でない人にとってはやや言葉足らずに感じられることがあります。
せっかく手順5までの過程で例題を理解できても、次の周回時に忘れてしまっていては、再び理解するのに時間がかかってしまいます。
そのため、後から読み返したときにすぐ理解できるよう、自分の言葉でメモを残しておきましょう。
数学を偏差値70まで伸ばす勉強
今回の方法で青チャートを固めるだけでも、共通テストで8割を狙えるのはもちろん、記述模試でも偏差値65前後まで伸ばすことが可能です。
ただし、さらに偏差値70を目指して難関大学の数学にも対応できるようにしたい場合は、以下の記事をご覧ください。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。