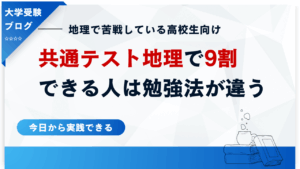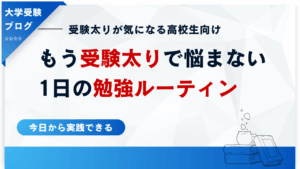【理系決定版】偏差値50から60に上げる勉強法とかかる時間
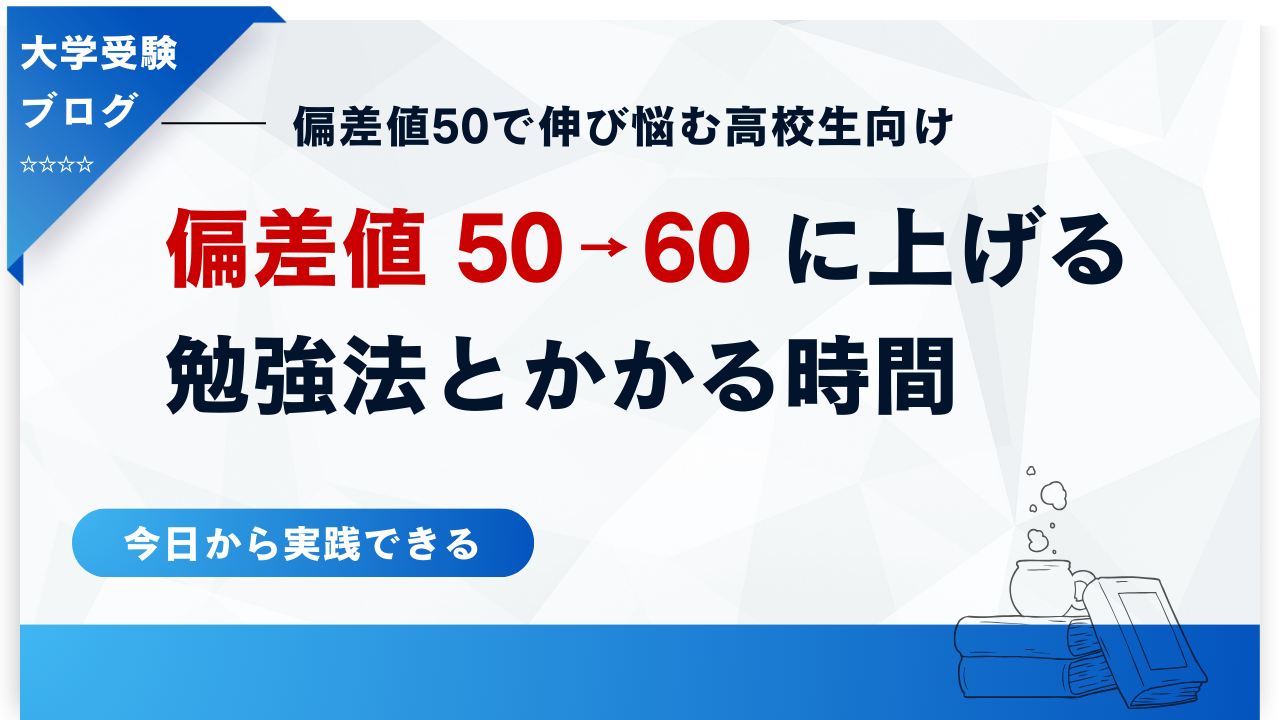
勉強しているのに成績が下がった、偏差値60なんて達成できる気がしない…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

勉強する前よりも、勉強してからの方が成績が下がったんだけど…

勉強しても勉強しても、ぜんぜん成績が伸びないのはどうして…
成績が偏差値50付近で伸び悩み、このまま頑張っても偏差値60を超えることはないのかもしれないと、落ち込んでいませんか。
あとどれくらい勉強したら、偏差値60なんて超えられるんだろう
現状から考えると、偏差値60は夢物語のように感じるかもしれません。しかし、やるべきことと必要な分量をこなすことができれば、偏差値60は達成できる壁です。
何をどれくらい勉強をすれば、いつ頃までに達成できるのか。今回は偏差値50から60に上げるために必要な勉強法と、達成までにかかる時間について紹介します。
✔︎ 偏差値50から60に上げる勉強法
✔︎ 偏差値50から60までの参考書
✔︎ 偏差値50から60までの勉強時間
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
偏差値50から60までにかかる期間
偏差値を50から60まで上げるためには、それなりの勉強期間が必要です。SNSでMARCHは3ヶ月で十分などと謳ったコンテンツがありますが、成績はそう簡単には上がりません。
では、偏差値を60まで上げるためには、どれくらいの勉強量と時間が必要になるのか。
あくまで目安ですが、全統記述の基準で偏差値を50から60まで上げようとすると、理系の場合はおよそ1,300時間ほどの勉強量が必要になります。
総合偏差値50から60まで、理系の場合はおよそ1,300時間かかる
1,300時間というのは、偏差値を50から60まで上げるために必要な合計の時間です。では、1日あたりの勉強時間に換算してみるとどうでしょう。
1年はおよそ休日120日と平日245日で構成されています。月あたりに直すと、休日が10日と平日が20日ほどあります。
| 年間休日 | 約120日 |
| 年間平日 | 約245日 |
| 月間休日 | 約10日 |
| 月間平日 | 約20日 |
もし3ヶ月で偏差値を50から60まで上げようとすると、授業時間を除く1日の勉強時間は、平日と休日ともに14.5時間ほど必要になります。これはあまりにも非現実的な時間です。
では、現実的な勉強時間として、平日の勉強時間が5時間、休日の勉強時間が10時間としましょう。すると、1ヶ月あたり200時間ほど勉強ができることになります。
先ほどの1,300時間を200時間で割ると、およそ6ヶ月ほどかかることになります。これだけ真剣に勉強して、半年かけてようやく偏差値が60まで上がるのです。
かかる期間の目安
平日5時間・休日10時間ほどの勉強で、偏差値50から60まで上げるのに半年かかる
科目別に必要な勉強時間の目安
偏差値50から60まで上げるために必要な合計時間と、1日あたりの勉強時間の目安を紹介しました。ここでは、科目別に必要な勉強時間の目安をご紹介します。
科目別の勉強時間の目安
| 英語 | 340時間 |
| 数学 | 400時間 |
| 国語 | 90時間 |
| 理科1 | 220時間 |
| 理科2 | 220時間 |
| 社会 | 60時間 |
| 情報 | 10時間 |
理系の場合は、数学と理科の攻略がカギとなります。しかし、これらの教科は難易度が比較的高く、ゆえに得点の変動幅も大きいです。
一方で、英語は実力に応じて得点が安定します。そのため、変動の大きい理系だからこそ、得点が安定しやすい英語の勉強にも時間をかける必要があります。
英語力を鍛えてできるだけ点数を安定させ、安心して受験本番に臨めるようにしましょう。
科目別の1日あたりの勉強時間
前述のとおり、総合偏差値を50から60まで上げるには、最低でも半年ほどの時間が必要です。その半年間の学習では、科目別に次のような配分を意識してみてください。
0〜4ヶ月目の勉強時間の配分
| 平日の勉強 | 休日の勉強 | |
|---|---|---|
| 英語 | 1時間30分 | 3時間0分 |
| 数学 | 1時間30分 | 4時間0分 |
| 国語 | 0分 | 0分 |
| 理科1 | 1時間0分 | 1時間30分 |
| 理科2 | 1時間0分 | 1時間30分 |
| 社会 | 0分 | 0分 |
| 情報 | 0分 | 0分 |
英語と数学は主要科目であることに加え、成績が上がるまでに時間がかかるので、他の科目に比べて優先的に固めていきましょう。
それに加え、理系の場合は理科2科目もわりと重いです。優先順位としては英語と数学に劣りますが、0〜4ヶ月目は勉強時間のうち3割ほどを理科にかけるようにすると、バランスよく学習を進めやすいです。
0〜4ヶ月は英語と数学で70%、理科2科目で30%ほどの割合で勉強時間を分配するとよい
4〜6.5ヶ月目の勉強時間の配分
| 平日の勉強 | 休日の勉強 | |
|---|---|---|
| 英語 | 1時間0分 | 1時間0分 |
| 数学 | 1時間0分 | 3時間0分 |
| 国語 | 1時間0分 | 2時間0分 |
| 理科1 | 1時間0分 | 1時間30分 |
| 理科2 | 1時間0分 | 1時間30分 |
| 社会 | 30分 | 1時間0分 |
| 情報 | 0分 | 0分 |
最初の4ヶ月間で英語と数学、および理科2科目に時間をかけたので、残りの2ヶ月半は各科目に勉強時間をバランスよく配分していきましょう。
勉強は基礎が固まるまでは集中的に取り組んだ方が定着しやすいですが、ある程度固まってからはすこしずつの勉強でも身につくようになります。
残りの期間では、これまでに触れていなかった国語や社会のようなサブ科目にも少しずつ時間をかけていきましょう。
4〜6.5ヶ月は英数理だけでなく、他のサブ科目にも時間を配分してバランスよく進めるとよい
偏差値60までの英語の勉強法
英語の偏差値が50前後の場合は、以下の手順で学習を進めてみてください。
英語の偏差値50〜60の勉強内容
偏差値50以上の場合、基本的な英単語や英文法、英文解釈力はそれなりに身についた状態となっています。しかし、安定して得点をするために必要な基礎が十分に固まっているかというと、そういうわけでもありません。
そのため、偏差値50以上の段階からは、長文読解の練習を進める中で、つど発見した英単語や英文法、構文知識の弱点を埋めていきます。
特に、長文の中で定期的に出てくるのに正しく使えなかった知識は、文法の参考書や英単語帳にてピンポイントで復習をするチャンスです。
❶のステップでは、長文問題を解いて、解答解説の確認、苦手のピンポイント復習までを行いました。では、長文1題を解き終わったらそれで終了かというと、そういうわけではありません。
その長文を時間をかけて全文訳し、そのレベルの文章を正しく訳す力が備わっているかどうかを確認してください。自力で訳せなかった文章は、どのように訳すのかを確認して、次にいかせるようにメモをしておきましょう。
❷のステップにて全文訳ができたら、次にやることは「付属の英語音声に合わせて音読」をするシャドーイング練習です。シャドーイングのやり方(タップで確認)は、この勉強ステップまとめの後で紹介します。
さて、❶〜❸にて長文1題の学習方法を紹介してきましたが、❶〜❸の流れを1日で終わらせようとすると、膨大な時間がかかります。
ですので、1日目は❶、2日目は❷、3日目は❸のように、1日ごとに分けて進めてみるとよいでしょう。
この段階まで学習が進むと、英単語熟語・英文法・構文知識・英文解釈力が身についているので、それなりに英作文(和文英訳)ができる状態になっています。ここから重要になってくるのは、入試本番で減点をされない英作文の仕方です。
日本語の例文をもとに紙に書いて英作文をし、模範解答と解説を確認して、模範解答で使われている表現を使いこなせるよう、書いたり音読したりと反復しながら、頭に入れていきましょう。
英作文の練習で短文の和文英訳ができるようになれば、あとは「自分が使いやすい表現を用いて」長い文章を書いていく練習になります。自由英作文の場合、長い英文を書くのが大変というのもありますが、どちらかというと次に2点が課題となります。
1つ目は、お題に対して「日本語で自分の意見を論理的に」書けるかどうか。2つ目は、自分で書いた日本語の文章を、いかに自分が英文を書きやすいように言い換えられるかどうか。これら2つの練習をしっかりと行えば、長い英文を書くことそのものは、あまり苦労しないでしょう。
上記で紹介した5ステップは、面倒くさくてつまらない作業です。それゆえに、やりたがらない人が多いので差がつきます。
英語の学習は、いかに日々の面倒くさいと向き合うかですので、上記の流れをルーティン化して、着実に成績を伸ばしていきましょう。
シャドーイングのやり方
シャドーイングはそれなりに大変なので、面倒くさくてやりたくないという人も少なくありません。しかし、シャドーイングは受験本番までの長い目で見ると、非常に時間効率がよい学習方法なのです。
✔︎ リスニング力が身につく
✔︎ 長文の速読力が格段に上がる
大変かもしれませんが、英語の点数アップに効率よく直結するので、ぜひ以下の手順でシャドーイングをしてみましょう。

とはいっても、シャドーイング用の音声って何を使えばいいんだろう…
使用する素材は、学習対象が長文読解の場合は、長文参考書に付属の音声、学習対象が英文解釈の場合は、英文解釈の参考書に付属の音声など、参考書に付属の英語音声を使うとよいでしょう。
- シャドーイング STEP1
- まずは英文全体を自力で正しく訳してください(長文読解の参考書を学習するケースなど、自力で正しく全文を訳す過程がすでに終わっている場合は、STEP1を飛ばして構いません)。
- シャドーイング STEP2
- 英語音声を再生して、自分的に聴きとれる限界まで反復しましょう。このとき、聴きとれた英語を紙に書くとベストですが、大変で続かなそうであれば、耳で聴くだけでも構いません。
- シャドーイング STEP3
- STEP2にて音が聴きとれ出したら、英文を見ながら、音声に合わせて音読をしましょう。音声の速度に合わせて、ある程度スラスラと音読できるようになったらクリアです。
- シャドーイング STEP4
- STEP3にて音声のスピードで音読ができるようになったら、次は英文を見ながら音読をしつつ、同時に「英語の意味」も脳内で訳すようにしましょう。最初は苦戦をしますが、何度も繰り返しているうちに英語のまま意味がわかるようになってきます。
- シャドーイング STEP5
- STEP4までの流れができれば、最後は何も見ずに、英語の音声のみを聴きながら、同時に音読をしていきます。このとき、STEP4でやった、音読と同時に「英語の意味」を脳内で訳すという動作も同時に行いましょう。音声に合わせて音読をしながら、ある程度英文の意味がとれるようになってきたら、その日のシャドーイング練習は終了です。
かかる目安の時間
STEP2〜STEP5までのシャドーイングが完了するまで、200~300語で40分~1時間程度かかる
英語のおすすめ参考書ルート
ここからは、おすすめの参考書と勉強法について紹介します。
偏差値60までのおすすめ参考書
✔︎ 本番まで英単語熟語を反復
✔︎ 英文法・英文解釈の弱点埋め
✔︎ 読める英文レベルを上げる
✔︎ 英文を読むスピードを上げる
偏差値50を超えてくると、基礎的な英単語熟語や英文法、英文解釈の知識はある程度身についた状態になります。ここからは長文演習を進めながら、見つかった弱点をピンポイントで復習していくとよいでしょう。
また、難関大学を志望する場合は、読める英文のレベルを上げるために難易度を上げた英文解釈を、難関私立の場合はレベルの高い英文法まで学習しなければなりません。
志望大学のレベルによってやることが変わってくるため、受ける大学の英語レベルはどの程度か、どのような形式で出題されるのか、一度過去問に目を通しておくとよいでしょう。
ターゲット1900
ターゲット1900は、受験基礎から旧帝大レベルまでの英単語を掲載している英単語帳です。ターゲット1200を使用していた人は、1400を挟まずにそのまま1900へとつなぐことができます。
また、時間があれば1〜1900まで覚えた方がよいですが、中堅以下の大学を志望する場合は、1500までをしっかり定着させるだけでも十分でしょう。
ターゲット1900の進め方ですが、①まずは見出し単語をひと通り覚える ②覚えられたら次に派生語も覚える ③全体的に覚えたら右ページの例文を用いて定着させる、というように段階を踏んで学習すると挫折しづらいです。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
英熟語は長文演習の過程で覚えていくことで、ほとんどの場合は対策ができます。ただ、もしまとまった知識として覚えたい場合は、ターゲット1000か速読英熟語がおすすめです。また、ターゲット1000は分量が多いため、難熟語が集められたPart5はやらなくても構いません。
英文法ポラリス1
現在の受験英語では、特定の私立大学を受けない限り、単純な英文法としての問題が大量に出題されることが減りました。そのため、英文を読むために必要な文法知識を入れられたら、読解力を上げることに時間を費やす方がよいでしょう。
英文法ポラリスシリーズは、問題数があまり多くないため、時間がない中でも英文法の知識確認がしやすいです。ポラリス1レベルは読解に必要な内容ですので、十分に身についているかどうか、演習してみるとよいでしょう。
文法の勉強方法
まずは自力で問題を解き進め、根拠も含めて正解できた問題と、間違えたあるいは根拠が曖昧だった問題を振り分けること。2周目以降は、1周目に根拠を含めて正解できた問題以外を集中的に反復していく。
ただ丸暗記をしても、文章の中で使えない知識となってしまうので、正解の根拠を説明できるようにすることが大切。
The Rules1・2
この参考書は、長文問題の読み進め方を丁寧に解説した、英文解釈と長文読解の合体版参考書です。偏差値50を超えていれば解き進めることができる内容ですので、長文読解を通して英文を読む練習を積み重ねましょう。
冒頭でも説明しましたが、ただ解くだけでなく、全文訳とシャドーイングも欠かさず行なう(タップで確認)ようにすると、非常に効果的です。ただ、英文の量が意外と多いので、音読が体力的にしんどい場合は、パラグラフごとに分けてシャドーイングをしても構いません。
基礎英文解釈の技術100
この参考書は基礎とついていますが、特に後半になるにつれて難しくなっていきます。この参考書に載っている英文が正しく解釈できるようになれば、難関大を目指さない限りは、十分な解釈力が身につきます。
The Rules1・2の学習と並行して、あるいはThe Rules1・2が終わった後に学習を進めるのがおすすめです。
英文解釈の勉強方法
まずは自力でSVを振りながら英文の構造を把握し、日本語訳を紙に書きましょう。このときに、変な日本語になってもよいので、英文法のルールに従って正しく正確に直訳するようにしてください。
直訳ができたらそこで初めて、直訳の日本語をもとに、意味が変わってしまわないように自然な日本語に書き換えましょう。ここまでができたら、解答解説の確認をします。
最後は、例文をシャドーイングしながら(付属の音声を使う)、返り読みをせずに前から順に(左から右に)訳します。これを数回ほど繰り返して前から順に意味をとれだしたら、次の例文へと移ります。
偏差値60までの数学の勉強法
数学の偏差値が50前後の場合は、基本的な問題はそれなりに解ける状態です。そのため、以下の流れでの勉強法が効率よく効果を発揮します。
参考書1周目の進め方
どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースにOKマークを1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
参考書1周が終わったら次へ次へと進む人がいますが、参考書の演習は1周だけでは完成しません。

この問題、どこかで見たことはある気がするけど、解き方が思いつかない…
模試やテストの時に経験するこの現象は、参考書演習が中途半端な状態で終わってしまった時によく発生します。
参考書2周目以降の進め方
OKマークがついていない問題のみを解き進め、どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。
自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。
自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。
解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。
単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。
自分が習得したい問題すべてにOKマーク、あるいは◯が2つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。それまでは、❶〜❹の流れに沿って繰り返し周回し、参考書を反復しましょう。
ここまでの流れが習得できれば、模試で数学の偏差値が60前後まで伸びます。
数学のおすすめ参考書ルート
ここでは、偏差値60超えを目指すときにおすすめの数学参考書を紹介します。
解法を定着させる数学参考書
| 解く問題 | 例題★2〜★4 |
| 解き進め方 | OKか◯2つ付くまで反復 |
青チャートは、章末問題や★4〜★5以外はそれほど難易度は高くなく、解説も丁寧に書かれている網羅系参考書なので、一気にやり込む参考書としてはおすすめです。
青チャートよりも少しだけ難易度が低い黄チャート(例題★2〜★5)、他にも青チャートと同等のFocus Gold(例題★2〜★3)やNEW ACTION LEGEND(例題★2〜★3)などがありますが、いずれを使っても構いません。
また、受験までの残り時間が少ない場合は、頻出問題だけに絞った基礎問題精講のような参考書でも代用できます。
定着を確かめる数学参考書
網羅系参考書が終わったら、次は本当に解法が身についたかどうかを確かめる実践演習です。参考書にあまりお金をかけないという観点で、教科書の傍用問題集を用います。
| 解く問題 | 発展を除く全ての問題 |
| 解き進め方 | OKか◯2つ付くまで反復 |
代用できる参考書
ここで挙げているクリアー数学はあくまで一例です。通っている学校によって配られる問題集は異なるので、ご自身の学校で配られた教科書の傍用問題集で構いません。
在学中の場合、定期テストの対策にもなるので、学校で配られた問題集を用いた定着度の確認作業は非常におすすめです。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
偏差値60までの物理の勉強法
ここでは、偏差値60超えを目指すときにおすすめの物理の参考書を紹介します。
解法を定着させる物理の参考書
✔︎ 頻出の基礎問題が網羅されている
✔︎ シンプルな構成のため進めやすい
✔︎ 問題数が適量のため反復しやすい
頻出の問題をかき集めており、教科書傍用の問題集と比べて問題数が適量なので、時間がない中でも基礎の反復演習がしやすい点が強みの一冊です。
この参考書で到達できるレベル
到達レベル
理解した上で解けるようになれば共通テストで高得点を狙えるだけでなく準難関大学レベルまで対応できるようになる
物理を共通テストでしか使わない場合や、中堅大学を志望する場合は、参考書演習は基礎問題精講までで構いません。
この参考書の内容が理解した上で身につけば、十分に合格ボーダーを狙える力が身につきます。あとは早めに過去問対策に入り、過去問演習と参考書の振り返りを行なうとよいでしょう。
この参考書の効果的な勉強法
前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。
もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。
本質が理解できる物理の参考書
✔︎ 問題の解き方の解説が詳しい
✔︎ 本質的な理解を促す解説が多い
✔︎ 問題量が適度で進めやすい
物理のエッセンスは多くの受験生が使う有名な参考書です。そのため、この参考書から手をつけ始める人もいますが、この参考書は物理中級者向けです。
学習するタイミングを誤るとかえって物理がわからなくなるような、すこし扱いの難しい参考書となっています。
しかし、基礎が身についた段階で取り組むには、かなり効果的な参考書です。
なんとなく理解していた物理の本質が明確にわかり、応用力の土台がしっかりと身につくので、暗記物理になっている懸念がある場合は、この参考書を学習しましょう。
応用レベルまで身につけなければならない難関志望にとっての登竜門ですので、上位の大学を目指す場合は触れておくことをおすすめします。
この参考書で到達できるレベル
到達レベル
理解した上で解けるようになれば準難関大学から旧帝大レベルまで対応できるようになる
この参考書に載っている内容をしっかりと理解できた上で問題が解けるのであれば、旧帝大レベルまで目指すことができます。
しかし、わかった気で終わってしまう場合が少なくありません。
本質理解に時間をじっくりかけるよりも、演習量を重ねることによって理解を進めたい性格であれば、この参考書のあとにもう1冊、演習系の参考書を挟んでおくと安心でしょう。
この参考書の効果的な勉強法
まずは講義を読んで、これまで勘違いしていた内容や、本質を理解できていなかった内容があれば理解する。
左右の見開き1ページ分の内容を読み終えて、新たな発見があった場合は、字は汚くても構わないので理解した内容の要点を参考書に直接メモする。
勉強ステップ1が終わったら次のページへ移動して同様のやり方で学習し、その章の終わりまで同様に進める。
途中で例題(Ex)が出てきたら、その場で自力で解いてから解答を確認する。解説を読んで理解ができたら再度自力で解き、完全に解けるまで繰り返してから次へ進む。
もし解説を読んでも理解できなかったら、講義を読み直してから再び解説の理解に励み、解説が理解できたら自力で解けるまで解きなおす。
例題(Ex)と章末の練習問題のみ解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、その章の講義を読み直して理解した内容の要点を口頭で説明できるようにし、再度自力で解けるまで繰り返す。
例題(Ex)と章末の練習問題のうち、OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、その章の講義を読み直して理解した内容の要点を口頭で説明できるようにし、再度自力で解けるまで繰り返す。
例題(Ex)と章末の練習問題のうち、OKマークあるいは⚪︎マークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、その章の講義を読み直して理解した内容の要点を口頭で説明できるようにし、再度自力で解けるまで繰り返す。
すべての問題に⚪︎マークがついたら参考書は完成とする。
偏差値60までの化学の勉強法
ここでは、偏差値60超えを目指すときにおすすめの化学の参考書を紹介します。
解法を定着させる化学の参考書
✔︎ 頻出の基礎問題が網羅されている
✔︎ シンプルな構成のため進めやすい
✔︎ 問題数が適量のため反復しやすい
頻出の問題をかき集めており、教科書傍用の問題集と比べて問題数が適量なので、時間がない中でも基礎の反復演習がしやすい点が強みの一冊です。
この参考書で到達できるレベル
到達レベル
理解した上で解けるようになれば共通テストで高得点を狙えるだけでなく準難関大学レベルまで対応できるようになる
化学を共通テストでしか使わない場合や、中堅大学を志望する場合は、参考書演習は基礎問題精講までで構いません。
この参考書の内容が理解した上で身につけば、十分に合格ボーダーを狙える力が身につきます。あとは早めに過去問対策に入り、過去問演習と参考書の振り返りを行なうとよいでしょう。
この参考書の効果的な勉強法
前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。
もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。
応用まで身につける化学の参考書
✔︎ 標準から応用の頻出問題を網羅
✔︎ 基礎力がない逆効果になりうる
重要問題集は、多くの難関大志望の受験生が使う有名な参考書です。そのため、この参考書から手をつけ始める人もいますが、内容は中級レベル以上向けです。
また、解答がそれほど丁寧ではないため、基礎が身についてない人が独学で進めるには、少し苦労をするでしょう。
ただ、基礎が身についた段階で取り組むには効果的な参考書ですので、基礎問題精講が固まった段階で移るとよいです。
この参考書で到達できるレベル
到達レベル
理解した上で解けるようになれば準難関大学から旧帝大レベルまで対応できるようになる
もしも中堅大学を志望しており、重要問題集を使う場合は、A問題のうち7割以上を解ける状態にしておくとよいでしょう。
準難関大学を志望する場合は、A問題のすべてと、B問題の必・準のうち8割以上を解ける状態にしておくようにしましょう。
旧帝大を志望する場合は、A問題のすべてと、全B問題のうち7.5割以上を解ける状態にすることが目標となります。
この参考書の効果的な勉強法
この参考書を演習するときの進め方がわからない場合は、以下の学習順を参考にしてみてください。
| 理論 | 無機 | 有機 | 高分子 | |
|---|---|---|---|---|
| A必 | 順番1 | 順番3 | 順番5 | 順番7 |
| A準必 | 順番2 | 順番4 | 順番6 | 順番8 |
| A残り | 順番9 | 順番10 | 順番11 | 順番12 |
| B必準 | 順番13 | 順番14 | 順番15 | 順番16 |
| B残り | 順番17 | 順番18 | 順番19 | 順番20 |
重要問題集には、基礎から標準レベルのA問題と、応用レベルのB問題があり、さらに問題ごとに「必須問題」「準必須問題」「これら以外」に分かれています。
B問題は難関大学を志望する受験生向けですので、それ以外の受験生はA問題を中心に進めるとよいでしょう。時間がない人はA問題の必・準必のみでも構いません。
前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。
根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。
もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。
根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。
すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。
偏差値60までの国語の勉強法
ここでは、偏差値60超え(共通テスト7割)を目指すときにおすすめの国語の参考書を紹介します。
古文の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 文法(特に助動詞・敬語)を学ぶ
✔︎ 単語帳の単語をすべて覚える
✔︎ 実践を繰り返し弱点を埋める
古文単語の勉強法
古文単語315は、古文単語とその意味を載せているだけでなく、イメージしやすい絵と、その言葉になった語源も一緒に載せてくれています。
絵を見ながらイメージをわかせつつ、なぜその古文単語ができあがったかの理由と背景を読んで理解すれば、知識が長期的に定着しやすくなるので、非常におすすめの単語帳です。
ただし、すべてを学習すると分量が非常に多いので、まずは赤字の見出しのみ覚えるようにして、もし本番までに時間が残されていたら、黒字部分の意味を覚えるようにしましょう。
英単語と比べると分量は少ないため、夏休み(7月〜8月)に一気に時間をかけて覚えると、後でラクになります。
単語の覚え方
まずは古文単語とその意味(赤字)を声に出して反復しながら覚える。このやり方で見開き1ページ分を覚えたら、次のページへ移動して同様の作業を行なう。
その日の分量が終わったら、最後にその日覚えた古文単語を覚えているか通しで復習する。覚えていない単語があった場合は、その日の分量の最初からやり直して、通しでクリアするまで繰り返す。
その日の分量をクリアできたら、寝る前、あるいは次の日の朝に復習をする。
全体的にある程度覚えられたら、次は単語単体ではなく例文を使って覚えているか確認をする。例文での単語の使われ方も覚えられたら古文単語はOK。
古典文法の勉強法
富井の古典文法は、これまで学校の古典の授業をまともに受けていなかった人でも取り組めるような、話し言葉で書かれた非常にわかりやすい文法参考書です。古典文法の全体像を把握でき、共通テストで必要とされる文法は網羅されています。
ただし、問題演習が少ないため、知識のインプットとしては申し分ありませんが、これとは別にアウトプット用の参考書もしておくとベストです。
文法の学習手順
まず1周目は章の中に含まれている講を読み進めていき、書かれている内容を理解する。内容が理解できたら、参考書にそのまま書き込んでよいので、理解したことを自分の言葉でメモする。
1つの講が終わったら練習問題を解き、正答率が悪い場合は(目安は50%以下)、再びその講の説明を読み返して、理解し直してからもう一度解き直すこと。
2周目以降は、別冊を使って反復し、わからないところだけ本冊の内容を確認する。
富井の古典文法がある程度終われば、実際にどれほど身についているか、実践演習をしていきます。その時に用いるアウトプット用の参考書が、ステップアップノート30です。
実践演習の手順
まず1周目は問題を解き進めていって、自力で解ける問題と解けない問題を振り分ける。その際に、解説を読んでも理解できない箇所があれば、富井の古典文法で該当箇所を振り返り、理解し直すこと。
2周目以降は、1周目に解けなかった問題のみを解き進め、ある程度できるようになった段階で、一旦参考書の演習はOKとする。
古文の実践演習
ここでは駿台の実践問題集を紹介していますが、そこまで古文に力を入れるつもりがない人は、やや簡単な河合の総合問題集でも構いません。
ただし、昨年分の河合全統マーク模試をそのまま載せているので、浪人生の場合は問題が被ることがある点に注意が必要です。
漢文の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 構文を覚えて使えるようにする
✔︎ 過去問演習を何度も繰り返す
共通テストの漢文対策は、この参考書に載っている構文を覚えて使えるようにするだけで、かなり得点率が変わってきます。
それほど分量も多くなく、直前期で一気に追い込むこともできるので、時間がない理系受験生にはありがたい一冊です。もちろん、漢文の知識がまっさらな状態からでも問題なく取り組めるので、その点はご安心ください。
この参考書が仕上がったら、駿台の実践問題集や過去問などの共テ形式の実践を行ない、忘れている箇所のみピンポイントで復習すると、安定して高得点がとれるようになります。
評論の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 解き方の仕組みを理解する
✔︎ 根拠だけをもとに答える練習
✔︎ 過去に出された漢字を覚える
この参考書は、国語が苦手な理系受験生を助けてくれる、非常におすすめの一冊です。論理的な読み解き方を丁寧に説明してくれているため、現代文における解き方のルールをインプットすることができます。
また、根拠を徹底した参考書ですので、いつも現代文を解くときに書かれていない想像までして答えてしまうという人にも効果的です。
理屈で学習を進めたい人に向いている参考書ですので、理系で国語に困っている場合は、ぜひ取り組んでみてください。
評論の勉強方法
まずは自力で問題を解くが、このときにただ読んで答えるだけでなく、本文の構造がどうなっているか(逆説・純説・対立・修飾など)を書き込みながら、解き進めていく(書き込むのが嫌な場合はコピーする)。
解き終わったら解答解説を確認し、設問の答えがなぜそうなるのかを確認した後に、自分の解釈した文章全体の構造と、模範回答の文章全体の構造を照らし合わせる。
自分のものと模範解答が異なる場合は、なぜ違うのかを確認して理解する。これを毎回の題で繰り返し、根拠を持って答える意識を身につける。
評論の漢字対策は必須
評論での安定した得点源といえば漢字です。配点があまり大きくないので、時間をかけすぎるのは避けたいですが、いっさい対策をしないのももったいないです。
ですので、共通テストの漢字対策は、共通テストを用いて行なうようにしましょう。駿台の実践問題集のような、各塾が出している模擬問題集でもよいですし、実際の共通テスト過去問を用いても構いません。
国語の共テ形式を解いた際に、漢字のパートで間違えたものは、ノートや単語カードなどにまとめて、何度でも復習できるようにしておきましょう。
実用文・小説の勉強法
実用文の勉強法
実用文の範囲は図表の読み取り要素が強いため、どちらかというと理系選択の高校生には馴染みがあるかもしれません。
課題となるのは、内容というよりも「かけられる時間の短さ」です。限られた時間の中で、文章と図表を読んで正誤を選択しなければならないため、間に合わなかったりケアレスミスしたりというケースが失点の要因となります。
ですので、この範囲は参考書などでの対策というよりも、模試や過去問を用いて時間慣れをしておく方がよいでしょう。
小説の勉強法
小説については、国語が苦手かつ時間がない受験生の場合は、対策する必要ありません。内容の難しさによって得点が大きく左右され、中途半端な対策では安定がしないからです。
また、日本語が話せるのであれば、対策なしでもとれる時は点数がとれます。ですので、理系受験生の場合は、より再現性の高い古文漢文に勉強時間をかけることをおすすめします。
偏差値60までの地理の勉強法
ここでは、偏差値60超えを目指すときに気をつけるべき地理の勉強法と参考書を紹介します。
偏差値60超えの地理の勉強法
参考書にさらっと目を通して最低限の基礎知識を覚える
共通テストの過去問を使って実践演習を行なう
共通テストの過去問の直しをしながら資料集や参考書で詳細を調べる
❸のステップが終わったら再びその過去問の回をすべて解き直す
解き直しでも間違えた苦手な問題をノートに貼り付けてストック
❷〜❺までのステップが終われば再び別の過去問で実践演習を行なう
共通テスト地理は、問題から与えられた情報と、最低限知っておくべき基礎知識をもとに、地理的な思考をしながら問題を解いていくテストです。つまり、経験量が重要な役割を果たします。
ただ知識を大量にインプットしたからといって、得点できるようになるわけではありません。
地理の勉強で重要なポイント
共通テストの地理では、実践こそが大切であると書いてきました。しかし、基礎知識がゼロでは意味がありません。では、どうすればよいのか。
そこでやってほしいのが、最初は参考書や教科書を1周分さらっと読んで、全体の流れや知識をざっくり頭に入れるという前準備です。
まずは参考書や教科書を使って地理の全体の流れをざっくりと頭に入れる
全体のイメージがついたら、次は実践演習に移ります。ここで重要なのが、共通テスト本番の過去問を使うというところです。
予備校の出している模擬問題集は、最初のとっかかりとしてはよいですが、回によっては本番よりも明らかに簡単なものがあります。また、出題される傾向なども異なることがあるため、共通テストの過去問を用いて、本番レベルで実践をしてください。
実践演習では過去問を使って、できるだけ共通テスト本番レベルで経験を積む
また、解き終わったらそこで終了ではなく、必ず時間をかけて答え直しをしましょう。その時にですが、知らない知識や勘違いしている知識が出てきたら、教科書や参考書を開いて該当箇所を調べてみましょう。地名などの場合は、地図帳を開いて場所を覚えておくとよいです。
答え直しがひと通り終われば、もう一度同じ過去問を解き直してください。
そして、それでもなお解けない問題があれば、その問題をコピーしてノートに貼り、定期的に復習できるようにすると自分だけの弱点問題集ができあがります。
実践演習が終わったら、失点原因の確認と調べ物に時間をかけて解き直しまでやり切る
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。