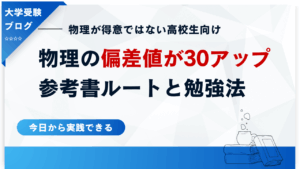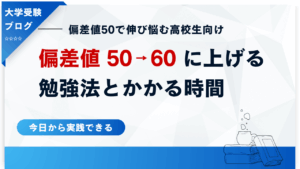【理系決定版】共通テスト地理|50点の人と90点の人の勉強法はここが違う!
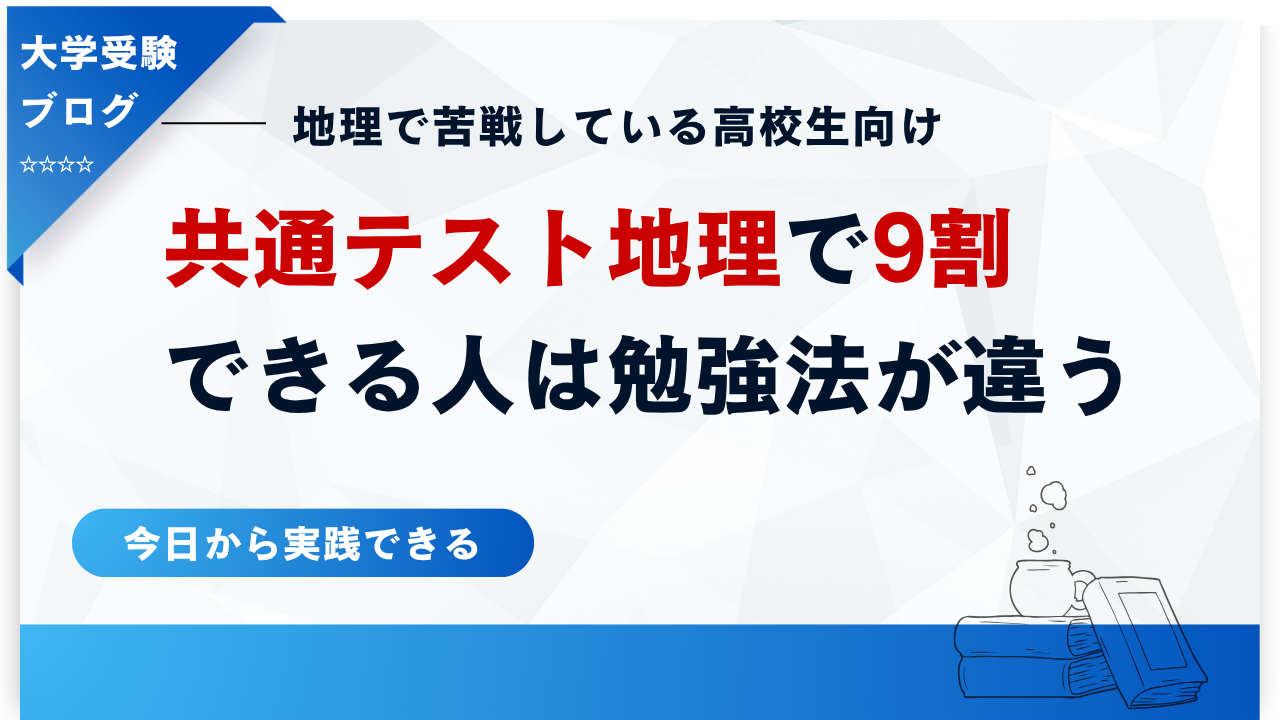
地理の点数が伸びない、いつから対策始めればいいんだろう…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

覚えるべきことは覚えたのに、地理の点数がぜんぜん安定しない…

そもそも理系って、地理の対策はいつから始めればいいんだろう…
受験生の頃、筆者は地理という科目が大好きでした。勉強を進めていても楽しいし、他の科目の息抜きにもなっていたので、地理の学習時間はワクワクしていました。
しかし、好きと得意は別です。マーク模試や本番では5割、自分で実施した模擬で、簡単な回の時にようやく8割に届くか届かないか。このような成績しか残せませんでした。
なんだよ、ぜんぜん克服できていないじゃん!
ほとんどの方はそう思われると思います。ですので、今回ご紹介するのは、筆者のように時間をかけても点数が伸びなかった人と、同じ時間で9割超えを安定させた人の勉強法の違いです。
✔︎ 共テ地理の勉強で後悔したこと
✔︎ 時間効率のいい地理の勉強法
✔︎ 共テ対策に使う地理の参考書
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
理系だからと地理を選択したら
反省ポイント
共通テスト地理に間違えた勉強方法で時間を費やしてしまい、最終的に50点台で幕を閉じた
これは筆者の体験談になるのですが、理系選択で受験をしていたため、「理系は地理」という空気感から疑いもなく地理を選択しました。
地理はそれなりに知識をインプットすれば、あとは一般常識と思考力で、ある程度の点数がとれると聞いていたからです。
ただ、心配性だった筆者は、仮に第一志望を変えた場合でも問題なく対処できるよう、地理の勉強にけっこうな時間を割いていました。覚える必要のある基礎知識の暗記は抜かりないまで繰り返し、資料や地図の読み取り対策にも時間をかけていました。
しかし、その勉強量とは相反して、なかなか点を取ることができず、結局のところ本番も50点台という結果で終わりました。この頃には、他の教科の成績がよかったため、勉強のやり方そのものには自信があったのですが、なぜか地理には通用しませんでした。
どうせ50点台しかとれないなら、勉強してもしなくても変わらなかったじゃん…
地理の自己採点が終わった直後、その感想しか出てこなかったことを今でも覚えています。
地理向きの受験生の特徴
共通テストの地理には、多少なりとも向き不向きの特徴があります。当てはまっている特徴によっては、地理よりも他の社会科目の方が適している可能性もあります。
地理に向いている受験生の特徴
✔︎ 地理という科目が好き
✔︎ 暗記よりも実践演習を好む性格
✔︎ 社会科目に時間をかけたくない
✔︎ 社会で高得点をとらなくていい
共通テスト地理は、高得点を狙うのに苦労する一方で、一般常識や資料読み取り問題も含まれているため、勉強をあまりしていない場合でも人によっては50点ほどとることができます。
一方で、日本史や世界史など暗記量に左右される科目は、勉強をしなければ点数をとることができません。このように、地理には点数が伸びにくい一方で、勉強しなくてもある程度とれるという特徴があります。
そのため、社会でそれほど高得点をとる必要がない受験生や、あまり時間を割きたくない理系受験生には向いている科目といえます。
また、地理は実践演習の成果が強くあらわれやすい科目です。真面目に参考書学習を重ねて知識を積み上げるタイプよりも、最低限の知識を持ちながら実践演習を重ねるタイプの方が向いています。
筆者の場合は、参考書学習に時間のほとんどを割き、実践演習にあまり時間をかけられなかったことが敗因でした。真面目な完璧主義タイプの人は特に要注意です。
地理に向いてない受験生の特徴
✔︎ 地理という科目が好きではない
✔︎ 参考書演習と暗記を好む性格
✔︎ 社会科目に時間をかけられる
✔︎ 社会で高得点をとる必要がある
前述の通り、地理は必ずしも努力量に比例して点数が伸びるとは限りません。勉強方法があっていなければ、努力をしても成長が見られないということも起こります。
もしも真面目で努力家な人や、社会に勉強時間を費やせる人は、地理よりも他の社会科目を選んだ方が点をとりやすいかもしれません。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
90点の人と50点の人の地理の勉強法
ここでは、50点から抜け出せなかった人の勉強法と、90点で安定していた人の勉強法を対比させながら紹介します。
50点を抜け出せない誤った勉強法
参考書を何度も反復して載っている知識を完璧に定着させる
予備校が出す予想問題集で実践演習を行なう
実践演習にて不正解だった問題の直しと暗記を実施
これは筆者がやっていた、本番で点数がとれなかった勉強法と使っていた参考書(最新年度版に差し替えています)です。一見すると良い勉強法に見えますが、共通テスト地理という観点では無駄の多い勉強法です。
これまでに繰り返している通り、実践演習にかける時間が減ってしまったからです。共通テスト地理では、いかに最低限の知識を素早くつけて、実践演習にてトライアンドエラーを繰り返すかが重要になります。
90点で安定する地理の勉強法
参考書にさらっと目を通して最低限の基礎知識を覚える
共通テストの過去問を使って実践演習を行なう
共通テストの過去問の直しをしながら資料集や参考書で詳細を調べる
❸のステップが終わったら再びその過去問の回をすべて解き直す
解き直しでも間違えた苦手な問題をノートに貼り付けてストック
❷〜❺までのステップが終われば再び別の過去問で実践演習を行なう
これは筆者の友人がやっていた勉強法と使っていた参考書です。地理の勉強時間が筆者より少なかったにも関わらず、40点ほども差が開いていました。
また、その友人は地理以外の成績は悪く、他の科目では勉強方法も確立しているわけではありませんでした。しかし、地理においてはこのような逆転現象が起きていたのです。
では、筆者と友人の勉強法では、具体的に何がどのように違っていたのか。その違いがなぜここまでの差を生んでしまったのか。
共通テスト地理で起きる失敗
共通テスト地理は、問題から与えられた情報と、最低限知っておくべき基礎知識をもとに、地理的な思考をしながら問題を解いていくテストです。つまり、経験量が重要な役割を果たします。
ただ知識を大量にインプットしたからといって、得点できるようになるわけではありません。ここを当時の筆者は勘違いして「社会は単なる暗記科目」という偏見を持ったまま勉強していたのです。
その結果が、時間をかけて50点しかとれなかった筆者と、限られた時間の中で90点を連発していた友人との差でした。
地理の勉強で重要なポイント
共通テストの地理では、実践こそが大切であると何度も書いてきました。しかし、基礎知識がゼロでは意味がありません。では、どうすればよいのか。
そこでやってほしいのが、最初は参考書や教科書を1周分さらっと読んで、全体の流れや知識をざっくり頭に入れるという前準備です。
まずは参考書や教科書を使って地理の全体の流れをざっくりと頭に入れる
全体のイメージがついたら、次は実践演習に移ります。ここで重要なのが、共通テスト本番の過去問を使うというところです。
予備校の出している模擬問題集は、最初のとっかかりとしてはよいですが、回によっては本番よりも明らかに簡単なものがあります。また、出題される傾向なども異なることがあるため、共通テストの過去問を用いて、本番レベルで実践をしてください。
実践演習では過去問を使って、できるだけ共通テスト本番レベルで経験を積む
また、解き終わったらそこで終了ではなく、必ず時間をかけて答え直しをしましょう。その時にですが、知らない知識や勘違いしている知識が出てきたら、教科書や参考書を開いて該当箇所を調べてみましょう。地名などの場合は、地図帳を開いて場所を覚えておくとよいです。
答え直しがひと通り終われば、もう一度同じ過去問を解き直してください。
そして、それでもなお解けない問題があれば、その問題をコピーしてノートに貼り、定期的に復習できるようにすると自分だけの弱点問題集ができあがります。
実践演習が終わったら、失点原因の確認と調べ物に時間をかけて解き直しまでやり切る
共通テスト地理の勉強時間
かかる目安時間
1日2時間 × 60日 = 120時間
地理は知識よりも実践経験が重要とは言われつつも、地理総合・地理探求の分量は非常に多いです。しかし、理系受験生の場合、それほど社会科目に時間を割けるわけではありません。
ですので、対策の時期としては、自学の時間をとる場合は夏休みと直前期の2ヶ月間が集中期です。しかし、この2ヶ月で十分に対策が間に合うかというと、十分ではありません。
そのため、地理に関しては、自学の時間を十分にとれないからこそ、学校の授業時間を大切にしましょう。学校の授業が有益な場合はしっかりと授業をうけ、有益でないと判断できる場合は、その時間を使って自分で地理の勉強を進めましょう。
❶ 学校の地理の授業時間を使う
❷ 夏休み中に基礎知識を入れる
❸ 直前期に実践演習を主に進める
では、筆者と同じ道はたどらないように、共通テスト地理で高得点が狙えるよう、学習を進めてみてください。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。