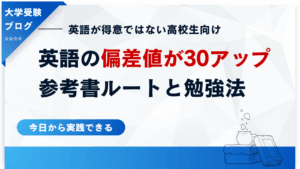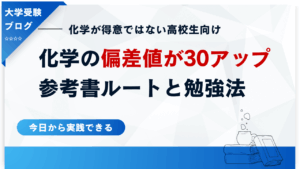【理系決定版】最短で共通テスト国語を7割以上にする勉強法
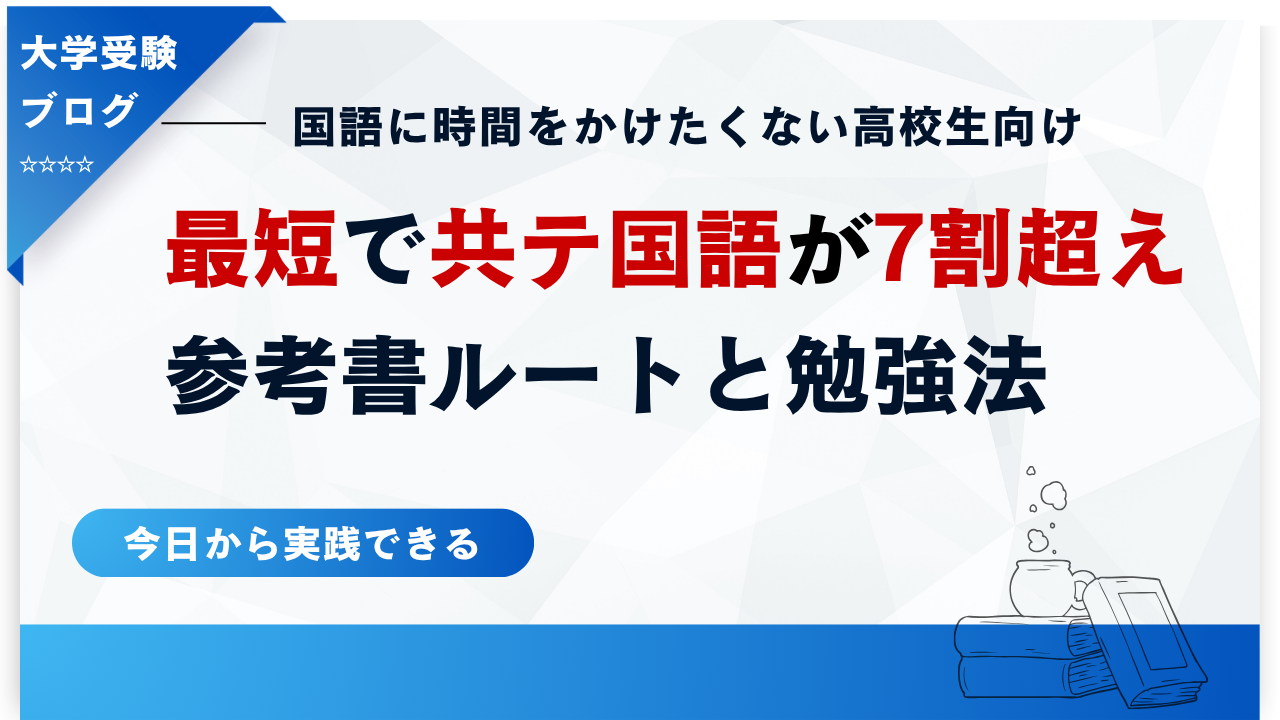
国語が嫌いで全然できない、いつから対策始めればいいんだろう…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

古文と漢文は全くできないし、現代文もぜんぜん点数が安定しない…

そもそも理系の場合って、国語の対策はいつから始めれば間に合うんだろう…
受験生の頃、筆者も国語という教科が大嫌いでした。マーク模試で200点中38点という結果を叩き出したことがあるほどです。
しかし、そんな筆者でも、最終的には7割をとれるようになりました。
なんだよ、たったの7割しかとれるようにならないのかよ!
ほとんどの方はそう思われると思います。ですので、あくまで今回ご紹介するのは、理系が時間をかけずに7割をとる勉強法となります。
✔︎ 共テ国語の勉強で後悔したこと
✔︎ 時間効率のいい国語の勉強法
✔︎ 共テ対策に使う国語の参考書
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
理系が国語を頑張った末路
反省ポイント
国語が苦手な人が8割超えを目指すと想像よりもはるかに時間がかかる
これはあくまで筆者の体験談になります。筆者が受験生の頃、国語で7割まではすぐにクリアをすることができました。比較的スムーズに進んだため、8割までもそう遠くなさそうだと感じ、国語の重要性は低かったものの、国語の対策に多くの時間を割きました。
しかし、模試の易化により点数がとれる時を除き、8割以上で安定することはありませんでした。そして案の定、受験本番でも7割は超えられましたが、8割には届きませんでした。
8割超えを目指して国語にかけてきた勉強時間は、理系受験生の中では決して少ないものではありませんでした。それゆえに、あの時間を他の学習に回していれば、という心残りも生まれました。
後悔した国語の勉強時間
最初は点数が伸びやすい
かつての筆者は、ネットで調べた情報をもとに、国語の勉強を進めていました。その結果、140点台まではすぐに伸ばすことができました。
それまで5割もとれない状態が続いたり、200点中38点という結果を叩き出したりしていたので、自分でも驚きました。
もっと頑張れば、もっと伸びるんじゃないか…?
マーク対策をそれほど頑張る必要がない大学(東京科学大学)を志望していたにも関わらず、国語の点数を伸ばしてみたい一心で、国語に時間をかけ続けました。
成績の頭打ちがやってくる
しかし、演習量を増やしても、読解の量を増やしても、そこから点数が上がることはありませんでした。最終的に国語にかけた時間は、本来予定していた時間の2倍。
そうです、7割まで上げるために使った時間と、8割まで上げるために試行錯誤した時間が同じくらいだったのです。その反面、残念ながら点数はほとんど上がることはありませんでした。
もしこれで受験に失敗していたら、おそらく筆者は国語に費やした時間のことをずっと悔やんでいたでしょう。では、なぜ勉強時間をかけても点数がなかなか伸びなかったのか。まだまだ勉強量が足りなかったからです。
理系が国語で苦戦する理由
国語で8割を安定させるためには、現代文の克服が欠かせません。しかし、現代文はすこし勉強したからといって、一朝一夕に伸びるものでもありません。文章を読む速さ、言葉の意味の知識、解き方のルール、文章理解力、いろんな能力が必要になります。
そして、これらの能力は付け焼き刃の暗記や理解では、なかなか補うことができないものでもあります。もちろん、時間をかけて一つひとつ達成していけば、国語が苦手な受験生でも点数をさらに上げられるでしょう。
しかし、理系受験生の場合、時間をかけられるといってもそこまで多くの勉強時間はとれません。そうなると、中途半端な状態で終わってしまうことになり、それが点数になかなか反映されない原因へとつながるのです。
理系受験生の国語の勉強量
前述のとおり、国語は中途半端な勉強になってしまうと、効果があまり見込めなくなってしまいます。
そのため、東大や京大のように二次で国語が必要な場合や、医学部のように共通テストボーダーが非常に高い場合以外は、必要以上に国語に時間をかけるメリットはありません。
メインである英数理で点をとりつつ、国語では7割台を確保して足を引っ張らないようにするという対策で十分です。
つまり、国語が苦手な理系がこれから力を入れるべきは、いかに早く国語で7割を安定させる力をつけるか、いかに残りの時間を必要な教科に費やすかという2点です。
国語で7割をとるための勉強時間
かかる目安時間
1日2.5時間 × 40日 = 100時間
2025年度の共通テストから、評論・小説・古文・漢文の4題形式ではなく、「実用的な文章」を含んだ5題形式に変わりました。
表やグラフの読みとりが主となる大問ですので、内容としては理系受験生が得意とする大問です。それも考慮して、以下のような勉強時間の配分が、共通テストの国語対策の目安になります。
| 対象 | 勉強時間 | 目標得点 |
|---|---|---|
| 古文 | 60時間 | 31点 |
| 漢文 | 20時間 | 42点 |
| 評論 | 15時間 | 27点 |
| 実用文 | 5時間 | 16点 |
| 小説 | 0時間 | 27点 |
共通テスト国語の学習時期
学習時期
✔︎ 夏休み中(目安 7月〜8月)
✔︎ 本番直前(目安 11月末〜1月)
もちろん、早めに対策できればそれがベストですが、国語に時間を割いている場合ではないという人もいるでしょう。
そのような場合は、国語の勉強は夏休みと共通テスト直前に集中的に取り組むのがおすすめです。夏休みは普段よりも勉強時間を多めにとれるので、国語にも手をまわすチャンス。
ただ、暗記要素が強い内容は期間を空けると忘れてしまいやすいので、理解要素が強い文法を中心に進めるのがおすすめです。
漢字や単語、構文などの暗記知識については、共通テスト直前期に一気にやり込むとよいでしょう。
共通テスト国語の学習順
学習順
❶ 古文(単語・文法・実践)
❷ 漢文(構文の暗記・実践)
❸ 評論(漢字・読解・実践)
❹ 実用文(実践)
❺ 小説(対策なしでもよい)
勉強順についてですが、理系受験生の場合「古文→漢文→評論→実用文→小説」の順で進めるのがおすすめです。
漢文は古文の単語や用法の知識を一部用いるので、この順番で対策をすると時間効率がよいです。ただし、時間がない受験生の場合は、漢文を最優先に勉強してください。
漢文は構文の丸暗記でもそれなりに点数をとることができるため、得点効率がよいからです。
評論・実用文・小説については、十分に対策する時間が割けない場合、評論→実用文の順に時間をかけましょう。
小説に関しては、しっかりと時間をかけて実力をつけない限り、運やその時の調子、問題の難しさにかなり左右されるので、あえて対策をしない選択肢もありです。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
国語で7割をとるための勉強法
ここからは、理系受験生のための共通テスト国語の勉強法について紹介します。
古文の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 文法(特に助動詞・敬語)を学ぶ
✔︎ 単語帳の単語をすべて覚える
✔︎ 実践を繰り返し弱点を埋める
古文単語の勉強法
古文単語315は、古文単語とその意味を載せているだけでなく、イメージしやすい絵と、その言葉になった語源も一緒に載せてくれています。
絵を見ながらイメージをわかせつつ、なぜその古文単語ができあがったかの理由と背景を読んで理解すれば、知識が長期的に定着しやすくなるので、非常におすすめの単語帳です。
ただし、すべてを学習すると分量が非常に多いので、まずは赤字の見出しのみ覚えるようにして、もし本番までに時間が残されていたら、黒字部分の意味を覚えるようにしましょう。
英単語と比べると分量は少ないため、夏休み(7月〜8月)に一気に時間をかけて覚えると、後でラクになります。
単語の覚え方
まずは古文単語とその意味(赤字)を声に出して反復しながら覚える。このやり方で見開き1ページ分を覚えたら、次のページへ移動して同様の作業を行なう。
その日の分量が終わったら、最後にその日覚えた古文単語を覚えているか通しで復習する。覚えていない単語があった場合は、その日の分量の最初からやり直して、通しでクリアするまで繰り返す。
その日の分量をクリアできたら、寝る前、あるいは次の日の朝に復習をする。
全体的にある程度覚えられたら、次は単語単体ではなく例文を使って覚えているか確認をする。例文での単語の使われ方も覚えられたら古文単語はOK。
古典文法の勉強法
富井の古典文法は、これまで学校の古典の授業をまともに受けていなかった人でも取り組めるような、話し言葉で書かれた非常にわかりやすい文法参考書です。古典文法の全体像を把握でき、共通テストで必要とされる文法は網羅されています。
ただし、問題演習が少ないため、知識のインプットとしては申し分ありませんが、これとは別にアウトプット用の参考書もしておくとベストです。
文法の学習手順
まず1周目は章の中に含まれている講を読み進めていき、書かれている内容を理解する。内容が理解できたら、参考書にそのまま書き込んでよいので、理解したことを自分の言葉でメモする。
1つの講が終わったら練習問題を解き、正答率が悪い場合は(目安は50%以下)、再びその講の説明を読み返して、理解し直してからもう一度解き直すこと。
2周目以降は、別冊を使って反復し、わからないところだけ本冊の内容を確認する。
富井の古典文法がある程度終われば、実際にどれほど身についているか、実践演習をしていきます。その時に用いるアウトプット用の参考書が、ステップアップノート30です。
実践演習の手順
まず1周目は問題を解き進めていって、自力で解ける問題と解けない問題を振り分ける。その際に、解説を読んでも理解できない箇所があれば、富井の古典文法で該当箇所を振り返り、理解し直すこと。
2周目以降は、1周目に解けなかった問題のみを解き進め、ある程度できるようになった段階で、一旦参考書の演習はOKとする。
古文の実践演習
ここでは駿台の実践問題集を紹介していますが、そこまで古文に力を入れるつもりがない人は、やや簡単な河合の総合問題集でも構いません。
ただし、昨年分の河合全統マーク模試をそのまま載せているので、浪人生の場合は問題が被ることがある点に注意が必要です。
漢文の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 構文を覚えて使えるようにする
✔︎ 過去問演習を何度も繰り返す
共通テストの漢文対策は、この参考書に載っている構文を覚えて使えるようにするだけで、かなり得点率が変わってきます。
それほど分量も多くなく、直前期で一気に追い込むこともできるので、時間がない理系受験生にはありがたい一冊です。もちろん、漢文の知識がまっさらな状態からでも問題なく取り組めるので、その点はご安心ください。
この参考書が仕上がったら、駿台の実践問題集や過去問などの共テ形式の実践を行ない、忘れている箇所のみピンポイントで復習すると、安定して高得点がとれるようになります。
評論の勉強法とおすすめ参考書
✔︎ 解き方の仕組みを理解する
✔︎ 根拠だけをもとに答える練習
✔︎ 過去に出された漢字を覚える
この参考書は、国語が苦手な理系受験生を助けてくれる、非常におすすめの一冊です。論理的な読み解き方を丁寧に説明してくれているため、現代文における解き方のルールをインプットすることができます。
また、根拠を徹底した参考書ですので、いつも現代文を解くときに書かれていない想像までして答えてしまうという人にも効果的です。
理屈で学習を進めたい人に向いている参考書ですので、理系で国語に困っている場合は、ぜひ取り組んでみてください。
評論の勉強方法
まずは自力で問題を解くが、このときにただ読んで答えるだけでなく、本文の構造がどうなっているか(逆説・純説・対立・修飾など)を書き込みながら、解き進めていく(書き込むのが嫌な場合はコピーする)。
解き終わったら解答解説を確認し、設問の答えがなぜそうなるのかを確認した後に、自分の解釈した文章全体の構造と、模範回答の文章全体の構造を照らし合わせる。
自分のものと模範解答が異なる場合は、なぜ違うのかを確認して理解する。これを毎回の題で繰り返し、根拠を持って答える意識を身につける。
評論の漢字対策は必須
評論での安定した得点源といえば漢字です。配点があまり大きくないので、時間をかけすぎるのは避けたいですが、いっさい対策をしないのももったいないです。
ですので、共通テストの漢字対策は、共通テストを用いて行なうようにしましょう。駿台の実践問題集のような、各塾が出している模擬問題集でもよいですし、実際の共通テスト過去問を用いても構いません。
国語の共テ形式を解いた際に、漢字のパートで間違えたものは、ノートや単語カードなどにまとめて、何度でも復習できるようにしておきましょう。
実用文・小説の勉強法
実用文の勉強法
実用文の範囲は図表の読み取り要素が強いため、どちらかというと理系選択の高校生には馴染みがあるかもしれません。
課題となるのは、内容というよりも「かけられる時間の短さ」です。限られた時間の中で、文章と図表を読んで正誤を選択しなければならないため、間に合わなかったりケアレスミスしたりというケースが失点の要因となります。
ですので、この範囲は参考書などでの対策というよりも、模試や過去問を用いて時間慣れをしておく方がよいでしょう。
小説の勉強法
小説については、国語が苦手かつ時間がない受験生の場合は、対策する必要ありません。内容の難しさによって得点が大きく左右され、中途半端な対策では安定がしないからです。
また、日本語が話せるのであれば、対策なしでもとれる時は点数がとれます。ですので、理系受験生の場合は、より再現性の高い古文漢文に勉強時間をかけることをおすすめします。
まずは古文漢文で80時間ほどの時間をかけられるように、学習スケジュールを調整してみてください。
共通テスト国語の時間配分
| 大問1 | 評論 | 25分 |
| 大問2 | 小説 | 20分 |
| 大問3 | 実用文 | 10分 |
| 大問4 | 古文 | 20分 |
| 大問5 | 漢文 | 15分 |
✔︎ 漢文
✔︎ 古文
✔︎ 実用文
✔︎ 評論 ※どちらが先でも可
✔︎ 小説 ※どちらが先でも可
理系受験生の場合、安定して高得点が狙いやすい順で解くのがおすすめです。
評論と小説に関しては、安定をしやすいのは評論ですが、高得点が出やすいのは小説です。こちらについては、自分の好きな方を先に解いて構いません。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。