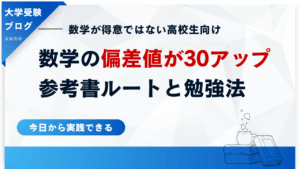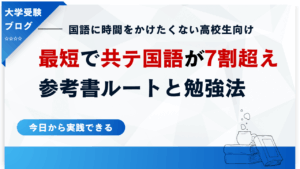【理系決定版】英語の偏差値を30上げる参考書ルートと勉強法
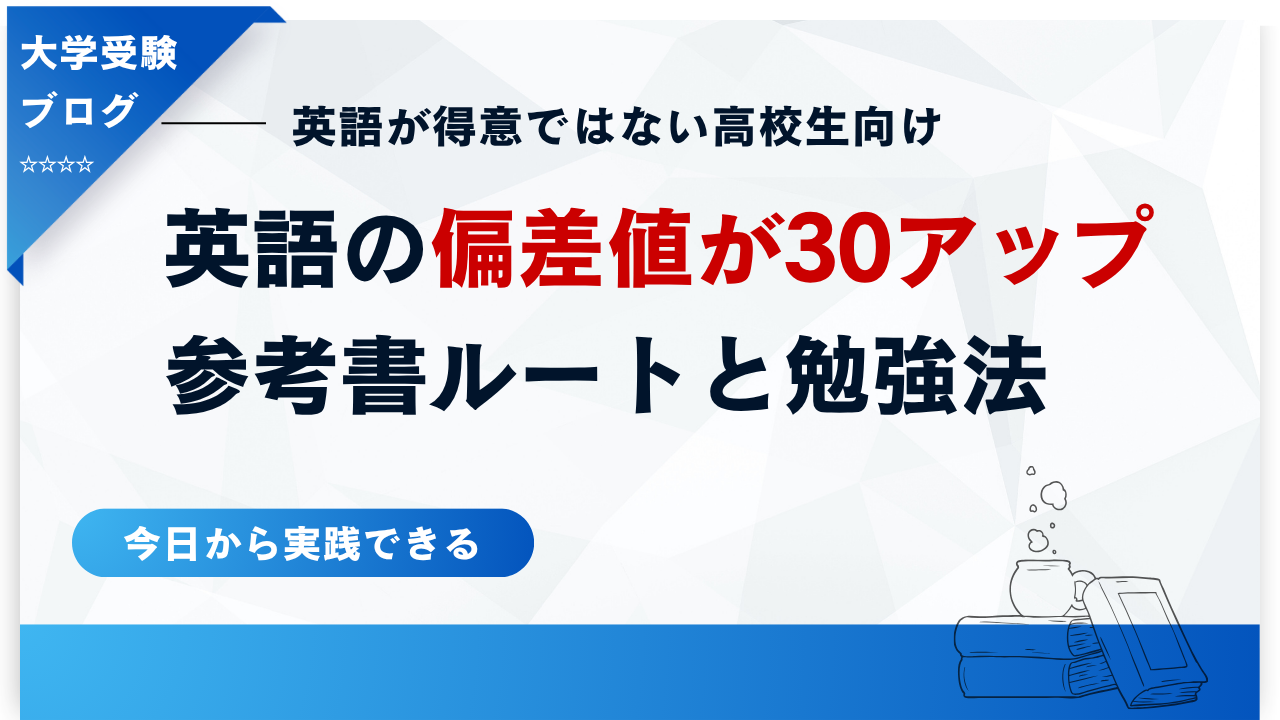
英語に苦手意識を持っている、まだ英語を得意にできていない…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

授業にもついていけないし、まず何から始めればいいのか分からない…

苦手意識はなくなったけど、まだ得意だと言えるほどは英語力が身についてない…
筆者もかつて、中学レベルの英語知識も入っていない状態から学習を始め、試行錯誤を重ねてようやく、英語を克服することができました。
どうせ英語が得意な人は、読解力もあって言語のセンスが元からいい人なんだ!
そう思い込んでいましたが、英語はそんな理不尽な教科ではありませんでした。
今回の記事では、偏差値別に必要な英語の勉強法を紹介します。
これから紹介する内容を実践できれば、今よりも英語の偏差値が大幅にあがっているはずです。
✔︎ 偏差値が上がる英語の勉強方法
✔︎ 偏差値別のおすすめ英語参考書
✔︎ 自分にあった英語長文の解き方
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
英語の偏差値が上がる学習手順
英語が苦手な人と英語が得意な人には、2つの大きな違いがあります。1つ目は自明ですが勉強量、そして2つ目は勉強する時の学習順です。
特に学習する順番を間違えると、勉強時間はかけているのになぜか成績が上がらない事態に陥ってしまいます。

いつも長文問題の選択肢で、2つに絞ったうちの間違った方を回答してしまう…
これも、英語の学習を曖昧な手順で進めてしまった時によく起きる現象のうちの一つです。努力が正しく成績に反映されるよう、これから紹介するステップをぜひ参考に、英語の学習を進めてみてください。
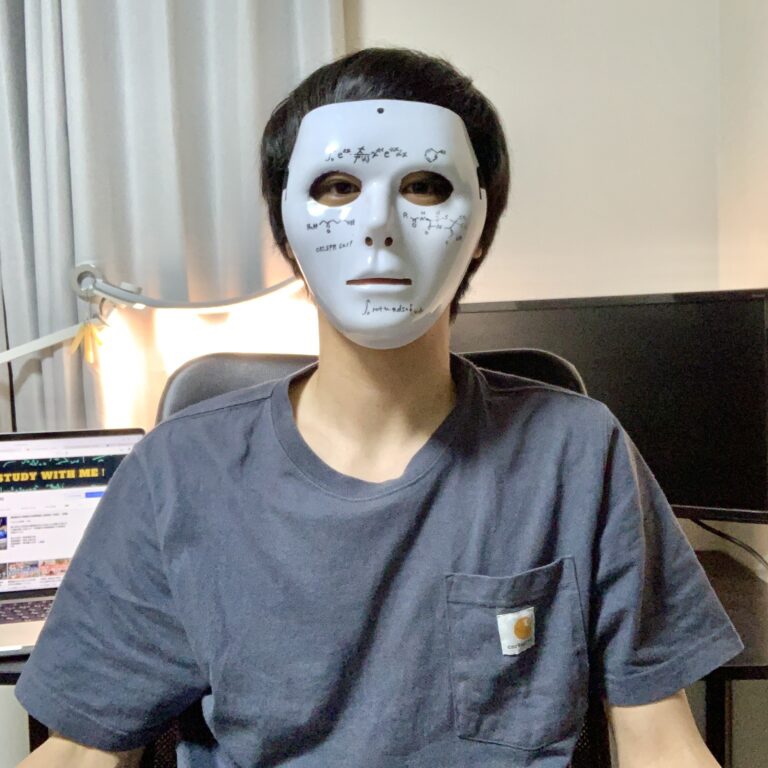
英語は学習順が本当に大切だから要注意!
まず、英語の勉強順は偏差値50未満と偏差値50以上とで異なります。
英語の偏差値50未満の勉強順
英語の場合、中学基礎レベルの英単語が身についていなければ、今後の学習すべての定着度が格段に落ちてしまいます。文法参考書の例文や解説内で出てくるような基本的な英単語は、なによりも最優先で身につけましょう。
早く長文に移りたいと焦る気持ちもあるかもしれませんが、基礎英文法の定着なくして長文が読めることはまずありません。英単語と英文法は、英語を読めるようにするための必須材料なので、英単語の暗記と並行して、中学〜高校基礎レベルの英文法を学習しましょう。
英文法を学ぶと、英語を正しく読むためのルールがわかるようになります。ここで初学者が最初にぶつかる課題が、文法の説明を読んで理解した内容を使いこなせるかどうか。
模試やテストになるとあいまいな訳になってしまうというのは、わかった気になっていることが原因です。そうならないために必要なのが「実際に使ってみる練習」です。
英文法の参考書を進めながら、学んだ英文法を使って、載っている例文を自力で英作文して再現してみましょう。
基本的な英文法が身についてくると、簡単な短い英文であれば自力で正しく訳せるようになります。この段階で次に必要になるのが、3〜5行程度のやや長い英文のかたまりを正しく訳す力(英文解釈力)です。
どこからどこまでが主語で、どこからどこまでが目的語で、副詞はどの節にかかっているかなど、英文の構造を論理的に読み解く練習をすることで、”時間さえかければ”長文も自力で問題なく読める状態になります。
上記の4ステップまでの学習が終われば、偏差値が50を超えてきます。しかし、英文が読めるようになったからといって、高得点がとれるかというとそういうわけではありません。
ここまでの4ステップでできるようにしたのは、時間さえかければ自力で英文を訳せるという段階までです。つまり、このままでは模試やテストの制限時間で解き終わらないという事態が発生します。
ここで次に重要になってくるのが「長文読解の練習」です。ここからは、偏差値50以上の勉強順へと移行します。
目安の勉強時間
偏差値30台から偏差値50に到達するまでは、勉強時間として400時間ほどかかる
英語の偏差値50以上の勉強順
偏差値50以上の場合、基本的な英単語や英文法、英文解釈力はそれなりに身についた状態となっています。しかし、安定して得点をするために必要な基礎が十分に固まっているかというと、そういうわけでもありません。
そのため、偏差値50以上の段階からは、長文読解の練習を進める中で、つど発見した英単語や英文法、構文知識の弱点を埋めていきます。
特に、長文の中で定期的に出てくるのに正しく使えなかった知識は、文法の参考書や英単語帳にてピンポイントで復習をするチャンスです。
❶のステップでは、長文問題を解いて、解答解説の確認、苦手のピンポイント復習までを行いました。では、長文1題を解き終わったらそれで終了かというと、そういうわけではありません。
その長文を時間をかけて全文訳し、そのレベルの文章を正しく訳す力が備わっているかどうかを確認してください。自力で訳せなかった文章は、どのように訳すのかを確認して、次にいかせるようにメモをしておきましょう。
❷のステップにて全文訳ができたら、次にやることは「付属の英語音声に合わせて音読」をするシャドーイング練習です。シャドーイングのやり方(タップで確認)は、この勉強ステップまとめの後で紹介します。
さて、❶〜❸にて長文1題の学習方法を紹介してきましたが、❶〜❸の流れを1日で終わらせようとすると、膨大な時間がかかります。
ですので、1日目は❶、2日目は❷、3日目は❸のように、1日ごとに分けて進めてみるとよいでしょう。
この段階まで学習が進むと、英単語熟語・英文法・構文知識・英文解釈力が身についているので、それなりに英作文(和文英訳)ができる状態になっています。ここから重要になってくるのは、入試本番で減点をされない英作文の仕方です。
日本語の例文をもとに紙に書いて英作文をし、模範解答と解説を確認して、模範解答で使われている表現を使いこなせるよう、書いたり音読したりと反復しながら、頭に入れていきましょう。
英作文の練習で短文の和文英訳ができるようになれば、あとは「自分が使いやすい表現を用いて」長い文章を書いていく練習になります。自由英作文の場合、長い英文を書くのが大変というのもありますが、どちらかというと次に2点が課題となります。
1つ目は、お題に対して「日本語で自分の意見を論理的に」書けるかどうか。2つ目は、自分で書いた日本語の文章を、いかに自分が英文を書きやすいように言い換えられるかどうか。これら2つの練習をしっかりと行えば、長い英文を書くことそのものは、あまり苦労しないでしょう。
上記で紹介した5ステップは、面倒くさくてつまらない作業です。それゆえに、やりたがらない人が多いので差がつきます。
英語の学習は、いかに日々の面倒くさいと向き合うかですので、上記の流れをルーティン化して、着実に成績を伸ばしていきましょう。
目安の勉強時間
偏差値51台から偏差値70に到達するまでは、勉強時間として1000時間ほどかかる
シャドーイングのやり方
シャドーイングはそれなりに大変なので、面倒くさくてやりたくないという人も少なくありません。しかし、シャドーイングは受験本番までの長い目で見ると、非常に時間効率がよい学習方法なのです。
✔︎ リスニング力が身につく
✔︎ 長文の速読力が格段に上がる
大変かもしれませんが、英語の点数アップに効率よく直結するので、ぜひ以下の手順でシャドーイングをしてみましょう。

とはいっても、シャドーイング用の音声って何を使えばいいんだろう…
使用する素材は、学習対象が長文読解の場合は、長文参考書に付属の音声、学習対象が英文解釈の場合は、英文解釈の参考書に付属の音声など、参考書に付属の英語音声を使うとよいでしょう。
- シャドーイング STEP1
- まずは英文全体を自力で正しく訳してください(長文読解の参考書を学習するケースなど、自力で正しく全文を訳す過程がすでに終わっている場合は、STEP1を飛ばして構いません)。
- シャドーイング STEP2
- 英語音声を再生して、自分的に聴きとれる限界まで反復しましょう。このとき、聴きとれた英語を紙に書くとベストですが、大変で続かなそうであれば、耳で聴くだけでも構いません。
- シャドーイング STEP3
- STEP2にて音が聴きとれ出したら、英文を見ながら、音声に合わせて音読をしましょう。音声の速度に合わせて、ある程度スラスラと音読できるようになったらクリアです。
- シャドーイング STEP4
- STEP3にて音声のスピードで音読ができるようになったら、次は英文を見ながら音読をしつつ、同時に「英語の意味」も脳内で訳すようにしましょう。最初は苦戦をしますが、何度も繰り返しているうちに英語のまま意味がわかるようになってきます。
- シャドーイング STEP5
- STEP4までの流れができれば、最後は何も見ずに、英語の音声のみを聴きながら、同時に音読をしていきます。このとき、STEP4でやった、音読と同時に「英語の意味」を脳内で訳すという動作も同時に行いましょう。音声に合わせて音読をしながら、ある程度英文の意味がとれるようになってきたら、その日のシャドーイング練習は終了です。
かかる目安の時間
STEP2〜STEP5までのシャドーイングが完了するまで、200~300語で40分~1時間程度かかる
英語のおすすめ参考書ルート
ここからは偏差値ごとに分けて、おすすめの参考書と勉強法について紹介します。
偏差値50未満向けの参考書
① 基本的な英単語熟語を覚える
① 基本的な英文法を身につける
② 基本的な英文解釈力をつける
英単語熟語と英文法は、同時に学習を進めましょう。英文法がある程度身につけば、次は基本的な英文解釈の練習です。
どの参考書でも共通ですが、1周した程度では知識は身につきません。定着するまで参考書を反復するようにしましょう。
ターゲット1200
英単語熟語帳であるターゲット1200は、中学レベルから受験基礎レベル(偏差値50~55程度)までの英単語と熟語が載っています。基本的な単語熟語から順に載っているので、前から順に覚えていくのがよいです。
ただし、熟語が覚えづらいということであれば、まずは英単語を中心に覚え、英単語が覚えられたら熟語を中心に覚えるというやり方をとってもよいでしょう。
もしも、heやdoなどの超基本的な単語の意味がわからない場合は、ターゲット1200ではなく1800を選んだ方がよいかもしれません(基本的にはターゲット1200でOK)。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
大岩のいちばんはじめの英文法
大岩の英文法は、中学から共通テストレベルまでの英文法を、英語の初学者でもわかりやすいように解説している、良質な参考書です。
一般的な教科書や参考書では、ページ内の隅に小さく載っているような補足事項は必要ない場合もあったりしますが、この参考書に載っている知識は、隅から隅まですべて受験で頻出の内容となっています。
中学高校と英語をサボってしまって、どこからやり直せばいいのだろうと迷っている人は、この1冊を極めることで英語を読むために必要な基礎英文法が身につきますので、確実に定着させられるよう反復するとよいでしょう。
文法の勉強方法
まずは単元の説明ページを読み進める際に、1ページごとに理解した内容を自分の言葉で要約して雑紙などに簡単にまとめる。説明途中に例文が載っている場合は、理解した後に自力で例文を英作文してみること。
単元終わりに載っているチェック問題は、最終的には自力ですべて解けるようにしてほしいが、超重要な問題しか掲載されていないので、チェック問題だけ反復して覚えても、英文法の基礎は固まらないことに注意しておく。
あくまでも、参考書全体の内容を理解して頭に入れるように、何度も反復して定着させること。
大岩の英文法の内容をしっかりと定着させられたかどうか、しっかりと把握したいということであれば、英文法ポラリス1での演習を挟むとよいでしょう。
肘井学の読解のための英文法
英語が苦手な人向けに、難しい英単語は使わないように構成された、英文解釈の参考書です。英単語と英文法の基本が身についた段階で取り組むと、詰まることなく学習を進めることができます。
ただし、比較的簡単な英文しか載っていないため、英語が苦手な人が最初に学習する英文解釈の参考書としてはよいですが、これだけでは模試やテストの得点にはつながりません。
入門英文解釈の技術70
英語が苦手な人が最初に取り組むには少し苦戦しますが、肘井の読解のための英文法を終わらせた後で取り組む参考書としては、入門英文解釈の技術70がおすすめです。
後半になるにつれて難しくなってくる、説明や表現が少しかたいという特徴がありますが、英文解釈の基礎を固めるには非常によい王道の参考書です。
英文解釈の勉強方法
まずは自力でSVを振りながら英文の構造を把握し、日本語訳を紙に書きましょう。このときに、変な日本語になってもよいので、英文法のルールに従って正しく正確に直訳するようにしてください。
直訳ができたらそこで初めて、直訳の日本語をもとに、意味が変わってしまわないように自然な日本語に書き換えましょう。ここまでができたら、解答解説の確認をします。
最後は、例文をシャドーイングしながら(付属の音声を使う)、返り読みをせずに前から順に(左から右に)訳します。これを数回ほど繰り返して前から順に意味をとれだしたら、次の例文へと移ります。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
偏差値50以上向けの参考書
✔︎ 本番まで英単語熟語を反復
✔︎ 英文法・英文解釈の弱点埋め
✔︎ 読める英文レベルを上げる
✔︎ 英文を読むスピードを上げる
偏差値50を超えてくると、基礎的な英単語熟語や英文法、英文解釈の知識はある程度身についた状態になります。ここからは長文演習を進めながら、見つかった弱点をピンポイントで復習していくとよいでしょう。
また、難関大学を志望する場合は、読める英文のレベルを上げるために難易度を上げた英文解釈を、難関私立の場合はレベルの高い英文法まで学習しなければなりません。
志望大学のレベルによってやることが変わってくるため、受ける大学の英語レベルはどの程度か、どのような形式で出題されるのか、一度過去問に目を通しておくとよいでしょう。
ターゲット1900
ターゲット1900は、受験基礎から早慶・旧帝大レベルまでの英単語を掲載している英単語帳です。東大や京大を志望する場合は、鉄壁を使用する人が多いですが、ターゲット1900で合格している受験生もいるので、大体の受験生はターゲット1900で完成します。
ターゲット1200を使用していた人は、1400を挟まずにそのまま1900へとつなぐことができるので、1200を使っていた人は1900でよいでしょう。
また、時間があれば1〜1900まで覚えた方がよいですが、中堅以下の大学を志望する場合は、1500までをしっかり定着させるのでも十分でしょう。
ターゲット1900の進め方ですが、①まずは見出し単語をひと通り覚える ②覚えられたら次に派生語も覚える ③全体的に覚えたら右ページの例文を用いて定着させる、というように段階を踏んで学習すると挫折しづらいです。
単語熟語の覚え方
1ページ内の英単語(英熟語)を1つずつ隠して日本語の意味を答え、答えられなかったら日本語の意味を確認して簡単に覚える。1ページ内の英単語(英熟語)の意味が通しで答えられるまでこれを繰り返し、できたら次のページへ移動する。
1語あたりの暗記に時間をかけすぎず、反復して覚えるという意識が大切。その日覚えた単語熟語は、その日の夜寝る前、あるいは次の日の起床後に復習すると、記憶が定着しやすい。
英熟語は長文演習の過程で覚えていくことで、ほとんどの場合は対策ができます。ただ、もしまとまった知識として覚えたい場合は、ターゲット1000か速読英熟語がおすすめです。また、ターゲット1000は分量が多いため、難熟語が集められたPart5はやらなくても構いません。
英文法ポラリス1
現在の受験英語では、特定の私立大学を受けない限り、単純な英文法としての問題が大量に出題されることが減りました。そのため、英文を読むために必要な文法知識を入れられたら、読解力を上げることに時間を費やす方がよいでしょう。
英文法ポラリスシリーズは、問題数があまり多くないため、時間がない中でも英文法の知識確認がしやすいです。ポラリス1レベルは読解に必要な内容ですので、十分に身についているかどうか、演習してみるとよいでしょう。
ただし、難関私立を目指す場合は、時間が残されているのであれば、Vintageのような網羅系演習を行なうと安心です。
文法の勉強方法
まずは自力で問題を解き進め、根拠も含めて正解できた問題と、間違えたあるいは根拠が曖昧だった問題を振り分けること。2周目以降は、1周目に根拠を含めて正解できた問題以外を集中的に反復していく。
ただ丸暗記をしても、文章の中で使えない知識となってしまうので、正解の根拠を説明できるようにすることが大切。
The Rules1・2
この参考書は、長文問題の読み進め方を丁寧に解説した、英文解釈と長文読解の合体版参考書です。偏差値50未満までの流れが完了したら、問題なく解き進めることができる内容ですので、長文読解を通して英文を読む練習を積み重ねましょう。
冒頭でも説明しましたが、ただ解くだけでなく、全文訳とシャドーイングも欠かさず行なう(タップで確認)ようにすると、非常に効果的です。ただ、英文の量が意外と多いので、音読が体力的にしんどい場合は、パラグラフごとに分けてシャドーイングをしても構いません。
基礎英文解釈の技術100
この参考書は、入門英文解釈の技術70の次にやるレベルの参考書です。基礎とついていますが、特に後半になるにつれて難しくなっていきます。この参考書に載っている英文が正しく解釈できるようになれば、難関大を目指さない限りは、十分な解釈力が身につきます。
The Rules1・2の学習と並行して、あるいはThe Rules1・2が終わった後に学習を進めるのがおすすめです。
英文解釈の勉強方法
まずは自力でSVを振りながら英文の構造を把握し、日本語訳を紙に書きましょう。このときに、変な日本語になってもよいので、英文法のルールに従って正しく正確に直訳するようにしてください。
直訳ができたらそこで初めて、直訳の日本語をもとに、意味が変わってしまわないように自然な日本語に書き換えましょう。ここまでができたら、解答解説の確認をします。
最後は、例文をシャドーイングしながら(付属の音声を使う)、返り読みをせずに前から順に(左から右に)訳します。これを数回ほど繰り返して前から順に意味をとれだしたら、次の例文へと移ります。
難関大志望でない場合は、ここまでの流れがしっかりと定着したら、志望大学の過去問を一度解いてみましょう。
難関向けの英語参考書(偏差値60〜)
読解力を引き上げる参考書
ポレポレは旧帝大の中でも上位校を目指す人以外は不要です。英文解釈の解像度がグッと上がる、昔から評判のよい定番の参考書ですが、非常に難易度が高く、特にライオンマークはハイレベルなので、中途半端な英語力で挑むと苦戦をします。
基礎英文解釈の技術100がしっかりと身についた状態であれば、問題なく読み進めることができます。
またThe Rules4も非常に難易度が高い英文が載っていますので、東大・京大・早慶レベル以外はThe Rules3までを仕上げて、過去問に移っても構いません。The Rules3においても、解いて終わりではなく、シャドーイング(タップで確認)を行なうようにするとよいでしょう。
英作文用の参考書(必要な人のみ)
ハイパートレーニングシリーズは、解説が丁寧でわかりやすいのが特徴です。分量的にも取り組みやすく、インプット用の例文も掲載されているので、残された期間で英作文の土台を叩き上げるのにもってこいです。
和文英訳編はしっかりと身につけられたら、ほとんどの大学で通用するので、何度も反復をして英文の型を身につけましょう。
自由英作文は、最初は書かなければならない英文の量に圧倒するかもしれません。ですので、書き上げるまでに必要な要素を分けて、段階的に書き上げていきましょう。
手順としては、まず日本語で回答をつくり、その日本語を自分が英語を書きやすいように言い換え、それから英訳するというようにステップを踏むと、取り組みやすくなります。
英作文の勉強方法
まずは自力で英作文をして紙に自分の回答を書き、終えたらペンの色を変えて、単語熟語帳や辞書などを用いて、書けなかった箇所を書き足していく。ここまでが終わったら、模範解答と解説を確認し、書き方を理解して学んだら、再び自力で解答を再現してみる。
これをできるまで繰り返し、再現ができるようになったら、次の例文に移る。英作文は理解で終わるだけでなく、使えるようにならないと意味がないため、移動時間などの暇な時間で例文集を反復するとベスト。
自由英作文の勉強方法
いきなり英文を書き始めずに、まずは日本語で「主張 → 理由 → 具体例 → 結論」の論理構成で自分の回答を作ってみる。その日本語をもとに、自分が英語を書きやすいように、日本語を言い換えてみる。
言い換えが完了したら、ここでようやく英語へと書き換えて、自由英作文を完成させる。英文が完成したら、模範解答と解説を確認し、自分の論理主張と何が違うか、どのような英語表現の使われ方がしているかを丁寧に分析する。
最後に再び、自力で英作文を行ない、次の問題へと移る。この流れにある程度慣れてきたら、日本語で回答を作る過程をなくしていき、いきなり英文で書けるように練習していくとよい。
自分に合う英語長文の解き方
長文読解は時間との勝負です。制限時間でいかに正確に回答をしていくかが求められるため、自分に合った解き方が必要になってきます。しかし、いろんな解き方が紹介される中、どれが自分に合っているかわからないという人も少なくないでしょう。
ここでは、代表的な解き方4つと、それぞれどのようなシーンの時に使え、どのような人に合っているかを紹介します。
解き方1 オーソドックス型
これはごく一般的な、本文を最初から最後まで丁寧に読み、全体の内容を頭に入れてから一気に設問に取りかかるという解き方です。どのような形式の問題でも使えるやり方で、内容も頭に入ってきやすいので、まどろっこしいテクニックよりも英語力で突破したいという人に向いています。
ただ、英語力がないと全体の主旨を把握できなかったり、速読力がないと内容を忘れてしまったり間に合わなかったりと、デメリットもあります。速読力および読解力に自信のある方は、このオーソドックス型のやり方で問題ないでしょう。
✔︎ テクニックの使い分けが嫌い
✔︎ 英語の読解力と速読力がある
✔︎ 毎回同じやり方で解きたい
解き方2 スキャニング型
これは先に設問を読んで、本文全体を読まずに設問の解答に関係しそうな箇所だけを拾い読みをするという、共通テストなどの内容一致の問題でよく使われるテクニックになります。
設問内のキーワードをもとに、本文で同じ英語が使われている箇所がないか、同じ意味だけど言い換えられた箇所がないかをざっと探し、該当箇所の英文のみじっくり読みこむというやり方です。
デメリットとしては、なかなかキーワードに対応する箇所が見つからなかった場合、時間ロスで焦りが生じてしまう点です。さらに、内容全体の正誤を問われる問題や、全体を要約する問題など、「全体の把握」が求められる問題の時には使い勝手が悪いという欠点もあります。
ただ、うまく使いこなせたら非常に時間短縮になるので、試験の残り時間が少ない時などには効果的なやり方です。
✔︎ 試験の残り時間が少ない時
✔︎ 何よりも効率最重視である
✔︎ 単語熟語などの語彙が豊富
解き方3 サーベイ型
これはオーソドックス型とスキャニング型のハイブリッドのようなやり方になります。まず本文全体をさらっと流し読みして、大まかな話の流れを頭に入れます。そのあと設問内容を確認して、先ほど頭に入れた流れのうち設問に関する箇所をピックアップして読み込むというやり方です。
オーソドックス型とスキャニング型の両方の良さを取り入れているので、早いかつ精度は高いですが、長文読解に慣れていないとなかなか実現できません。また、本文の英文レベルが高いと流し読みが厳しくなるため、自分の英語力以下の英文レベルの時に使えます。
✔︎ 英語の長文読解に慣れている
✔︎ 本文よりも自分の英語力が上
解き方4 パラグラフ型
これは一つひとつの段落の主旨を読み取っていくやり方になります。英文の各段落の基本構造は、「その段落の主張 →具体例と説明→まとめ」となっています。そのため、段落の冒頭付近には「その段落の主旨」が書かれていることが多く、段落の後半付近には「その段落の」結論が書かれていることが多いです。
この2つを中心に段落の要点を把握していき、段落ごとにメモをすることで、設問を読んだ時にどこをじっくり読み直せばいいかを瞬時に判断できるようになります。
また、段落の順序を問われる問題や要約問題でも、このパラグラフ型の解き方は効果を発揮します。英文の難易度が上がれば上がるほど、ざっと全体を流し読むというのが難しくなるので、このパラグラフごとに分けた主旨の把握が重要になってきます。
この解き方に難点があるとすれば、英語力だけでなく言語としての論理的思考力が問われるため、国語が苦手で大嫌いな人には向かない可能性があるという点です。
✔︎ 言語の論理構造に慣れている
✔︎ 英文自体の難易度が高い時
✔︎ 段落の整序や要約問題の時
以上、日頃の長文演習の時に試して、どのやり方が自分に合うかを見つけてみてください。やり方は必ずしも一つに絞る必要はありません。シーンによって使い分けられる場合は、使い分けも試してみてくださいね。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。