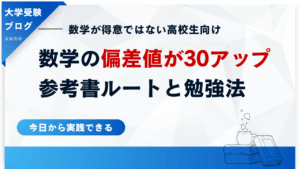【これが現実】偏差値39から独学で東京科学大学に合格した勉強法
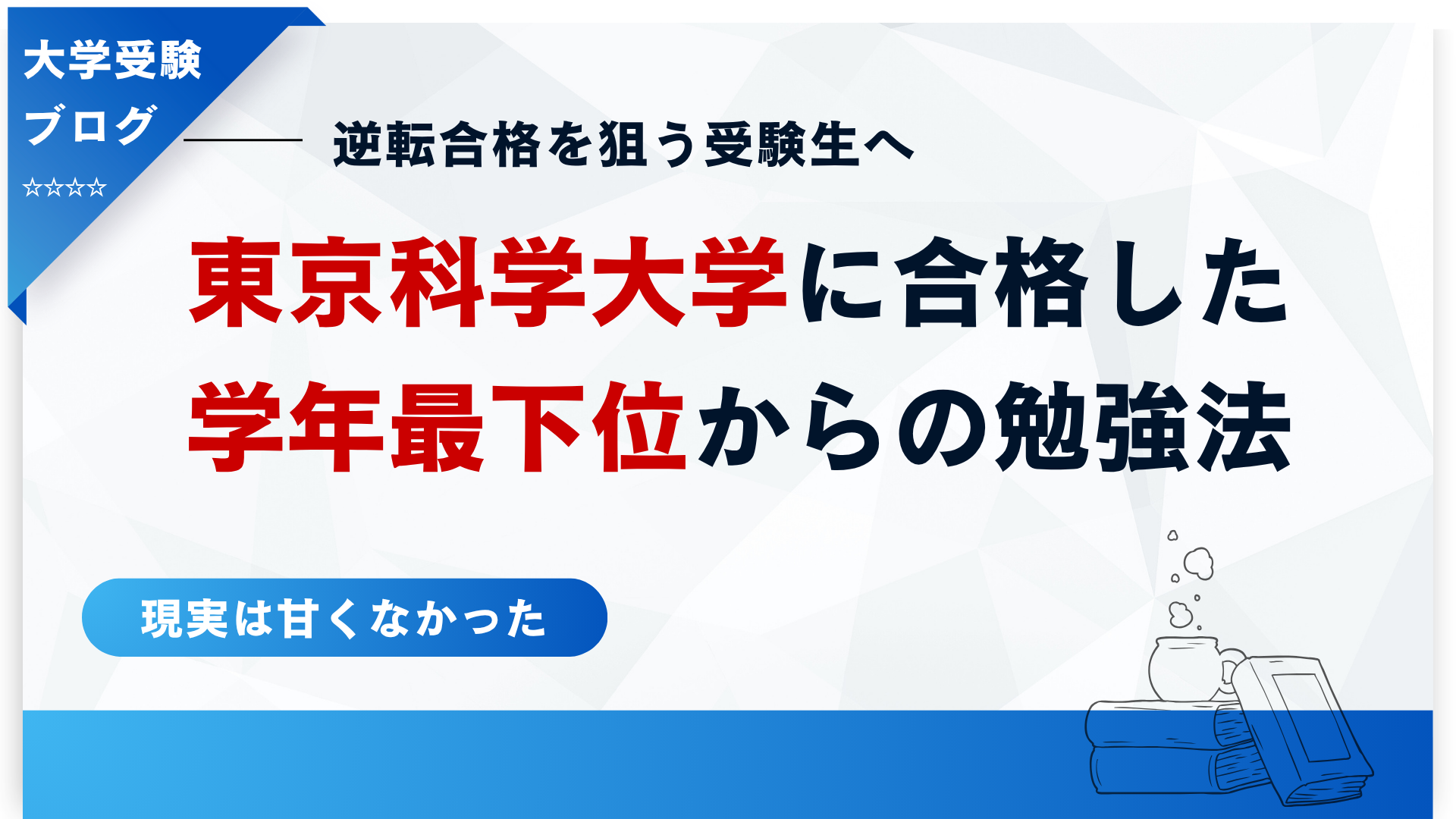
東京科学大学(旧 東京工業大学・略称 東工大)を志望しているけれど、今の成績のままでは厳しい…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

なにをどれくらい勉強すれば、合格ボーダーに届くんだろう…

毎日欠かさず勉強しているのに、まったく成績が上がらない…
筆者もかつて、受験知識がゼロの状態から受験を始め、手探りの状態で自分なりに勉強を進めていました。
たった1年で落ちこぼれから逆転合格、ドラゴン桜のような逆転劇は実現できる!
そう信じて机に向かっていたのですが、あっけなく不合格。受験はそう甘くありませんでした。
結果的には、1年間の浪人を経て東京科学大学(旧 東京工業大学・略称 東工大)に合格することができました。
しかし、その目標に辿り着くまでには、たくさんの失敗と反省がありました。
✔︎ 東科大合格までのリアル体験談
✔︎ 致命的な大失敗から学んだ教訓
✔︎ 合格に必要だった学習ステップ
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
受験を始める前の筆者の成績
大学受験のスタート地点は、みな平等ではありません。残酷なことに、よーいドンの時点で間に合わない人もいます。
それほどまでに、受験勉強を始める前の成績は今後の受験生活を大きく左右します。
筆者の場合、今がラクで楽しければいいという甘い考えで生きてきた結果、スタート時点で大幅に遅れをとってしまいました。
中学時代の筆者
| 学校の形態 | 中高一貫私立 |
| 学校偏差値 | 56 |
| 学年内順位 | 最下位 |
| 生活の態度 | 赤点補習すらサボる |
中学の頃の筆者は、教科関係なくほとんど全てのテストで赤点をとってしまい、毎週のように赤点補習を受けていました。
当時の状況
成績と学習態度に改善が見られなかった結果、中学3年時に教頭室に呼び出され、教頭・担任・親・筆者の四者面談にて自主退学を推奨される
高校時代の筆者
| 総合偏差値 | 39 |
| 勉強の姿勢 | 5分以上勉強できない |
| 英語の学力 | be動詞がわからない |
| 数学の学力 | 因数分解ができない |
| 理科の学力 | 中1レベルがわからない |
| 国語の学力 | 全く勉強していない |
| 社会の学力 | 全く勉強していない |
四者面談での反省もあり、高校への進学を許可されたものの、再び中学の頃のサボり癖が再発します。
その結果、いっさい勉強をしないまま、高校2年生の冬を迎えることになりました。
当時の状況
筆者は理系選択だったが、成績の悪い文系選択者よりも数学ができないなど、理数科目に苦手意識を持っていた
落ちこぼれ受験生からの脱却
このような落ちこぼれ状態から、どのようにして受験意欲を高め、2年足らずで東工大合格へとつなぐことができたのか。
そこには至って平凡な、しかし非常に重要な2つの仕掛けがありました。
1. 達成時のポジティブなイメージ
達成後のポジティブなイメージを持っているのといないのとでは、最初の一歩を踏み出すハードルが異なります。
例えば、普段と違うおしゃれな服を買いに行く時、緊張や不安を感じますよね。
しかし、購入後に自室でおしゃれをした自分の姿をイメージすると、一歩が踏み出しやすくなります。
達成後の姿のイメージは、勇気が出ない時や億劫な時に、背中を押してくれる材料になるわけです。
ただ、こう思う人もいるでしょう。

叶えたいポジティブなイメージなんてわからないんだけど…
叶えたいポジティブなイメージは「自分にとって」こうなるといいなと思えることであれば何でもかまいません。
筆者の場合、偏差値の高い大学に合格して、同級生から注目を浴びるというイメージが、前進の大きな源になりました。
第三者から見ればくだらないことであったとしても、本人が「こうなると嬉しいな」と感じていれば、ポジティブなイメージは効果を発揮します。
❶ 合格した後の自分の姿を想像する
❷ なりたい姿に近い他人を見つける
❸ 自分がその人になった妄想をする
❹ 実現のために今できることを考える
※ この段階で実現可能性は考えない
この「達成時のポジティブなイメージ」は、アメの役割を担います。しかし、アメがあるだけでは継続は叶いません。
2. 勉強を習慣化するきっかけ
成績の良し悪しの大部分は、トータルの勉強量に依存します。このトータルの勉強量を増やすためには、習慣化による継続が欠かせません。
では、勉強習慣が全くない状態から、どのようにして毎日の勉強を当たり前にしたのか。
筆者が行なったステップを以下で紹介します。
達成したい目標(例:志望大学への合格)を周りに知らせる
学校の休み時間など周りの目がある場所で勉強する姿を見せる(最初は形だけでもよい)
周りが本気度を疑わなくなるため逃げられない状況ができあがる
必ず達成できる最低限の量と理想の量の2つを立てて日々の計画を進める
前日達成できた量より少しずつでいいので毎日の目標量を増やしていく
2ヶ月ほど続けることで達成する習慣が身につく
この一連の流れが、筆者が勉強を習慣化するまでに行なったことでした。
このステップの中には、習慣化に重要な要素が4つあります。
✔︎ 目標を知っている人を周りにつくる
✔︎ 頑張る姿が人に見られる環境で勉強
✔︎ 今の自分に達成できる量から始める
✔︎ 量は一気にではなく少しずつ増やす
この「勉強を習慣化するきっかけ」は、ムチの役割を担います。アメとムチの両方がそろって初めて、成績を上げるための準備が整います。
偏差値を30伸ばした勉強計画
この章では、落ちこぼれ状態から2年足らずで偏差値を30伸ばした勉強計画について紹介します。
勉強開始から1ヶ月目
やったこと
イスに座って長時間好きなことをする練習で座る忍耐力を身につけた
受験勉強を始めたのは高校2年の冬でしたが、この頃まで長時間イスに座って勉強をした経験がありませんでした。
そこで、まずはイスに座ることに慣れるために、姿勢を正して座り、好きなことをすることから始めました。
冗談のような話ですが、このようなほんの小さな成功体験の積み重ねが、後の勉強習慣へとつながったのです。
2ヶ月目から5ヶ月目
やったこと
英語と数学に勉強時間を集中させて中学〜高校基礎レベルを身につけた
この2教科は早めに基礎固めをしておかないと、取り返しがつかなくなります。
やらなければならないことがたくさんあって焦る気持ちもあるかもしれませんが、できるだけこの2教科から固めていってください。
勉強する内容は、自分で弱点を把握しているならその範囲から、把握できていないようなら参考書1冊を最初から勉強し始めます。
筆者の場合、幸か不幸かいっさい基礎ができていなかったので、何の迷いもなく中学レベルからやり直しました。
✔︎ 中学〜高校基礎の英単語帳
✔︎ 中学レベルの英文法参考書
✔︎ 中学の英文解釈と和文英訳
英語には学習する順番があります。まずは基本的な英単語、これが身についていなければ英語の勉強が先に進まなくなります。
中学レベルの英単語に自信がない場合は、初学者用の英単語帳から始めるとよいでしょう。
基本的な英単語が頭に入れば、英文を読むためのルールブックである「英文法」の勉強が身につくようになります。
英文法を勉強する時に意識してほしいことが、説明を読むだけで終わるのではなく、簡単にでよいので例文を英作文する練習と音読をすること。
手に入れた武器は、使って慣れることで初めて使いこなせるようになります。
ここまでは、英語学習の超初学者がやる内容になります。
✔︎ 高校の網羅系参考書を使用
✔︎ 低難易度の基本例題のみ学習
数学に関しては、中学の内容からではなく、高校1年の内容(数IA)からやり直しました。
大学受験で必要な内容は、基本的に高校1年~3年の教材に集約されており、高校の教材でもカバーができるためです。
数学の学力に自信のない方は、高校の内容である数学IAから順に、初学者向けの簡単な参考書から始めるとよいでしょう。
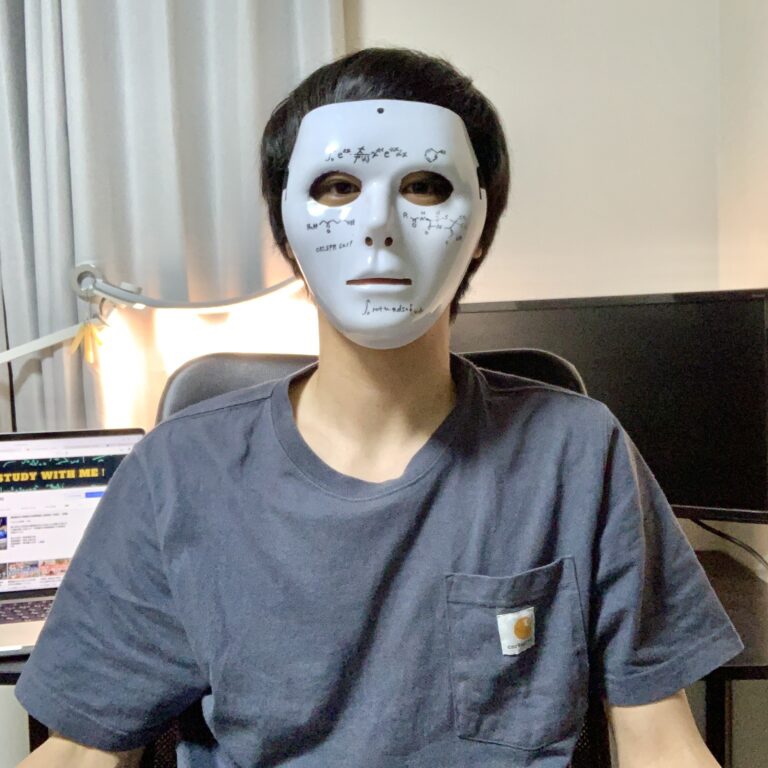
この時期の勉強時間の配分は英語45% 数学55%でした
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
6ヶ月目から8ヶ月目
やったこと
物理と化学に勉強時間を集中させて初学者〜受験基礎レベルを身につけた
最初の4ケ月で英語と数学の最低限の知識を身につけたため、この時期からは英語と数学を忘れないようにしつつ、物理と化学に注力しました。
まだ実力がないうちに全科目に勉強時間を分散すると、1科目あたりの勉強時間が減ります。
基礎というのは木の芽のようなもので、成長するまでは手をかけてあげなければ、すぐに枯れてしまいます。
基礎が身についていない時期は、決めた科目を一気に進めていくやり方がおすすめです。
✔︎ 初学者向けの参考書を使用
✔︎ 単元理解 → 例題演習を反復
理系の場合は、物理と化学を選択している人が多いでしょう。
この2科目は目に見えない現象を扱うことから、原理を理解するのに苦労するため、自分にとって理解しやすい参考書を使うのがおすすめです。
できるだけ簡単で初学者にとって読みやすい参考書から始めると、勉強が捗りやすくなるでしょう。
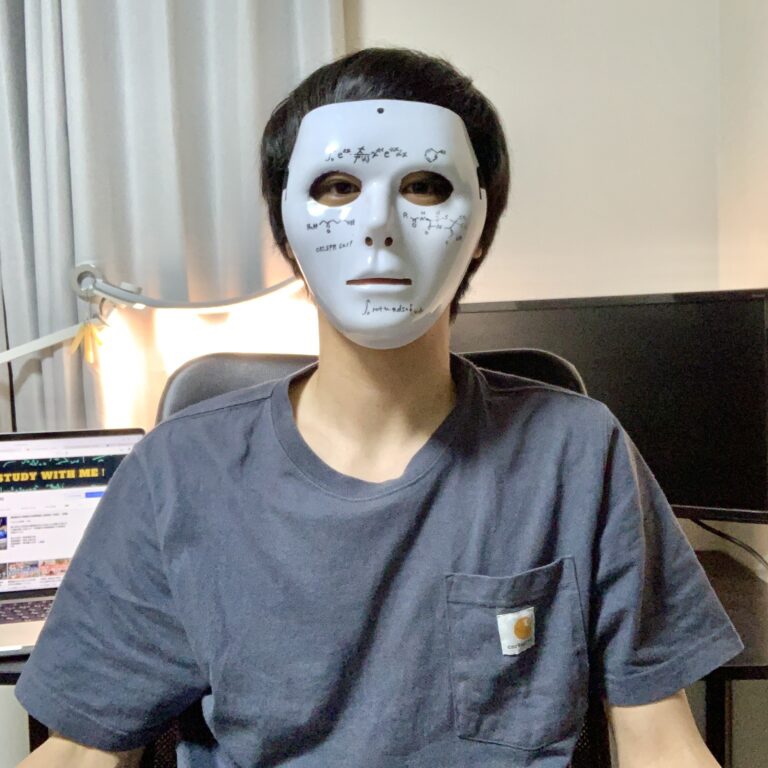
この時期の勉強時間の配分は英語10% 数学10% 物理40% 化学40%でした
9ヶ月目から11ヶ月目
やったこと
英語・数学・物理・化学に満遍なく勉強時間を配分して標準〜応用レベルの学習を進める
この時期には、4科目ともに基礎の学習をひと通り終えていました。
しかし、この「ひと通り終えた」という感覚が、筆者の受験人生における最大の過ちだったのです。
この頃から、残された時間も少ないため、二次向けの対策をし始めます。
基礎の参考書は反復したし、早く標準と応用に進まないと…
時間のなさから来る焦りから、とにかく先に進めることしか意識していませんでした。
その結果、筆者は2つの重要な過程を飛ばすことになったのです。
✔︎ 模試の苦手分析と解き直し
✔︎ ”わかった気”の発見と解消
やらなければならない演習の多さと、面倒くさいという気持ちから、模試の復習をおろそかにしていました。
間違えた問題の確認と、なぜ間違えたかの簡単な把握だけで終わっていたのです。
こんな簡単な問題、なんで間違えたんだろう。解答を見たらわかるし、さらっと解き直すだけでいいか…。
その場限りの振り返りで終わり、次へ次へと焦った結果、基礎を身についた気・理解した気のまま放置することになりました。
そうです、基礎はまだ十分に固まっていなかったのです。
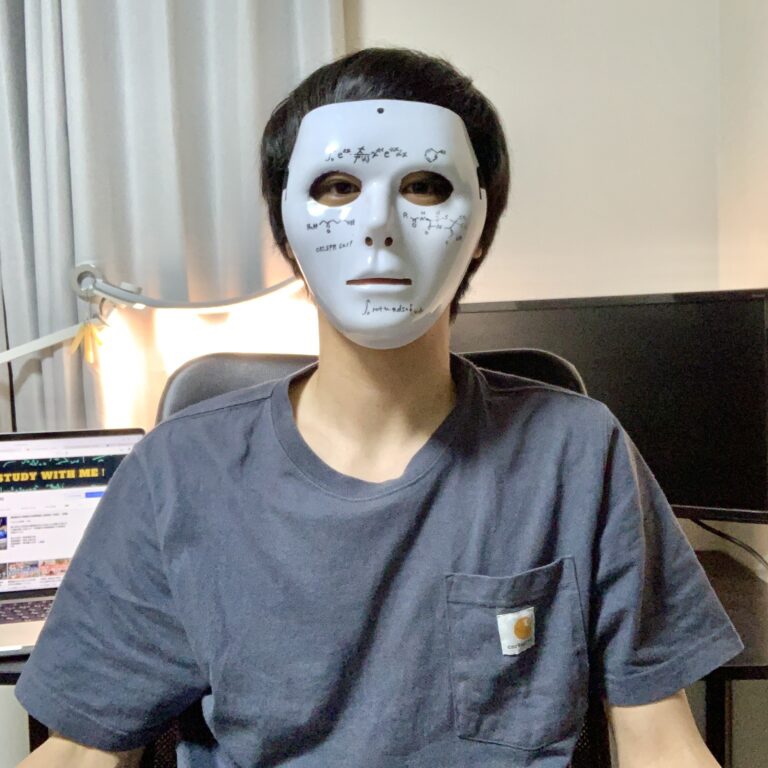
この時期の勉強時間の配分は英語25% 数学35% 物理20% 化学20%でした
12ヶ月目から13ヶ月目
やったこと
共通テスト(当時はセンター試験)対策で国語や地理などのサブ科目の勉強を開始した
この時期には、マーク形式の英数理で7〜8割、問題が簡単な回では9割を超える科目も出てきます。
第一志望は二次の得点のみで合否が決まりますが、他の大学に変える可能性も考慮して、国語や地理などのサブ科目にも時間を分配しました。
あくまで二次に必要な英数理で点をとりつつ、国語と地理はできるだけ足を引っ張らないように最短で身につけるという方針です。
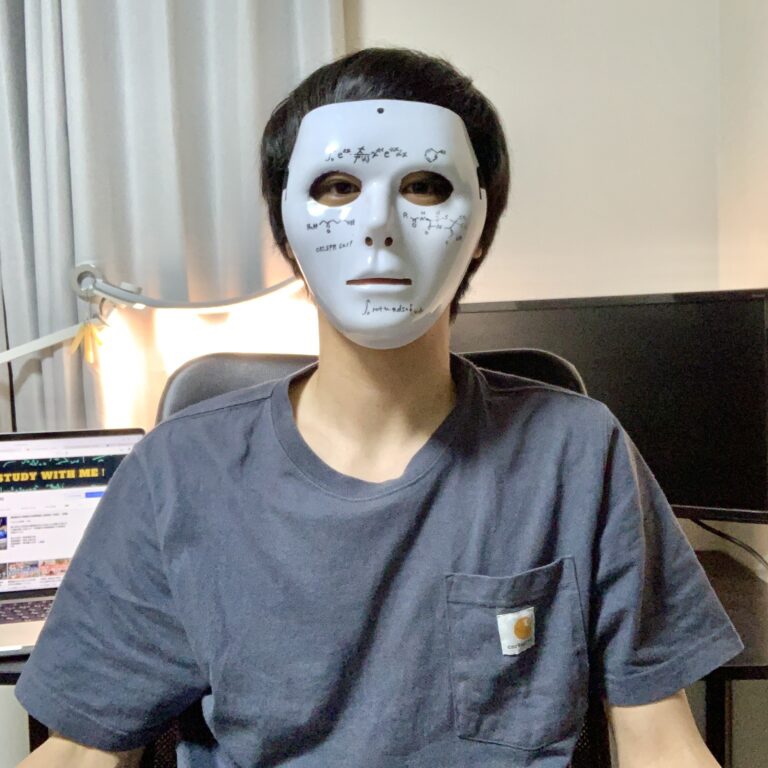
この時期の勉強時間の配分は英語20% 数学20% 物理10% 化学10% 国語20% 地理20%でした
13ヶ月目から14ヶ月目
やったこと
頻出の応用パターンを参考書にて学習しつつ過去問の特徴を把握する
本番直前期になり、二次対策を中心に進めることになります。
しかし、まだ参考書での演習が十分に進んでいなかったため、過去問演習ではなく応用の頻出パターンに時間を割いていました。
参考書演習は、本来11月までに終わらせているのがベストですが、筆者の場合は間に合いませんでした。
そのため、残された少ない時間でできることに、過去問対策の時間を集中させました。
✔︎ よく出る単元の傾向を確認
✔︎ 時間配分と出題形式の確認
✔︎ 合否を分ける難易度を把握
✔︎ 解説から頻出の解法を確認
時間がある人の場合は、できる限り多くの年数分(少なくとも5年分)を実際に解くことで、傾向を把握するのがよいでしょう。
しかし、過去問対策に時間をかけられない場合、中途半端な使い方をするのは勿体無い。
そのような場合は、分析に時間をかける選択肢もあることを、最終手段として頭の片隅に入れておいてください。
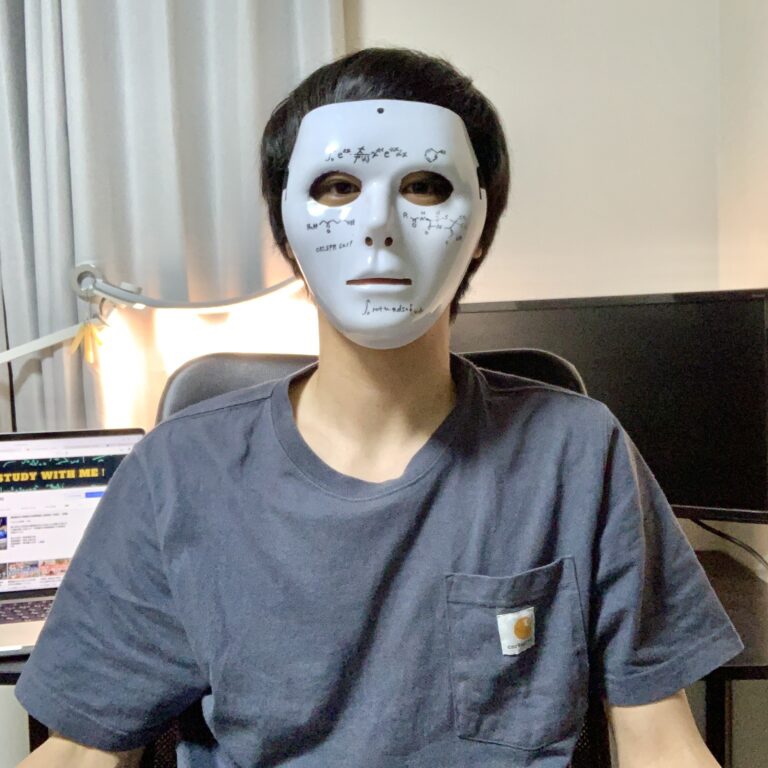
この時期の勉強時間の配分は英語20% 数学40% 物理20% 化学20%でした
現役時の入試結果
センター試験(共通テスト)
| 総得点 | 675点 / 950点 |
私立と後期試験
| 東京理科大 | 不合格 |
| 東京農工大 | 不合格 |
東工大本試験
| 総得点 | 120点 / 750点 |
| 英語 | 50点 / 150点 |
| 数学 | 30点 / 300点 |
| 物理 | 20点 / 150点 |
| 化学 | 20点 / 150点 |
入試本番を迎えた結果、地理と国語の得点率が5割とかなり低く、英数理もそれを補えるほど点数をとることができませんでした。
二次で使わない科目とはいえ、地理と国語でもある程度点をとることの重要性を痛感した瞬間です。
二次試験に関しては、当時の筆者が思っていたよりもはるかに壁が高く、正直受験を舐めていたと落ちて初めて実感しました。
✔︎ 模試の復習と分析を軽視した
✔︎ ”わかった気”で基礎を済ませた
✔︎ 圧倒的に勉強量が足りなかった
浪人時の入試結果
浪人生活では、現役時の反省点と向き合うことを大切に、受験勉強を進めていました。
結果として、1年間の浪人生活を経て、無事に第一志望である東工大に合格をすることができました。
センター試験(共通テスト)
| 総得点 | 798点 / 950点 |
私立大学
| 早稲田・東京理科大 | 合格 |
| 同志社・立命館・青学 | 合格 |
東工大本試験
| 総得点 | 400点 / 750点 |
| 英語 | 100点 / 150点 |
| 数学 | 110点 / 300点 |
| 物理 | 90点 / 150点 |
| 化学 | 100点 / 150点 |
浪人時代で主に行なったことは、徹底的に基礎を固める、各教科で苦手単元をなくすという、何ともつまらない作業の繰り返しです。
ただ、この何気ない積み重ねが、学力の安定につながりました。
難関大学を受けるということで、どこか疎かにしていた基礎。これが、合否を分ける大きな要素だったのです。
難問は基礎の組み合わせで構成されています。そして、手がつけられない難問は、ライバルも同じく苦戦します。
合格ボーダー付近の問題を確実にとりきり、難問でいかに部分点をもらうか。
それを実現するためには、基礎を疎かにしてはいけなかったのです。
大学受験で全落ちを経験したことで、この過ちがどれほど重大だったかを学びました。
✔︎ 基礎なくして応用は身につかない
✔︎ 焦って先に進むより目の前の基礎
✔︎ 難関だからこそ基礎理解を大切に
受験生に伝えたいこと
難関大を受ける場合でも、重要になるのは基礎の徹底です。筆者だけでなく、基礎でなく受験生を多く見てきました。
逆にいえば、それだけ基礎と理解に時間を費やせる受験生も多くないということ。
もし今が落ちこぼれだったとしても、ぜひ自分の夢に全力で挑んでみてください。結果がどうであれ、今後の人生の糧になるはずです。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。