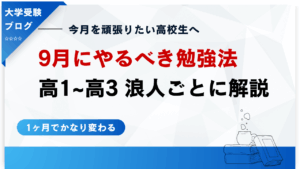【2025年最新】10時間勉強が実現する休日の勉強ルーティンを徹底紹介
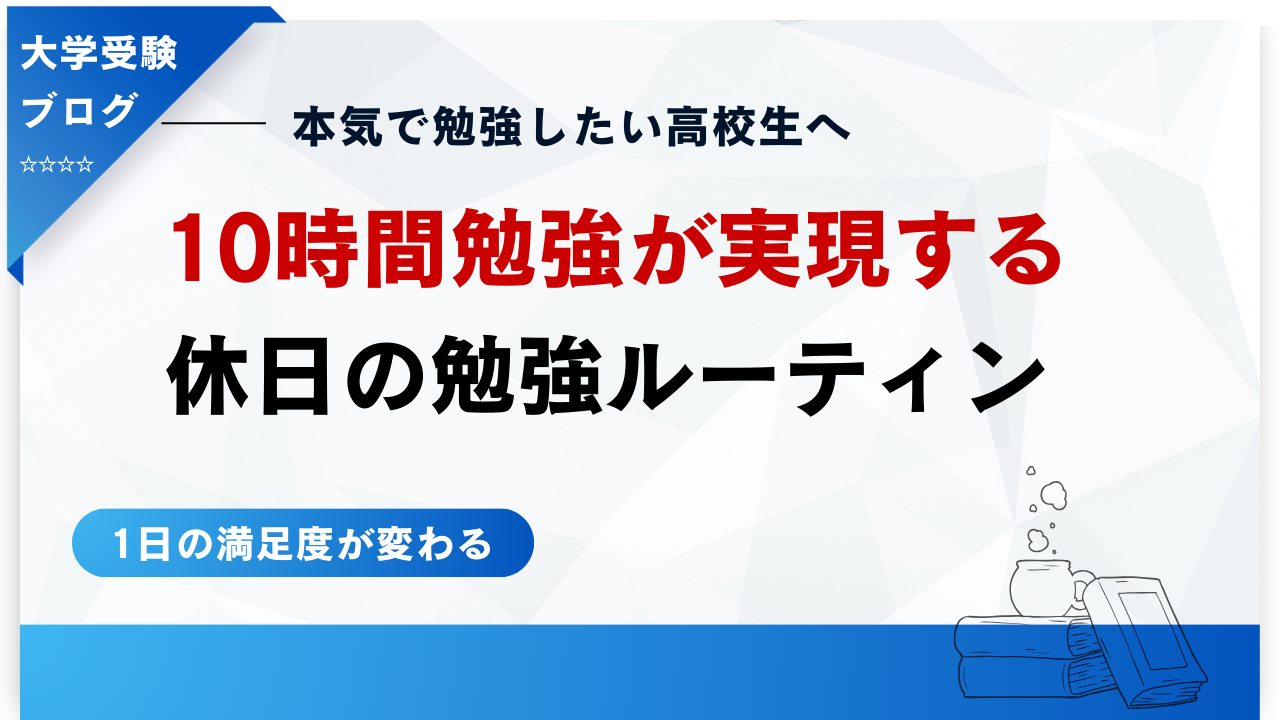
1日10時間勉強できるようになれば、今よりもっと成績が上がるのかな…”そんなふうに思ったことはありませんか?

まだ勉強習慣ができてないけど、受かるために10時間勉強しなきゃ…

今よりもっと勉強量を増やして、もっと早く成績を伸ばしたい…
1日10時間の勉強は、多くの受験生が目標とする勉強量です。ですが、その10時間を目標にする際には、ひとつ注意しなければならない点があります。
勉強を始めて10時間が経ったから、今日の目標はこれで達成!
本来の10時間勉強とは、勉強した結果として得られる勉強量を指します。単なる経過時間ではなく、10時間相当の勉強量を目標にすることを忘れないようにしましょう。
✔︎ 10時間勉強を習慣化するステップ
✔︎ 10時間勉強に必要な勉強計画術
✔︎ 10時間勉強を実現するルーティン
不安を放置したらダメ!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
10時間勉強に適した勉強環境
1日10時間の勉強は、難関大合格者にとっても厳しい勉強量です。努力が得意な人であっても、環境が合っていなければ、どれほど熱量が高くても実現は困難なのが現状です。
目標達成の可能性を高められる環境に身を置いて勉強すること
いまの勉強環境で、高いモチベーションや厳しいルールに頼らなければ勉強が続けられないのであれば、それは自分に合っていない環境だということです。
自分に合っている勉強環境とは
判断ポイント
怠惰な心を無理に律したり、嫌々努力している感覚を持つことなく、その場に身を置き、邪魔になる障害さえ取り除けば、自然と淡々と勉強を進められる環境であるかどうか
たとえば、学校の学習室や塾の自習室、図書館では無理なく勉強できるのに、自分の部屋ではテスト直前のような緊迫した状況でないと勉強が進まない、というケースはわかりやすい例です。
この場合、自分に合った環境とは「緊迫感がある」「誰かに行動や成果を見られる」といった環境だと言えます。
では、自分に合った環境づくりを、以下の手順に沿って完成させましょう。
集中できた勉強環境を振り返る
具体的にやること
これまでの人生を振り返り、比較的集中できた勉強場所1つと、集中ができなかった勉強場所1つを思い出し、その違いを比較する
中学受験や高校受験、定期テスト直前など、これまでを振り返り、比較的集中して勉強できた場所とできなかった場所を挙げましょう。
勉強場所の例
✔︎ 塾の自習室
✔︎ 学校の学習室
✔︎ 図書館
✔︎ 公民館
✔︎ カフェ・ファミレス
✔︎ 自宅
適した勉強環境を見つけるコツ
それぞれの勉強場所を思い出したら、次は両者の違いを把握する段階です。以下の項目に沿って、一つひとつ確認しましょう。
チェック項目
項目1:緊迫した雰囲気 (有・無)
項目2:他者の存在 (有・無)
項目3:行動の自由度 (低・高)
項目4:空間の静けさ (静・騒)
項目5:スマホ環境 (無・有)
項目6:勉強以外の誘惑 (無・有)
項目7:時間的な制約 (有・無)
| 勉強場所 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塾の自習室 | 有 | 有 | 低 | 静 | 無 | 無 | 有 |
| 学校の学習室 | 有 | 有 | 低 | 静 | 無 | 無 | 有 |
| 図書館 | 有 | 有 | 低 | 静 | 微有 | 微有 | 有 |
| 公民館 | 微有 | 有 | 低 | 微騒 | 微有 | 微有 | 有 |
| カフェなど | 無 | 有 | 低 | 騒 | 微有 | 微有 | 有 |
| 自宅 | 無 | 無 | 高 | 微騒 | 有 | 有 | 無 |
チェック項目で答えた内容のうち、上記の表と一致する項目が多い勉強場所がどこなのかを確認してください。多くの場合、塾の自習室や学校の学習室、図書館が該当するでしょう。
さて、場所の想定までできたとしても、それだけでは10時間勉強を実現する環境はまだ整っていません。次に取り組むべきことが、以下の手順です。
集中に差があった要素を特定する
具体的にやること
比較的集中できた勉強場所において、過去に集中できたときと集中できなかったときとで、どのような違いがあったのかを振り返る
先ほど挙げた勉強場所(過去に集中できた勉強場所)を思い出すと、程度の差はあっても、集中できたときとできなかったときがあるはずです。その際の違いを、思いつく限り挙げてみましょう。
よくある違いの例
✔︎ スマホの有無
✔︎ 周囲の騒がしさ
✔︎ 周囲の人数の多さ
✔︎ 眠気の有無
✔︎ 空腹の有無
✔︎ 勉強の不明箇所の有無
集中できたときとできなかったときの差が「周囲の騒がしさ」や「周囲の人数の多さ」以外の要素であれば、自分の行動ルーティンを変えることで調整できます。この点については、後述の勉強をルーティン化する手順(タップで移動可)で解説します。
一方、「周囲の騒がしさ」や「周囲の人数の多さ」は自分では制御できないため、勉強場所そのものを変える必要があります。
自宅や学校から1時間圏内(タップで移動可)で、集中しやすい環境を探してみましょう。
勉強をルーティン化するコツ
Step1 勉強開始までの行動を決める
Step2 行動の阻害となるものを排除
毎日欠かさず一定量の勉強をこなし、満足のいく1日を終えるためには、以上の2つの手順が不可欠です。
勉強開始までの行動を決める
10時間勉強を実現するには、二度寝やスマホ閲覧、勉強を始めるまでのダラダラ時間など、1日の中の無駄を極力減らす必要があります。
これらを抑えることができれば、勉強場所さえ確保していれば、10時間勉強はそれほど難易度が高いものではありません。
まずは以下の質問に沿って、勉強開始までの一連のルールを決めてください。
Step1 タイムスケジュールを決める
7つの決めごと
① 勉強場所のOpenとClose時間は
② 家から勉強場所までの時間は
③ 外出までにかかる準備時間は
④ 休日の起床時間は
⑤ 昼食にかかる時間は
⑥ 就寝準備にかかる時間は
⑦ 就寝する時間は
⑧ 家で勉強する必要がある時間は
①は、10時間勉強に適した勉強環境(タップで移動可)として選んだ施設のホームページを調べれば、すぐに確認できるはずです。
②は電車や自転車など、その場所に行くまでの移動時間のことを指します。③〜⑦については、自分の普段の時間の使い方を想定してください。
①〜⑦に答えることで、10時間を目標とする際の「⑧ 家で勉強する必要がある時間」がわかるので、⑧が決まったら以下の注意点に反しないように、①〜⑧の時間を再度調整しましょう。
もしも一番集中できる勉強場所が自宅でない場合は、「⑧ 家で勉強する必要がある時間」は1.5時間を超えないようにすること
Step2 行動のルールを決める
5つの決めごと
① 朝どうやって起きるか
② 立ち上がるまでの行動は
③ 洗面所でまずやることは
④ 朝食前にやることは
⑤ 朝食後にやることは
休日に10時間勉強できない人の多くは、朝起きられず(①)勉強場所に行けない、あるいは到着が遅れて目標量をこなせないことが原因です。
目覚ましだけで起きれないなら、親に協力してもらってでも起こしてもらいましょう。また、起きてもスマホを見て立ち上がれないケース(②)も、開始が大幅に遅れる大きな要因です。
①〜⑤で決めた行動通りに動けば、10時間達成はぐっと近づきます。今すぐ①〜⑤の行動ルールを決めましょう。
スケジュールどおりに進まず勉強場所へ行くのが遅れた場合でも、30分以内の遅延は許容範囲とし、それ以上は絶対に遅れないよう強く意識すること
行動の阻害となるものを排除
勉強場所が決まり、勉強場所に行くまでの行動ルールが定まれば、ほぼ達成の準備が整ったと言っても過言ではありません。ただし、最後にひとつだけ必要なものがあります。
それは、10時間勉強の流れを邪魔する阻害要素を取り除く工夫です。
勉強開始前の阻害を取り除く
よくある阻害の正体
✔︎ 友だちからのお誘い連絡
✔︎ スマホの通知やSNS確認
✔︎ 外出が不快となる天候
✔︎ 服選びに時間がかかる
✔︎ 持ち物の準備が面倒くさい
✔︎ 家族との雑談
起床後から勉強場所へ向かうまでの行動において、阻害要因となりやすいのが上記6つです。友だちの誘いについては、受験期であれば断り、受験期でない場合は頻度が多ければ回数を減らし、少なければその日を息抜き日と割り切りましょう。
また、服選びや持ち物の準備は当日の朝に行うと失敗の要因になりやすいため、必ず前日の夜に済ませることを徹底してください。
スマホは手に取れる場所にあるだけで誘惑に負けやすいため、1日の勉強を終えた後に1〜1.5時間ほど自由時間を設け、その中で閲覧するなど「スマホ時間」をあらかじめ設定しておく
勉強開始後の阻害を取り除く
よくある阻害の正体
✔︎ 眠気と仮眠
✔︎ スマホの通知やSNS確認
✔︎ 疲れや飽き
勉強を始めた後の阻害要素は、ある程度決まっています。食後の眠気は我慢せず、15〜35分ほど時間を決めて、突っ伏さずに座ったまま仮眠をとりましょう。
スマホは持ち込まないのが最善です。どうしても必要なら、充電を20%以下にして出かける、電源を切るなど、できるだけ触らない工夫をして鞄に入れてください。
疲れや飽きへの対応は、以下「10時間勉強を実現する勉強計画」で紹介します。
10時間勉強のための勉強計画
10時間もの勉強となると、しっかり計画を意識しなければ、時間だけが過ぎて中身の伴わない勉強になってしまいます。以下2つの計画性を意識しましょう。
Step1 勉強する量を具体化する
各科目の教材ごとに、完成までに取り組む目標量を設定しましょう。たとえば、参考書1冊の完成目標を3周とする場合、その総ページ数が達成すべき目標量となります。
❶で決めた参考書を進める際は、1時間あたりのおおよその進み具合を把握しておきましょう。進めるうちに変動することもありますので、あくまで目安で構いません。
達成すべき量と1時間あたりの進度が決まれば、達成に必要な合計の勉強時間を算出できます。最後に達成までの期間を設定すれば、1日あたりその教材に何時間割くべきか、必要な勉強時間が明確になります。
| 参考書のページ数 | 200 × 3 p |
| 1hで進むページ数 | 8 p |
| 達成したい期間 | 50日 |
| 数学の勉強時間 | 1日1.5時間 |
これを各科目の教材ごとに行い、1日10時間勉強する日は何をどれくらい取り組むのか、大まかでもよいので計画を立てておきましょう。
Step2 不快でない順に勉強する
10時間勉強を目指す日に取り組む科目と教材が決まったら、次に決めるべきは勉強の順序です。1日を通してできるだけ苦痛を感じずに勉強できるよう、以下の確認作業をしてみてください。
確認作業1
各科目の教材ごとに、好みの度合いに応じて順位を数値で割り振る
確認作業2
各科目の教材ごとに、負担の軽さに応じて順位を数値で割り振る
| 科目 | 教材 | 好み順 | 軽さ順 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 英 | 単語熟語帳 | 7 | 1 | 8 |
| 英 | 長文参考書 | 6 | 7 | 13 |
| 英 | 英作参考書 | 4 | 5 | 9 |
| 数 | 基礎参考書 | 3 | 3 | 6 |
| 数 | 応用参考書 | 1 | 8 | 9 |
| 物 | 演習参考書 | 2 | 6 | 8 |
| 化 | 演習参考書 | 5 | 4 | 9 |
| 国 | 古文単語帳 | 8 | 2 | 10 |
合計の数字が小さいほど、自分にとって不快感がない教材学習になります。あとは以下の流れに沿って、1日の時間帯ごとに教材を割り振れば、自分に合った勉強環境と勉強計画が完成します。
| 午前第1の勉強 | 最も不快感がある教材 |
| 午前第2の勉強 | 2番目に不快感がない教材 |
| 午前第3の勉強 | 3番目に不快感がある教材 |
| 午後第1の勉強 | 最も不快感がない教材 |
| 午後第2の勉強 | 2番目に不快感がある教材 |
| 午後第3の勉強 | 3番目に不快感がない教材 |
| 夜間第1の勉強 | 4番目に不快感がある教材 |
| 夜間第2の勉強 | 4番目に不快感がない教材 |
上の表は、時間帯ごとに勉強に飽きや疲れが出やすいタイミングを示しています。この表に沿って、先ほど決まった「不快感が少ない順」の教材を当てはめ、1日の勉強計画を立ててみましょう。
失敗したときのルールを決める
毎日勉強を続けていると、目標を達成できない日もあります。そのときの対処法を誤ると、10時間勉強の継続はさらに難しくなってしまいます。
目標量に到達できなかった場合
ルール1
翌日に、その日にできなかった分量を丸ごと足さないこと。できなかった分量は、1ヶ月以内に処理すればよいという気持ちで、翌日には1ページ分など、ほんの少しだけ追加して取り組むようにする。
勉強計画でよくある失敗は、自分の許容量以上にハードルを上げてしまい、失敗が重なることで挫折してしまうケースです。
10時間勉強では日々の誤差が生じやすいため、その日にできなかった分は仕方がないと割り切り、1ヶ月などといった長いスパンで取り返すつもりで調整しましょう。
1日ごとに1分、1ページなど、苦痛を感じにくい範囲から少しずつ増やしていくこと
イレギュラーが発生した場合
ルール2
10時間勉強の達成が難しくなりそうなイレギュラーに備えて、代替策を事前に考えておくこと
日によっては、午前中に急な用事が入ったり、夜に家族と外食することになったりと、想定外のイレギュラーが発生することもあるでしょう。
このときによくあるのが、想定外の出来事に対応できず、その日の勉強が疎かになり、習慣が途切れてしまうケースです。
代替策を講じても達成できない分については、仕方のないことなので気にする必要はありません。ただし、事前の対策でできる限りの工夫はしておきましょう。
たとえば家族旅行や外食が入った場合でも、移動中の車内や料理を待つ時間などに取り組めるよう、英単語や化学の無機分野など覚える要素が多い学習を割り当てられるようにしておきましょう。
そのためにも、イレギュラー時に比較的取り組みやすい勉強内容を、あらかじめ決めておくことが大切です。
たとえば午後にイレギュラーな用事が入った場合でも、図書館が9時からしか開いていないとしたら、6時に起床して1時間半は自宅で勉強し、その後準備をして図書館へ行き、9時から12時近くまで勉強するといった調整が可能です。
あらかじめ「どう入れ替えれば勉強量を最大化できるか」を想定しておけば、その日の後悔を減らせます。「どうしたら勉強量が最大になるか」という軸で考える習慣をつけておくとよいでしょう。
達やり切った上で達成できなかったときに「今日は仕方がなかった」と思うのは問題ありません。しかし、やり切る前からそう言い訳してしまうと、目標に対して逃げ道を作る癖がつきます。
イレギュラーな状況でもできることは必ずあるので、まずはその場でできることに力を注ぐ意識を持ちましょう。
受験対策していますか?
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。
10時間勉強する休日ルーティン
以下は、休日に10時間勉強する日のルーティン例です。流れを参考にしながら、自分の生活に合うようにカスタマイズしてください。
就寝前に、翌日持っていく教材をリュック(カバン)に入れ、玄関近くに置いておく。明日着る服も畳んで、ベッド(布団)のそばに用意しておく。
就寝直前に「明日は7:00に起きる」と10回声に出して意識し、目覚ましは「7:00, 7:01, 7:02, 7:03…」と複数回に分けて設定する。これでも起きられない場合は、7:00に起こしてもらえるよう保護者にお願いする。
7:00に起床し、スマホのアラームを止めたら、SNSなどは見ずにその場でいったん座る。10秒間、立つ心構えを整え、10秒後に立ち上がって、パジャマから用意しておいた私服に着替える。スマホは私服のポケットに入れ、そのまま洗面所へ向かう。
まず水で顔を洗い、タオルで拭いたら、そのタオルを持って服を着たまま浴室へ向かう。最初だけ冷水シャワーで頭を濡らし、必要に応じて徐々にぬるめに切り替えてもかまわない。髪を拭いて浴室を出たら、ドライヤーで乾かして髪を整える。なお、髪が長くて濡らしたくない場合は、顔を洗うだけでもかまわない。
❸のステップが終わったら、うがいをし、コップ1杯(約200ml)の水を飲んでから朝食をとる。このときスマホは見ないこと。どうしても見たい場合は朝食中のみ可とし、食べ終えたらすぐにポケットにしまう。
朝食が済んだらすぐ洗面所に向かい、歯磨きをする。歯磨き中もスマホは見ないこと。どうしても見たい場合は歯磨き中のみ可とし、終わったらすぐポケットにしまう。
出発前の準備として、必要に応じてお手洗いを済ませておく。ここは時間が延びがちなので、目標時刻を2つ設定しておく。第1は「何時までに済ませたいか」、第2は「何時になったら必ず切り上げるか」である。
用意しておいたリュック(カバン)を持って家を出て、勉強場所へ向かう。いったん家を出てしまえば、その日の勉強はおおむねうまく進む。まずは「家から出る」ことを意識すること。
勉強場所に着いたら、机には教材と筆記用具だけを出す。スマホは家に置いてくるのが最善だが、やむをえず持参する場合は、その場で電源を切り、リュック(カバン)の中に入れて視界に入らないようにする。
まずは、その日取り組む教材の中で最も不快感のある教材(タップで定義を再確認)から始める。朝いちばんは脳がリフレッシュしていて集中しやすいため、苦手を先に片づけると、その後の勉強がスムーズに続く。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量にとる
・ 突っ伏して寝る
休憩から戻ったら、次は2番目に不快感がない教材(タップで定義を再確認)に取り組む。朝いちで最も嫌な勉強を済ませた直後はやや疲労が出やすいため、できるだけ不快感の少ない教材を選ぶのがおすすめである。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
休憩から戻ったら、午前ラストは3番目に不快感がある教材(タップで定義を再確認)に取り組む。午前は集中しやすい一方で終盤は疲れが出やすいため、不快感のあるものの中でも程度が軽い教材を選ぶのがおすすめである。
昼休憩は最大でも約1時間とする。コンビニやお弁当で簡単に済ませても、10時間勉強のご褒美として外食してもかまわない。ただし、大盛りラーメンや大量のジャンクフードなど糖質過多は、食後の強い眠気につながるため、選ぶメニューには注意すること。
昼休憩から戻ったら、午後の最初は最も不快感がない教材(タップで定義を再確認)に取り組む。午後いちばんはモチベーションが下がり、眠気も強くなりやすいため、不快感の少ない教材を選ぶのがおすすめである。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
休憩から戻ったら、次は2番目に不快感がある教材(タップで定義を再確認)に取り組む。直前に最も取り組みやすい教材を済ませているため飽きは比較的少ない一方、午後の中でも眠気が出やすい時間帯である。強い眠気を感じたら、短時間の仮眠をとるのが有効である。
仮眠の仕方
机に突っ伏して寝ると寝過ぎにつながるため、椅子に座ったままうつ伏せにならずに15〜35分の仮眠をとる。目覚めたら水分補給をし、その後お手洗いへ行って強制的に覚醒を促すとよい。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
休憩から戻ったら、次は3番目に不快感がない教材(タップで定義を再確認)に取り組む。勉強への飽きが強まりやすい時間帯なので、ここがひと踏ん張りの関門である。
この時点で疲労と飽きがかなり蓄積しているため、40分程度の長めの途中休憩を入れるとよい。コンビニ等で軽く間食をしても、勉強場所の周辺を散歩してもかまわない。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
途中休憩から戻ったら、次は4番目に不快感がある教材(タップで定義を再確認)に取り組む。長めの休憩である程度リフレッシュされているため、比較的スムーズに学習が進みやすい時間帯である。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
休憩から戻ったら、次は4番目に不快感がない教材(タップで定義を再確認)に取り組む。疲れは溜まっているが、1日の終わりが見え始める時間帯でもあるため、比較的モチベーションを保ちやすい時間である。
10分ほど休憩をとり、水分補給をしてからお手洗いに行く。勉強場所の室内を少し歩いて気分を切り替え、席に戻る。
・ スマホをいじる
・ 糖質を大量に摂る
・ 突っ伏して寝る
ここまで来ればラストスパート。1日のうち、まだ目標量を終えられていない内容に取り組む。これが終われば勉強場所から解放されるため、最後の踏ん張りで力を発揮しやすい時間帯である。
勉強場所での1日の学習を終えたら、水分補給とお手洗いを済ませ、帰りの支度をして家へ向かう。
家に着いたら、手洗い・うがいを済ませてから夕食をとる。
夕食を食べ終えたら入浴タイム。疲れが溜まっている場合は湯船に浸かり、あまり疲れていない場合は時間短縮のためシャワーだけで済ませてもよい。
40〜50分ほどの自由時間を確保し、この時間でスマホをチェックしたり、Netflixなど途中で切り上げやすいコンテンツを楽しむとよい。ただし、長編映画のように途中でやめにくい娯楽はできるだけ避けること。
自室で仕上げの勉強をする。おすすめは、本日の未達分の勉強、英単語の暗記、英語リスニング対策、1日の総復習などである。日によって最適な内容を見極め、使い分けること。
ここまでで1日のルーティンは終了。明日の準備と就寝準備を済ませ、睡眠は少なくとも6時間、できれば7時間を目標に確保するとよい。
今の合格可能性を診断
「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?
ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…
現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。
そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。
今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。
目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。
今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。
基礎の徹底が超重要!
「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?
同級生は成績も上がってきているのに…
このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。
5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。
気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。